第九章 悪夢の宴(前編)
祭の日の朝は早い。夜明けと同時に島中の夢術師及びその弟子たちが一斉に夢晶体を紡ぎ出し、野に放つ。
腕によりをかけ紡ぎ出された夢晶体たちは普段とは異なり、祭の日が終わるまで溶けて消えることはない。
夢追いの祭は特別な一日。一年のうちで最も夢見の女神の影響力が強まる日だ。島の大気中には常より濃い夢粒子が漂い、この日だけは夢雪を使わなくても、ただ杖を振るだけで夢晶体を紡ぎ出すことができる。島で夢術を使えるありとあらゆる者が好きに夢晶体を紡ぎ出し、島は一日中、夢幻の生物や美しい幻想で溢れかえる。
だが、この祭の何よりの目玉は、まるで女神そのもののように美しく着飾った夢見の娘のパレードだ。
正午になると同時に小女神宮を出発するパレードは、クリスタルガラスでできたクラシックカーに、虹色の蝶の群れが運ぶ花の輿、ペガサスとユニコーンが引く宝石細工の馬車と次々に乗り物を変え、夢見の娘の紡ぐ夢晶体を引き連れて島中を巡るのだ。
「フラウラさん、もうちょっと頭下げて。……うん、そう。じゃあ載せるわよ」
綺麗に整えられたラウラの髪の上に、
ミルククラウンのような形をした透明な宝冠が載せられる。
女神の涙と呼ばれる聖なる泉の水面に水滴が落ちた瞬間を、
雪の女王の吐息により一瞬で凍らせ、特殊な断熱加工を施した“涙珠宝冠”だ。
耳には“貴婦人の耳飾り”の異名を持つ優美な
フクシアの花を飾り、首にはカスミソウと
淡水真珠で編まれた繊細で儚げな印象の
ラリエットを巻く。足に履くのは、硝子のような光沢と透明度がありながら、同時に絶妙な弾力と伸縮性をあわせ持つ“
クリスタル・ドラゴンの鱗”の革靴だ。

そしてその身にまとうのは“
空織のドレス”。島の南西“
空鏡塩原”で採れる“空映しの水”に丸一日浸した糸を使い、地平線まで続く広い草原の大きな空の下、数十人がかりで織り上げられたそのドレスの布地は、昼は澄んだ
セレスト・ブルーに白い雲模様、夕方は燃えるような夕焼けの茜色、夜は濃紺から黒のグラデーションに金銀の星のラメと刻々とその色と模様を変えていく。その時々の空模様を生地の上に浮かび上がらせる特殊なドレスなのだ。

多くの島民の手をかけて作られたこれら夢見の娘の衣裳は、夢追いの祭のただ一日のためだけに用意されたもの。祭が終われば全て炎に投じられ、女神の元へ還される運命にある。
「……よし!いい感じだわ。即興でやったわりには我ながら良い出来ね。ドレスの方も何とか見映えが良くなったし」
衣裳の着付け及びヘアメイク担当の
マリアン・カリヨンがやや遠くからラウラの全身を眺め、満足そうに頷いた。
「でも、少しバランスが悪い気がします。リリアン、左肩の所、リボンを追加してみてください」
衣裳のデザイン担当である
ミリアン・カリヨンが冷静に指示を出す。
「はいはーい。でもぉ、私としては肩だけじゃなくてもっとあちこちにリボンとかレースとかフリルとか、ゴージャスに縫いつけたいんだけど」
縫製の総責任者
リリアン・カリヨンが縫い針を手に伺うように姉を見る。
「ダメです。夢見の娘の衣裳は島の古い文献を元に、夢見の女神の最古の衣裳を再現したもの。多少のアレンジは許されても、あまりゴテゴテ盛り付けては女神の清楚なイメージを損なってしまいます。それに、もう時間もそれほど無いでしょう」

言ってミリアンはちらりと柱時計に目をやった。
「え……っ、うそっ、もうこんな時間!?やばっ、私としたことが衣裳のサイズ変更ごときでこんなに時間をとられるなんてっ」
「まぁ、それは仕方が無いでしょう。サイズだけでなく、フラウラさんの印象に合わせてデザインも多少変更しましたし」
既に用意されていた夢見の娘の衣裳は、全てアメイシャをイメージしてデザイン及び製作されたものだ。当然ラウラにはサイズが合わず、デザインも大人っぽ過ぎてラウラには似合わない。それを何とか調節するために、夢見の娘の衣裳に係わるカリヨン三姉妹が早朝から集まって作業を続けてきたのだ。

「あの……、いろいろとすみません。朝早くからご迷惑をかけて……」
ラウラが恐縮して頭を下げると、マリアンは軽く顔をしかめてみせた。
「こら、ダメよ。あなたは今日は女神の娘なんだから、そんな顔してちゃダメ。それにあなたのせいじゃないもの。謝る必要なんて無いわ」
「そうそう。あんたは余計なことなんて考えずにパレードにだけ集中してなさい。それに、これはなるべくしてなったことだって私は思うわ。アメイシャよりあんたの方が夢見の娘にふさわしいって、私は今でも思ってるし」
マリアンの言葉に同意するように何度も深く頷きながら入室してきたのは、普段のラフな格好とは違い、純白のワンピースの上にきっちりとローブを着こなしたキルシェ・キルクだった。
「……キルシェちゃん、それに、アプリちゃんも……」
アプリコットもキルシェと同じ姿でこちらに歩み寄ってくる。二人は今日は夢見の娘の
介添役として一緒にパレードを巡るのだ。本来であればラウラも同じように介添役としてアメイシャのパレードに同行するはずだったのだが……。

「アプリちゃん……メイシャちゃんは、大丈夫?」
ラウラは硬い声で問う。キルシェとアプリコットは何とも言えない表情で顔を見合わせた。
「……ショックを受けて部屋に引き籠もっているわ。アメイシャの性格からして、私たちから慰めの言葉なんて欲しくはないでしょう。今はそっとしておいてあげて」
ラウラは無言でうなずく。夢に見た夢見の娘になれたというのに、胸を満たすのは複雑な思いばかりで、喜びも嬉しさも一向に湧いて来ない。
「もうっ!辛気臭いのはやめにしましょ!私たちがへこんでたところでアメイシャのことはもうどうにもならないんだから。それよりスマイルよ、スマイル!祭の主役、夢見の娘がそんな顔しててどうするの!」
キルシェがその場に漂う重い空気を吹き飛ばすように明るく言う。
「うん。そうだよね。ピンチヒッターでもちゃんとやらなきゃ、お祭を楽しみにしてる皆に悪いもんね」
「それじゃあ行きましょう。もう準備はできているわ」
アプリコットが色とりどりの絹リボンで飾られたラウラの銀の匙杖を渡してくる。ラウラはそれを、ややぎこちない笑顔で受け取った。
「夢より紡ぎ出されよ!“めくるめく四季”パレード・バージョン!」
ラウラが銀の匙杖を振ると、杖の先から色とりどりの花々が飛び出してきた。それらは互いに茎と茎を絡ませ合い、ひとりでに花冠となって沿道の人々の頭の上にふわりふわりと載せられていく。ラウラの好きな“春”の姿だ。

次いでラウラが杖を振ると、今度は先端から瑞々しい若葉の群れが飛び出してきた。パレードを囲むように一面に広がった緑の葉のカーテンには、まるで水面に反射した日光のような、涼やかな金の波模様が描かれる。
ラウラはパレードの進行に合わせ、何度も杖を振る。そのたびに杖の先から出るものは変化していく。
若葉の次には錦絵のように色鮮やかな紅葉、その次には陽光にきらめくダイヤモンドダスト。そしてその後は再び花の冠。全てラウラが四季の光景の中で“好きなもの、綺麗だと思ったもの”だ。沿道の人々は歓声を上げてラウラの紡ぐ夢に見惚れた。だがその中に、その夢術から目を逸らすようにうつむく者がいた。小女神宮の部屋をこっそり一人で抜け出したアメイシャ・アメシスだ。
彼女は目深にかぶったフードの下で唇を噛みしめる。我慢できず見には来たものの、その胸にはやはり昏い感情しか湧いてはこなかった。本来であれば、あの場で喝采を浴びているのは彼女のはずだったのだ。
アメイシャはうつむいたまま人の輪からそっと離れる。どこか静かな所、祭の喧騒の届かぬ所へ行きたかった。
街を抜け、橋を渡り、濠のように丸く都を取り囲む川を越えると葬花砂漠――花雲から降った花びらが、いつしか都の外に風で運ばれ、色鮮やかなまま砂となり、そっと葬られる場所だ。
砂を踏みしめるたびに花の香の立ち上るこの砂漠は、その場所場所によりまた細かく呼び名が分かれている。黄色い砂ばかりが広がる黄花砂漠に、薄紅色の砂が広がる桃花砂漠、幾色もの砂が混じり合う七色砂漠、そして今アメイシャの進む純白の砂漠は白薔薇砂漠と呼ばれている。甘い薔薇の香の漂う、まるで雪原のように真っ白な、地平線まで続く砂漠だ。
しばらく行ったところでアメイシャは下腹部の痛みに思わずうずくまった。少しも自分が望んだものではないその痛みに眉を寄せ、彼女は全てを投げ出すように砂の上に横たわる。甘やかな香りに包まれながら、アメイシャは全てを拒むかのように固く、固く目を閉じる。
「……なぜなんだ。なぜ、こんなことで夢見の娘の座を奪われなければならない?」
固く閉じた瞳から、涙が溢れて頬をつたう。
「何という理不尽だ。こんな、自らの意思ではどうにもならない肉体の成長によって、夢を奪われなければならないのか?こんなことで、今までの努力の何もかもが否定されるなど……認めない。そんな世界は、私が絶対に認めない」
アメイシャの唇から低く小さな笑いが零れだす。ラウラが己の全てを懸けて夢見の娘という夢を追っていたように、アメイシャもまた、己の人生を懸けてその夢を追っていた。そうしなければならない理由が、彼女にはあった。
――『アメイシャ、あなたなら最高の夢見の娘になれるわ。母さまに叶えられなかった夢を、あなたなら叶えられる』
脳裏に蘇るのは母の声。自らの果たせなかった夢を娘に託し、まるで刷り込みのように何度も何度も言い聞かせ続けてきた母親の声だった。
まるで呪いのように刻みつけられたその言葉が、いつしかアメイシャの存在理由となっていた。それが砕け散ってしまった今、アメイシャの心は空っぽだった。この先何をすれば良いのか、何をしたいのかすら分からない。今まで通りに食事をし、眠り、当たり前の日常を送る気力すら失われて、それでも『死んでしまいたい』という思いすら浮かばぬほどの、ひたすらに空っぽで虚ろな心。
「……要らない。もう、何もかも消えてしまえばいい。運命が私を選ばなかったと言うなら、そんな運命を紡ぎ出す世界など、私は要らない。祭も夢見の娘もこの島も私も……全てなくなってしまえばいいんだ」
笑い声は徐々に大きくなっていく。アメイシャは涙を流したまま、狂ったように笑い続けた。
その笑い声に応えるかのように、純白の砂原に異変が現れた。雪のような白一面の世界に、まるでそれを汚すかのようにどこからともなく滲み出してきたのは、影のような黒い染みだった。
白い布に墨汁が染みていくかのようにじわじわと砂原を染めていくそれは、やがてくぷりと音を立て、空気をはらんで宙空に浮かび上がってくる。
分裂し、増殖しながら地表や宙をゆらゆらと漂うそれは、まるでシャボンの泡のようだった。ただしそれはシャボンの泡のように光を受けて七色にきらめくことはなく、むしろ光も色も何もかもを呑み込んでしまいそうな、どこまでも深淵な闇の色をしていた。
瞳を閉ざしたままのアメイシャは、己の身をゆっくりと覆っていくその闇に気づかない。
黒い泡は、まるで浸蝕するかのように彼女の身を覆っていく。まるで、彼女の存在そのものを闇に包み隠していくかのように……。
異変は島の各地で起きていた。葬花砂漠で泡が出現するのと同時に、島のあちらこちらで同様に地から黒い泡が湧き出していた。
黒い泡は島民たちの紡ぎ出した夢晶体を次々に呑み込んでいく。
呑み込まれた夢晶体たちは、皆その姿を禍々しく変化させていった。七色の蝶は毒々しいまだら模様の蛾に変わり、純白の小鳥は黒々としたコウモリに、長くひらめいていたリボンは長く躯をくねらせる蛇に、あらゆるものが不気味に変貌を遂げていく。
変質した夢晶体たちは、その身からこぽこぽと黒い泡を立ち上らせながら、ゆっくりと移動を始めた。
目指す先は皆同じ、世界樹の切株を取り囲む谷の一角。流星の谷と呼ばれるその場所は、多くの夢術師たちが暮らす学術都市であり、夢見の娘のパレードが最後に到達する祭のフィナーレの場所でもあった。

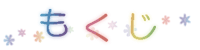


 の本文ページです。
の本文ページです。