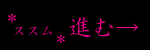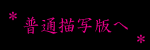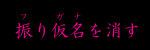序 花咲く頃に君を想う |
外は雨だった。けぶるように降る春雨 は、山々を白く霞 ませ、森の色を一層深く濃く見せていた。
「せっかくの月待 の日に、あいにくのお天気ですねぇ」
茶店の主人 が苦笑混じりに話しかけてくる。
「月待?……あぁ、今流行 りのアレか」
俺は適当に答え、茶をすする。月待とは月待講 のことで、いつの頃からか流行りだした月神信仰の一種だ。夜半 に出る二十三夜の月を待ち、月神に供物 を捧げて夜通しの宴を行えば、願いが叶うという。
「おや、お客さんは願掛けなさらないんですか?」
「あいにく、神に叶えられる類 の願いなど、持っておらぬからな。この辺りではそんなに月待が盛 んなのか?」
「へぇ、そりゃもう盛んですねぇ。特に、こんな風に龍神様の泪雨 の降る頃には。龍神様のご加護もあって願いが叶いやすいとか何とかで」
「龍神の……泪雨?」
さすがに聞き咎め、その言葉を繰り返すと、店主は笑って天 を仰 いだ。
「この雨のことですよ。この時季になると、この辺りの山で天 を飛ぶ龍神様のお姿が見られるそうで、いつしか春の、こんな風にしとしと降る雨を『龍神様の泪雨』と呼ぶようになったそうです。龍神様の流す泪が雨となり天から降ってくるのだと」
俺は何も答えずに茶を飲み干した。苦いものが胸に広がるのを感じる。
「馳走 になった。勘定 を頼 む」
「もう行かれるんですか?まだ雨は止 んでおりませんよ」
「構 わん。これしきの雨、大 したことではない」
勘定を済ませ、そのまま店を出ようとし、俺はふと思いついて店主に声を掛けた。
「そうだ。お前、花は好きか?」
「花?へぇ、好きと言えば好きですが」
「ならば、これをやろう」
渡された花の種に店主は首を傾 げる。
「これはどうも。で、これは何の種なんです?」
「幸 を呼ぶ花の種だ。『自分以外の誰か』の幸を強く願って育てれば、やがて花咲く時、見る者全てに幸を与えてくれる」
「へ……?」
店主の疑問の声には答えず、俺は今度こそ店を後にした。
「せっかくの
茶店の
「月待?……あぁ、今
俺は適当に答え、茶をすする。月待とは
「おや、お客さんは願掛けなさらないんですか?」
「あいにく、神に叶えられる
「へぇ、そりゃもう盛んですねぇ。特に、こんな風に龍神様の
「龍神の……泪雨?」
さすがに聞き咎め、その言葉を繰り返すと、店主は笑って
「この雨のことですよ。この時季になると、この辺りの山で
俺は何も答えずに茶を飲み干した。苦いものが胸に広がるのを感じる。
「
「もう行かれるんですか?まだ雨は
「
勘定を済ませ、そのまま店を出ようとし、俺はふと思いついて店主に声を掛けた。
「そうだ。お前、花は好きか?」
「花?へぇ、好きと言えば好きですが」
「ならば、これをやろう」
渡された花の種に店主は首を
「これはどうも。で、これは何の種なんです?」
「
「へ……?」
店主の疑問の声には答えず、俺は今度こそ店を後にした。
しばらく峠の道を行き、人気 が無くなったのを見計らい、俺は変化 を解いた。否 、新たに変化し直したと言った方が正しいかもしれない。
俺の姿は、人の形から、銀の鱗 に覆 われた長大な龍の姿へと変じていた。そのまま俺は前肢 で空 をかき、灰色に曇 った天 へ向け、滑 るように泳ぎだす。
そう、この辺りの村人がこの時季に見るという龍神とは、俺のことだ。ただし、今降るこの雨は俺の泪などではない。俺の泪はとうに涸 れ果て、おそらく、もう流れることはない。けれど、もしもこの雨が、もう泣くこともできぬ俺の代わりに天 が流す泪なのだとしたら、俺も少しは救われる気がする。
俺の姿は、人の形から、銀の
そう、この辺りの村人がこの時季に見るという龍神とは、俺のことだ。ただし、今降るこの雨は俺の泪などではない。俺の泪はとうに
絹糸のような雨に鱗を洗われながら天を泳いでいくと、緑一色だった眼下に、ふいに鮮やかな色彩が現れた。それは、険しい山々の合間に隠れるように存在する花園。急峻な崖に守られ、俗人 では登ることも下りることもできぬ、秘められた花園だ。俺は再び人の姿へと変じ、そこへと降り立った。
花園の中央には、まるで墓標のように一本の木が立っている。俺はいつものようにその木に歩み寄り、愛 しむようにその木肌に触れた。そうして、呼びかける。この木の下に眠る、もうどんなに呼んだところで声の届くことのない君へ。
花夜 、俺は君を忘れない。幾百の歳月を越えて尚 。
目を閉じれば、今でも君との思い出が蘇 る。君と過ごした、短い、けれど幾百の歳月 にも勝るほどに濃く、満ち足りた日々が……。
花園の中央には、まるで墓標のように一本の木が立っている。俺はいつものようにその木に歩み寄り、
目を閉じれば、今でも君との思い出が