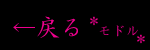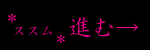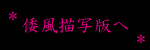第四章 |
俺達は一旦 、霧狭司 の兵士の手により拘束 され、国府の奥にある倉の一つに監禁 された。その扱いはとても神聖な巫女姫に対するものなどではなく、霧狭司が花夜のことを先代の社首 でも姫でもなく、単なる侵入者としか見ていないことは明白だった。
倉の中は昼でも隙間 から微 かな光が差し込むばかりで、隣 にいる花夜の姿さえ暗がりにぼんやり沈んでいるように見える。膝 を抱 えて座り込んだまま一言もしゃべらずにいる花夜に、俺はひっそりと問いかけた。
「お前、なぜ雲箇 の言葉を信じる?己の父が信じられないのか?」
俺はこの時まだ、雲箇の言葉を信じきれてはいなかった。一国の首長 としての決断とは言え、血を分けた己の娘をそう簡単に見棄 ててしまえるものなのかと疑問に感じていたからだ。まして、こんなにも健気 に国を想う花夜のことを、非情に切り捨てるなど、できるものなのだろうかと。
「……もしかして、表情にでも表れていましたか?私が父を信じきれていないことが」
それは彼女にしては珍しい、どこか皮肉混じりの声音 だった。
「ああ。お前のその瞳で分かった。口では違 うと言いながら、瞳は既 に何かを悟 ったような色をしていた。自分が棄 てられることさえも『有り得 ること』と、初めから全てを諦 めているかのような……」
その言葉に隣から苦笑するような気配が伝わってくる。花夜はうなずき、疲 れたような声で言った。
「そうです。私は、父を信じていません。雲箇 姫の言葉を否定したかったのは本当です。でも、それが否定しきれぬ真実だと、あの時既 に分かっていました。私は、父にそうされても仕方がない人間です。私は……父に、憎 まれているから……」
ひどく思いつめた顔で花夜が話し出したその時、ふいに柔 らかな声が室内に響いた。
『それは、あなたのせいではありません』
その声は花夜の腰に吊 るした五鈴鏡 から響いていた。それは触 れてもいないのに勝手に裏返り、ほのかに光をたたえた鏡面 を表に向ける。光は次第に強さを増し、鏡面から盛り上がり、やがて鳥の形となって鏡から飛び出してきた。
「母さま!?」
驚いたように名を呼ぶ花夜の前で、光はゆっくりと人の形をとっていく。
『改めまして、お初にお目にかかります、ヤトノカミ様。花夜の母・鳥羽 と申します』
光の中から顕 れたその姿に、俺は目を見張った。
「お前は……鳥神 の巫女だったのか」
初めて目にした人の姿の鳥羽は、花蘇利のような小国では首長 の妃 といえど決して身につけられぬはずの、高度な技術による衣裳 を身につけていた。おまけに、独特な形の袖 を持つ上衣は『天 の羽衣 』と呼ばれる、鳥神に仕 える巫女に特有のものだ。
『はい。私はかつて、ここより西の海辺に在 る『水鳥 多集 く羽真那国 』の姫であり、国の鎮守神 たる鳥神様に仕える社首 でした』
「ばかな。なぜそれが花蘇利 の首長の妃になどなっているのだ?神に仕える巫女に手をつけるのは大罪。しかもそれが他国の姫ともなれば尚更 のことのはず……」
『その理由は、これからお話しいたします。私がなぜ、あの人の妃となったのかを。そして花夜がこれまでこの国で、どのような目に遭 ってきたのかを……』
そうして鳥羽は語りだした。己の過去を。そして、花蘇利国 でかつて何があったのかを……。
倉の中は昼でも
「お前、なぜ
俺はこの時まだ、雲箇の言葉を信じきれてはいなかった。一国の
「……もしかして、表情にでも表れていましたか?私が父を信じきれていないことが」
それは彼女にしては珍しい、どこか皮肉混じりの
「ああ。お前のその瞳で分かった。口では
その言葉に隣から苦笑するような気配が伝わってくる。花夜はうなずき、
「そうです。私は、父を信じていません。
ひどく思いつめた顔で花夜が話し出したその時、ふいに
『それは、あなたのせいではありません』
その声は花夜の腰に
「母さま!?」
驚いたように名を呼ぶ花夜の前で、光はゆっくりと人の形をとっていく。
『改めまして、お初にお目にかかります、ヤトノカミ様。花夜の母・
光の中から
「お前は……
初めて目にした人の姿の鳥羽は、花蘇利のような小国では
『はい。私はかつて、ここより西の海辺に
「ばかな。なぜそれが
『その理由は、これからお話しいたします。私がなぜ、あの人の妃となったのかを。そして花夜がこれまでこの国で、どのような目に
そうして鳥羽は語りだした。己の過去を。そして、
それは花夜の父・萱津彦 が父親を戦 で亡くし、まだ二十歳 にもならぬ若さで首長の座に就 いてから、しばらく経 った頃のことだった。花蘇利の浜辺に一艘 の刳舟 が流れ着いた。中にいたのは気を失って倒れ伏した一人の少女。
それは白鷺 を思わせるほっそりとした首と真珠 のように白い肌を持つ、繊細 に整った顔立ちの少女だった。
しかも彼女は花蘇利の民が今までに目にしたことも無いような衣裳 に身を包んでいた。胸元を赤い紐 で結んだ白い上衣は極上 の柔らかさを持つ練絹 で織られ、しかもその袖 は細かなひだを重ね、鳥の翼を模 したかのような不思議な形をしていた。足先までを覆 う長い裳 は色鮮やかな朱華 色。肩に掛 けられた生絹 の領巾 には鳥の羽根の模様が摺 りつけられ、高く結 った髪の根元にも、やはり大きな鳥の羽根が飾 られていた。幅広 の腰帯には五つの鈴を持つ鈴鏡 。高い身分を窺 わせるように、耳には金の耳飾りが揺 れ、首にも勾玉 と丸玉の首飾りが二重に巻かれていた。
腰に鈴鏡を帯 びるのは東国 では巫女の証 。泥 に汚 れてはいても、その衣裳が神棲 まぬ国には到底 作れぬような高度な技術で作られた上等な巫女装束 であり、それを身に着ける少女が何処 かの国で神に仕える高貴な巫女姫であることは誰の目にも明らかだった。
話を聞き駆 けつけてきた萱津彦は、少女の姿を見るなり言葉を失った。しばらくの間は少女以外は目に入らず、何も考えられないような有様 だったと言う。そして敵国の罠 を疑う臣下たちの反対も聞き入れず、彼は少女を自らの館 に運ばせると、侍女 たちに命じ彼女を手厚く看護 した。
そんな萱津彦の姿に、臣下たちは悟らざるを得 なかった。この若き首長が、美貌 の少女に一目 で心奪 われてしまったことを。しかもそれは、萱津彦にとって生まれて初めての恋。それまでに彼が経験してきた戯 れの恋などとはまるで違 う、自分でも制御 しきれないほどの、狂おしく危 うい恋だったのだ。
それは
しかも彼女は花蘇利の民が今までに目にしたことも無いような
腰に鈴鏡を
話を聞き
そんな萱津彦の姿に、臣下たちは悟らざるを
萱津彦は少女に記憶が無いことを知ると、彼女が花蘇利に流れ着いた時に身につけていた一切のものを、首長と臣下以外は立ち入ることの許されない
神と
しかし神と巫との関係性はそれだけが全てではなく、たとえば伴侶としてではなく、親子や友人のような関係性を結んでいる神と巫も少なくはない。そうした場合は巫が神以外の人間と結ばれようと霊力を喪いはしないのだが、鳥羽もまた、そうした巫の一人だった。
妃となり、娘を産んでもなお、彼女の霊力は
神と契りを
彼女が花蘇利に来て以来、ありとあらゆる鳥の害がなくなった。里の田が
だが、そんな鳥羽が全てを思い出す時が、ある日突然
幼い少女が今までに目にしたこともないような美しい
「ねぇ母さま、見て見て。こんなきれいな
「まぁ……本当ね。きれいな衣」
鳥羽は初めのうち、ただ無心に衣裳に
「母さま!?どうしたの!?どこか痛いの?」
たまたま鳥羽の元へと向かっていた萱津彦は、その声を聞きつけ部屋に飛び込み、花夜の姿を見るなり
「何をしている、花夜!その衣裳をどこで見つけた!?蔵には入るなと言ってあったはずだろう!」
思わず手を上げかけた萱津彦を、鳥羽は無言で制した。それから静かに立ち上がり、告げた。
「……思い出しました。全てを。私は、行かねばなりません。巫女として、国を救いに戻らねば」
萱津彦は
「私の真の名は、
「そうだ。あれからもう長い時が経つ。残念だが、お前の故郷が羽真那だと言うなら、その国は
己が付けた
「それでも、戻らねばなりません。あなたが花蘇利の
「行けば殺されるぞ!敵国に
「覚悟の上です」
「行かせない!行かせるものか!どうしても行くと言うなら、行けないように閉じ込めるまでだ!」
萱津彦は鳥羽の手首を
「花夜。これを渡しておきます」
かつての巫女装束 に身を包み、すっかり旅支度 を終えた姿となった鳥羽は、そう言って花夜に一面 の鏡を渡した。鳥羽が花蘇利の浜に流れ着いた時に腰に帯 びていた五鈴鏡 だ。
「私はもう、あなたのそばにはいられません。これを私と思い、大切にしなさい」
「いやだ、母さま!行ってはいや!行かないで!」
泣いて引き止める花夜の頭を撫 で、鳥羽は困 ったように微笑 んだ。
「そういうわけにはいきません。これは、私が私であるためにしなければならない務 め。私は羽真那の最後の社首 。私が解放して差し上げなければ、鎮守神 たる鳥神様は国と交 わした鎮守 の契約により彼 の地に永久に縛 られたまま、何処 へも行くことができません。私のことを実の娘のように可愛 がってくださっていた鳥神様を裏切ってこの国で平穏 に生きることなど、私にはできないのです。……許 してね、花夜。あなたやあなたの父さまを哀 しませるのはとてもとても辛 いけれど、それでも、私は彼 の地へ戻ることを選ぶのです……」
鳥羽がどんなに言葉をつくしても、花夜が納得 することはなかった。とにかく鳥羽を行かせまいと、必死に衣を握 り続けた。鳥羽はそんな花夜を無理に振り払うことはせず、ただ彼女が泣き疲 れて眠るまで、ずっと頬 や頭を撫 で続けた。
次の朝、花夜が目覚めた時、既 に鳥羽の姿はどこにもなかった。そして彼女が生きた姿で花蘇利に戻ることは、二度となかった。
かつての巫女
「私はもう、あなたのそばにはいられません。これを私と思い、大切にしなさい」
「いやだ、母さま!行ってはいや!行かないで!」
泣いて引き止める花夜の頭を
「そういうわけにはいきません。これは、私が私であるためにしなければならない
鳥羽がどんなに言葉をつくしても、花夜が
次の朝、花夜が目覚めた時、
最愛の妃を失った萱津彦の嘆 きようと怒 りは凄 まじいものだった。彼は花夜の頬を張り飛ばし、罵声 を浴びせた。
「お前のせいだ!お前があの衣裳を引っ張り出してなど来なければ、花名女 がこの国を去ることは無かったものを!」
「ごめんなさい、父さま。ごめんなさい。ゆるして……」
泣きながら取りすがる花夜を、それでも萱津彦は許さなかった。これ以降彼は娘に対し、言葉をかけることも触 れることもなくなった。父だけでなく周りの人間も、鳥羽の加護が無くなり秋の収穫 が減ったことで、花夜に対する目を冷たくしていった。今まで自分たちが、真実を偽 って鳥羽を花蘇利に引き止めていたことからは目を逸 らし、ただ鳥羽がいなくなったことに対する責任を、全て花夜一人に背負わせ責めたのだ。
だがその一方で、鳥羽の娘である花夜が何らかの霊力を受け継 いでいることに期待し、幼い花夜を社首 に祭り上げようとする人間たちもいた。しかし、巫の加護は神と契 りを結んで初めて効力を発揮 するもの。たとえ血を受け継 いでいたとしても、鳥神と契りを結んでいない花夜がその加護を顕 せるはずもなかった。
社首にはなったものの、鳥羽のような霊力を一切顕 すことのできない花夜は、やがて全てから見放され、かと言って首長 の姫という立場ゆえ、あからさまに冷遇 することも、一度就 けた社首の座から特別な理由もなく降 ろすこともできず、ハレモノのように扱 われることとなった。唯一の慰 めは、無事に務めを果たした鳥羽が死の間際 、残りの霊力の全てを費 やし、娘を見守る霊鳥へと姿を変えて舞い戻ったことだった。そうして花夜は、母の霊だけを唯一の味方とし、頼 る者の誰もいない国の中で一人、生き抜いてきたのだ。
「お前のせいだ!お前があの衣裳を引っ張り出してなど来なければ、
「ごめんなさい、父さま。ごめんなさい。ゆるして……」
泣きながら取りすがる花夜を、それでも萱津彦は許さなかった。これ以降彼は娘に対し、言葉をかけることも
だがその一方で、鳥羽の娘である花夜が何らかの霊力を受け
社首にはなったものの、鳥羽のような霊力を一切
「なんという身勝手な話だ。花夜、お前は国の
「憎んでいないと言ったら、
それは皮肉も
「私は、これまでずっと母のようになろうと努力してきました。言葉や
そこまで言って、花夜は顔を
「ごめんなさい、ヤト様。私はこのように
泣きそうな顔で、おそるおそる花夜が問う。俺は深々とため息をついた。
「するわけがないだろう。一緒にいたのは短い間だが、お前の
「ヤト様……」
花夜は
「ありがとうございます。……ヤト様が、私の神様で良かった」