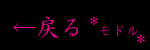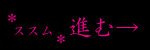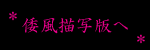| 第十一章 追憶に沈む大刀 |
『真大刀 、宮処 が陥落 したというのは本当なのか?』
俺の問いに、真大刀は硬 い表情でうなづいた。
「……ああ。そのようだな」
俺が郷 にいた四年の間、霧狭司国 は鯨鯢国 の周りの国を次々と攻 め滅 ぼしていた。
しかもそうして滅ぼした国々をきちんと統治 するでもなく、富や人材を根こそぎ奪 い去 ると、後は朽 ちるに任 せ放置しているような有様 だった。
その手はとうとう鯨鯢国にも及 び、小国であるこの国は数日ともたず宮処を奪われてしまった。だが鉄砂郷 は宮処よりさらに北の山の奥深くに位置していたため、この時はまだ霧狭司の兵士の手も及んでいなかったのだ。
「……宮処を陥落 させた敵の将が父に使者を送ってきた。『霧狭司に下 り、これからは霧狭司のために武器を作れ』……と。だが我々はそれに従うつもりはない」
その声は怒 りによってか、微 かに震 えていた。
『戦う気なのか?』
「ああ。幸運なことに武器ならば揃 っている。ここは鍛冶 の郷 だからな」
『だが、実際に大刀 を振るった経験のある者など、ここにはいないだろう』
その問いかけに、真大刀はしばし無言になった。勝ち目など無いことは今さら問わずとも最初から明らかだ。それでも戦うと、真大刀はそう言っているのだ。
「鉄砂郷 で作られる武器は他を滅ぼすためではなく、大切なものを守るためにこそ存在するもの。この郷 に生まれた鍛冶 ならば、必ずそう教えられて育つのだ。霧狭司 に下れば、その誇 りを失うことになる。霧狭司国は我々の鍛 えた武器を他国を滅ぼし、命を奪うことに使うだろう。それは間接的に我らが手を下すのと同じことだ。今までと何も変わらぬ何気 ない我らの日々の暮らしや生業 が、何処 かで誰 かに苦しみを与え、悲しみを生み出すことになるのだ。そのようなこと、耐 えられぬ」
その気持ちは理解できたが、その決意は無謀 としか思えなかった。だがその心を変えられる言葉を、俺は持っていなかった。
『どうしても、戦うのか?』
「ああ。どうしても、戦わなければならないのだ。……たとえ、命を落とすことになるとしても」
その声の震 えの中に、怒りだけではない隠 しきれない恐怖心が覗 いていることに、俺は気づいた。
その瞬間、真大刀と出会ってからの四年間の記憶 が刀身 の内を駆 け巡 った。その日々が失われ行こうとしていることに、俺もまた堪 らない恐怖を覚 えた。
『ならば真大刀よ、我 が刀身 を振 るえ』
思わず発したその言葉は、自分自身にとっても思いがけないものだった。
「お前……もう戦場に駆 り出されるのは嫌 なのではなかったのか?」
真大刀もまた、思いがけないことを聞いたというような顔で俺を見る。
『このままこの郷 に在 れば、いづれこの刀身 も霧狭司国 に奪われ、戦に使われよう。いづれにせよ戦に連れ出されるならば、お前たちと共に滅 んだ方がよほど良い』
それは後から考えた言い訳 のようなものだった。本音は、ただ真大刀を死なせたくないという、それだけだった。だがその想いを素直 に本人に告げることもできず、知られることすら何故 だか恐 れて、俺はそんな風に誤魔化 した。
それでも真大刀は初めて見るような感謝の眼差 しで俺を見、礼を言ってきた。
「ありがとう。……すまない」
『礼を言われることではない。それに、お前に素直になられると気持ちが悪い』
「人が礼を尽 くしているというのに気持ちが悪いとは何だ。お前は本当にひねくれた大刀 だな」
真大刀はさすがにむっとしたように言い返してくる。いつもの調子が戻 ってきたことに内心安堵 しながら、俺はさらにからかいの言葉を続けた。
この時はそんな風に、迫 り来る郷の最期 から目を逸 らし、わざと軽口を叩 き続けていた。だが、いくら目を逸 らしたところで無かったことになどなるはずがなく、その日は間違 いなくやって来た。
俺の問いに、真大刀は
「……ああ。そのようだな」
俺が
しかもそうして滅ぼした国々をきちんと
その手はとうとう鯨鯢国にも
「……宮処を
その声は
『戦う気なのか?』
「ああ。幸運なことに武器ならば
『だが、実際に
その問いかけに、真大刀はしばし無言になった。勝ち目など無いことは今さら問わずとも最初から明らかだ。それでも戦うと、真大刀はそう言っているのだ。
「
その気持ちは理解できたが、その決意は
『どうしても、戦うのか?』
「ああ。どうしても、戦わなければならないのだ。……たとえ、命を落とすことになるとしても」
その声の
その瞬間、真大刀と出会ってからの四年間の
『ならば真大刀よ、
思わず発したその言葉は、自分自身にとっても思いがけないものだった。
「お前……もう戦場に
真大刀もまた、思いがけないことを聞いたというような顔で俺を見る。
『このままこの
それは後から考えた言い
それでも真大刀は初めて見るような感謝の
「ありがとう。……すまない」
『礼を言われることではない。それに、お前に素直になられると気持ちが悪い』
「人が礼を
真大刀はさすがにむっとしたように言い返してくる。いつもの調子が
この時はそんな風に、
郷の見張りに立っていた鍛冶 の一人が敵の襲来 を告げる。真大刀 は緊張した面持 ちで俺の刀身 を鞘 から引き抜いた。
「……何故 だか、いつもより軽い気がするな」
『我 が霊力 をこの刀身 に漲 らせているからな。……良いか、真大刀。戦ならば我の方が慣 れている。我が声に耳を傾 け、我が声の通りに動け』
戦い方なら知っている。魂 の中に刻まれた数多 の戦の記憶により、どういう風に動けば相手を斃 せるかを俺は熟知 していた。
真大刀を死なせないためには、真大刀が傷つけられるより先に相手を斃 さねばならない。――その時はただ、そんな風にしか考えられなかった。
『真大刀、左だ!』
怒号 の飛び交 う戦場となった郷を、俺と真大刀は駆 け回った。
大刀 を振るったことのない真大刀が俺の刀身 を上手く扱 えるのかと初めのうちは心配したが、真大刀はまるで俺の思考を読んでいるかのように瞬時に俺の指示に応 え、敵を薙 ぎ倒 していった。いや、実際に彼は俺の思考を読み取っていたのかも知れない。真大刀には元々、大刀に宿 る精霊と言葉を交 わすだけの霊力を有していた。その霊力が戦により研 ぎ澄 まされていたのかも知れない。
それは俺の魂 と真大刀の魂 とが渾然一体 となっているかのような感覚だった。俺が真大刀に操 られているのか、俺が真大刀を操 っているのか分からない。そのくらいに、俺たちは一体となっていた。
俺の霊力もまた、戦の中で研 ぎ澄 まされ、真大刀の手に振 るわれ、昂 ぶっていくのが分かる。
(――霊力が湧 いてくる。強くなっていくのが分かる。我は、こんなにも強くなれたのか……)
まるで酒に酔 うかのように、俺は刀身 の内で昂 ぶり漲 るその霊力にいつしか酔 いしれていた。
(真大刀の言う通り、我は本当に神になれるのかも知れない。真大刀とならば、この郷を守ることもできるかも知れない)
だが俺たちの力だけで郷 を守りきれるほど、戦況 は甘くはなかった。兵士の数はあまりにも多く、俺たちが何人かを斃 している間にも他の郷人 たちは次々と斃 れていった。気づけば郷人の姿はほとんど見えず、敵の姿ばかりが郷に溢 れていた。
やがて真大刀の顔にも徐々 に疲労 の色が浮かび始めた。
「……鉄砂比古 様!」
門の前に鉄砂比古 の姿を見つけ、真大刀が駆 け出す。鉄砂比古は何人もの兵士を相手に鉄槌 を振 るい続けていた。
兵士達の大刀 や鎧 は鉄砂比古の鉄槌に触 れただけでぐにゃりと歪 み、形を変え、使い物にならなくなる。だが神とはいえ、目も脚 も不自由な身。その上、兵士達は次から次へと現れる。鉄砂比古の身は既 に満身創痍 だった。
「真大刀、逃 げろ!この郷はもう終わりだ!お前だけでも逃げろ!」
兵士達を薙 ぎ倒しながら鉄砂比古が叫 ぶ。だが真大刀は激しく首を横に振 った。
「行けません!私もあなたと共に戦います!そんなお姿のあなたを置いていくなど……」
今にも泣き出しそうなその声に、鉄砂比古は硬 い声で告げる。
「どの道、俺ももうこの世に長くはいられん。俺の依代 はこの郷 の鍛冶 の血だ。それがここまで喪 われてしまった以上、この存在を保 っていられるのも時間の問題だろう」
「ならば、私もここで共に果 てます!」
真大刀の頬 には汗 とも涙 ともつかぬものが幾筋 も伝 っていた。鉄砂比古 は肩 で息をしながら哀願 するように声を絞 り出す。
「頼 む真大刀、逃 げてくれ。せめてお前一人だけでも。この俺を、ただの一人も守りきれなかった情 けない鎮守神 にしないでくれ」
真大刀はハッとしたように鉄砂比古を見つめた。鉄砂比古は苦痛に歪 む頬 を無理矢理に持ち上げ笑 みを作る。
「行け、真大刀。お前に幸 く有 らんことを祈 っている」
真大刀の手が、強く強く俺の柄 を握 りしめてきた。まるで、何かを堪 えるかのように。
無言のまま鉄砂比古に一礼し、真大刀は後も見ずに走り出した。悲鳴も叫びも涙も、何一つなかった。ただしっかりと握 った手の震 えだけが、真大刀の心を痛いほど俺に伝えてきていた。
「……
『
戦い方なら知っている。
真大刀を死なせないためには、真大刀が傷つけられるより先に相手を
『真大刀、左だ!』
それは俺の
俺の霊力もまた、戦の中で
(――霊力が
まるで酒に
(真大刀の言う通り、我は本当に神になれるのかも知れない。真大刀とならば、この郷を守ることもできるかも知れない)
だが俺たちの力だけで
やがて真大刀の顔にも
「……
門の前に
兵士達の
「真大刀、
兵士達を
「行けません!私もあなたと共に戦います!そんなお姿のあなたを置いていくなど……」
今にも泣き出しそうなその声に、鉄砂比古は
「どの道、俺ももうこの世に長くはいられん。俺の
「ならば、私もここで共に
真大刀の
「
真大刀はハッとしたように鉄砂比古を見つめた。鉄砂比古は苦痛に
「行け、真大刀。お前に
真大刀の手が、強く強く俺の
無言のまま鉄砂比古に一礼し、真大刀は後も見ずに走り出した。悲鳴も叫びも涙も、何一つなかった。ただしっかりと
だが、どれほど人目を
鉄砂郷の
俺たちは――いや、少なくとも俺は、せめて真大刀の命だけは守りたいと、それだけを思って必死に追っ手と戦っていた。
逃げ続けているうちにも俺の霊力と真大刀の腕はますます上がり、もはや数人の兵士に囲まれたところで、それを
だが俺はその時全く気づいていなかった。敵の血を
「……この辺 りだったな。私とお前が初めて会ったのは」
逃れ逃れてたどり着 いた深い森の中で、辺りを見渡し、一つの木の根元に疲 れたように腰を下 ろし、真大刀はつぶやいた。
その時初めて、俺はそこが自分が真大刀と初めて会った場所であることに気づいた。
いや、そこが本当にその場所だったのか、今となっては分からない。だが俺たちは確かに魚眼潟 の森にいた。
『大刀雨 零 る魚眼潟国 』――かつてそう呼ばれていたそこは、東西南を内海に囲まれた地。北は既 に霧狭司 の兵士に固められ、他の三方は水に阻 まれ、もはやこれ以上何処 へ行っても逃げ場など無い。真大刀はそれを俺が気づくよりも早くに悟 っていた。
「今でもはっきりと思い出せる。あれは私にとって初めての旅だったからな」
『唐突 に何を言い出すのだ?真大刀……』
全てを懐 かしむような、それでいて全てを諦 めたかのような静かな声音 に不吉な予感を覚 え、俺は問う。だが真大刀は俺の言葉など聞いていないかのように一方的に語り続ける。
「精霊の宿る大刀と出会ったのは初めてだったからな。顔には出さなかったが、本当は感動していたのだ。あの時お前に会えて、本当に良かった」
普段はひねくれた真大刀の滅多 にない素直な言葉に、嫌 な予感は増 す。
『何を言っているのだ、真大刀。やめろ。お前が素直になると気持ちが悪いと言ったではないか』
俺は何とか真大刀の言葉を止めたくて声無き声を発する。だが真大刀は言葉を止めない。
「私はこのような性格だからな、郷 の同じ年頃 の男たちと上手 くやっていくことができなかった。だから、お前が初めての友のようなものだった。厭味 なことも散々 言ってきたし言われもしたが、お前がいてくれて、私は幸せだったと思う。……ありがとう」
言いながら真大刀は衣 の裾 を裂 き、それで俺の刀身 を丁寧 に拭 い始めた。
『……やめろ、真大刀。何をする気だ!?』
「ここまで一緒 に来てくれたお前をこんな形で遺 していくことは、心底 すまないと思っている。だが私はもはや、耐 えられぬのだ」
『やめるのだ、真大刀!諦 めるな!我とお前の霊力をもってすれば、きっと退路 は開 ける!』
俺は、真大刀がこの逃げ場の無い状況に絶望したのだと思い、そんな言葉を紡 いだ。だが、返ってきたのは俺が思ってもみなかった答えだった。
「……そうではない。私が耐 えられぬのは逃げ続けることに、ではない。自分の手を血で染 め続けることに、だ」
その言葉に、思考が止まる。俺は何も言うことができず、ただ真大刀の言葉の先を待った。
「こうなってみてようやく、私はかつてのお前が味わってきた苦しみを真の意味で理解することができた。……私はもう、どれだけの血を浴びてきたのだろうな?私が斃 した霧狭司の兵士の中には無理矢理に戦へ駆 り出された農夫もいるだろう。その者を大切に想う家族もいるだろう。一方は命令によりやむを得 ず戦わされる身、もう一方は自分の命を守るためやむを得ず戦う身――どちらも戦うことを真に望んでなどいないのに、どちらかの血が流れ、命が喪 われる。戦とはこんなにも哀 しく、醜 いものなのだな……」
真大刀が追っ手との戦いの中で何を考えていたのか、俺はこの時初めて知った。
「他を滅ぼすためではなく、何かを守るために大刀を鍛 える……。その誇 りを胸に生きてきたつもりだった……。だが、今の私が行っているのはまるで逆の行為だ。国も、父も、鉄砂比古 様も……私が大切に想ってきたものたちは、もう何もかも失われてしまった。このまま永 らえたところで、未来などありはしない。なのに……他の誰かの命を奪ってまで守りたいほどの何かを、私は今この手に持っているのだろうか?……もはや、そんなことを考えることにすら、疲 れてしまった……」
言いながら、真大刀はその両手で俺の刀身 を引き寄せた。まるで別れの抱擁 でも交 わしているかのように両腕 で俺の刀身 を抱 え、その刃を自分の首筋 に寄せていく。
真大刀が何をしようとしているのか瞬時に悟 った俺は、声無き声で必死に叫 んだ。
『……やめろ!真大刀!我はお前を殺したくなどない!』
その叫びに真大刀は一瞬だけ動きを止め、俺を見つめた。
そこに在 ったのは、恐 いくらいに静かで、哀 しいくらいに何もかもを悟 りきった、儚 い微笑 みだった。
「血を浴びることを厭 うお前を知りながら、最期 にその刀身 を穢 す私を、許 してくれ」
その言葉を受け止めきれぬうちに、真大刀は両目を閉 じ、その首筋に刃を沈めた。
その瞬間のことで覚 えているのは、刀身 に浴びた真大刀の血潮 の熱さだけだ。何が起きているのかをまるで受け止められぬまま、俺はただその熱さを全身に感じていた。
『……嘘 、だろう?真大刀……』
しばらく呆 けた後、おそるおそる問いかけたが、返る言葉はなかった。熱いほどに感じられていた真大刀の血潮の熱さ、両手のぬくもりさえ、湯が冷めていくように徐々 に、だが確実に、失われていく。
その命の灯 が消えてしまったのだと――それも、他ならぬ俺のこの刀身 により消してしまったのだと理解した瞬間、俺は叫びだしていた。
『……真大刀!目を開けよ!』
戦いの中で魂 が一つになる感覚に酔 って、俺はいつの間にか真大刀の何もかもを分かっているような気になっていた。これまで戦と無縁 だった真大刀が、戦いの中でどれほど心に傷 を負 っていたのか、まるで気づくことができなかった。真大刀の身を守ることにばかり必死で、その心を守ることになど思い及 びもしなかった。
『このようなこと、あってはならぬ!お前までもが命を喪 うなど、あってはならぬ!』
いくら悔 いても、叫んでも、もはや何もかもが遅 かった。それでもなお、俺は声無き声で叫び続けた。叫ばずにはいられなかった。
昼も夜も忘れたように叫び続け、どれほどの時が経 ったか分からない。自分自身でも、このまま魂 が狂ってしまうかと思っていたその時――ひどく無遠慮 な声が森に響 いた。
「おい!こっちへ来いよ!例の小僧 だ。もう死んでいるみたいだぞ」
それは俺達を追ってきた霧狭司 の兵士達だった。
「今まで散々手こずらせてきやがったくせに、こんな所で自害とはな……。だがまぁ、助かったか。この小僧 、異様に強かったからな」
「ああ。これでやっと霧狭司に帰れる。じゃあ、確かにこいつが死んだって証 を将の所へ持って帰ろう」
「おっと、その前に……この大刀 はもらっておこうぜ。相当な上物だからな」
兵士達は言いながら、俺の刀身 を真大刀から引き剥 がした。そのまま、まるで物か何かを扱 うように真大刀の髪をつかみ、乱暴に地の上に引き倒 す。
『……待て。貴様ら、真大刀の身に何をする気だ?』
問うが、兵士達の耳に俺の声無き声は届 かない。
兵士の一人が仰向 けに横たわる真大刀の身の上にまたがり、無言で大刀 を抜 く。その刀身が真大刀のか細 い喉 に振り下ろされようとした瞬間、俺は魂 の底から何か恐ろしいほどに禍々 しく熱いものが湧 き上がってくるのを感じた。
『おのれ、貴様ら!郷 を滅ぼし我らを追いつめただけでは飽 き足 らず、死した真大刀の身までをも辱 めるつもりか!』
魂 の奥底からせり上がってくる、溶岩 のように熱く滾 ったそれを、俺は感情の赴 くままに解き放った。瞬間、刀身 から炎が噴 き出す。それは禍々 しいほどに熱く、激しく荒れ狂う炎の霊力だった。
戦場で長年戦火を浴び続けた大刀には火に属する火の霊力が宿りやすくなっている。俺はその負の霊力を、自らの深い怒りと絶望により呼び寄せたのだ。そしてその怒りと絶望は、同時に俺の魂 を狂わせ、荒魂 へと変えていた。
荒魂となった魂 は、常にはあり得ぬような凄 まじい霊力を発現させる。
兵士達は、悲鳴を上げる間も与えられなかった。瞬 き一つ許さぬほどの間に、彼らは骨一本残さず灰と化した。
彼らだけではない。制御を失った荒ぶる霊力は、周囲を次々に巻き込んでいく。森の木も草も、真大刀の亡骸 さえも、全てが灰となり消えていく。
そしてその炎の中、俺はふいに、自分が人の形へと変化していることに気づいた。
「……何だ、これは……。俺は……神になったと言うのか……?」
荒魂となることで急速に膨 れ上がった霊力が、俺という存在を単なる精霊から神という高次元の存在へと一気に押し上げたのだ。
「……違 うだろう、真大刀!いずれ俺を神にしてみせると言ったのは、こういうことではなかったはずだ!何もかも失って、それで神になったとしても、何の意味がある!?」
神となったことを自覚してもなお、吹き荒れる炎は、狂おしいまでの怒りと絶望は、少しも治 まることはなかった。その炎はいつしか、俺の身さえも呑 み込 もうとしていた。だが俺はそれを避 けようとはしなかった。
(……それもまあ、良いだろう。この炎で我が身も共に葬 れるのならば。……もしかしたら、真大刀や郷 の皆 のいる場所へ行けるかも知れん……)
俺は目を閉じ、その炎の波に身を委 ねようとした。だが、怒りを忘れ、終わりを覚悟 したその瞬間、変化が起こった。
「…………っ!?これは……何だ?」
俺の左頬 から胸にかけてと、両足の甲に、ふいに金の光が浮かび上がったのだ。同時にそこから炎を打ち消すように、水の霊力が噴 き出してくる。
「何故 だ……?何故、水の霊力が……」
その霊力の源を探ろうと金の光に目を凝 らし……俺は息を呑 んだ。水の霊力が噴 き出すその場所に在 ったのは、真大刀が守り文様 として俺に刻ませた、三頭の金の龍の文様だった。
『……龍を選んだのは、水の眷属 たる“龍”を守り文様とすることで、水の霊力の加護を得るためです。戦場で長年戦火を浴びてきたこの大刀には、火に属する負の霊力が息づきやすくなっておりますから』
いつかの真大刀の声が頭の中に蘇 る。俺は震 える指で、頬 に現れたその文様をなぞった。
「真大刀……、お前は、どうしてこんな……」
水の霊力が、火照 った身体 の熱を冷 ますように、俺の霊を鎮 めていく。周囲で荒れ狂っていた炎の霊力も、少しずつ静かな水の霊力へと変わり消えていく。
その水の霊力にくるまれて、俺の身は再び別の形へと変化していった。人の肌 から、銀の鱗 に覆 われた肌へと。そしてその身は長く伸 びてくねり、額には角 が生 えてくる。人の姿から、真大刀が刀身に刻んだ通りの龍の姿へ……。
だが、俺の身は龍に変わることはなかった。精霊から神へと変わったばかりの俺に、完全に龍と化すだけの霊力は無く、俺は額に角 を生やした中途半端 な蛇神 となった。そして後には鬱蒼 と繁 る森の中、そこだけぽっかり丸く開 けた黒い焼野原 だけが残されていた。
逃れ逃れてたどり
その時初めて、俺はそこが自分が真大刀と初めて会った場所であることに気づいた。
いや、そこが本当にその場所だったのか、今となっては分からない。だが俺たちは確かに
『
「今でもはっきりと思い出せる。あれは私にとって初めての旅だったからな」
『
全てを
「精霊の宿る大刀と出会ったのは初めてだったからな。顔には出さなかったが、本当は感動していたのだ。あの時お前に会えて、本当に良かった」
普段はひねくれた真大刀の
『何を言っているのだ、真大刀。やめろ。お前が素直になると気持ちが悪いと言ったではないか』
俺は何とか真大刀の言葉を止めたくて声無き声を発する。だが真大刀は言葉を止めない。
「私はこのような性格だからな、
言いながら真大刀は
『……やめろ、真大刀。何をする気だ!?』
「ここまで
『やめるのだ、真大刀!
俺は、真大刀がこの逃げ場の無い状況に絶望したのだと思い、そんな言葉を
「……そうではない。私が
その言葉に、思考が止まる。俺は何も言うことができず、ただ真大刀の言葉の先を待った。
「こうなってみてようやく、私はかつてのお前が味わってきた苦しみを真の意味で理解することができた。……私はもう、どれだけの血を浴びてきたのだろうな?私が
真大刀が追っ手との戦いの中で何を考えていたのか、俺はこの時初めて知った。
「他を滅ぼすためではなく、何かを守るために大刀を
言いながら、真大刀はその両手で俺の
真大刀が何をしようとしているのか瞬時に
『……やめろ!真大刀!我はお前を殺したくなどない!』
その叫びに真大刀は一瞬だけ動きを止め、俺を見つめた。
そこに
「血を浴びることを
その言葉を受け止めきれぬうちに、真大刀は両目を
その瞬間のことで
『……
しばらく
その命の
『……真大刀!目を開けよ!』
戦いの中で
『このようなこと、あってはならぬ!お前までもが命を
いくら
昼も夜も忘れたように叫び続け、どれほどの時が
「おい!こっちへ来いよ!例の
それは俺達を追ってきた
「今まで散々手こずらせてきやがったくせに、こんな所で自害とはな……。だがまぁ、助かったか。この
「ああ。これでやっと霧狭司に帰れる。じゃあ、確かにこいつが死んだって
「おっと、その前に……この
兵士達は言いながら、俺の
『……待て。貴様ら、真大刀の身に何をする気だ?』
問うが、兵士達の耳に俺の声無き声は
兵士の一人が
『おのれ、貴様ら!
戦場で長年戦火を浴び続けた大刀には火に属する火の霊力が宿りやすくなっている。俺はその負の霊力を、自らの深い怒りと絶望により呼び寄せたのだ。そしてその怒りと絶望は、同時に俺の
荒魂となった
兵士達は、悲鳴を上げる間も与えられなかった。
彼らだけではない。制御を失った荒ぶる霊力は、周囲を次々に巻き込んでいく。森の木も草も、真大刀の
そしてその炎の中、俺はふいに、自分が人の形へと変化していることに気づいた。
「……何だ、これは……。俺は……神になったと言うのか……?」
荒魂となることで急速に
「……
神となったことを自覚してもなお、吹き荒れる炎は、狂おしいまでの怒りと絶望は、少しも
(……それもまあ、良いだろう。この炎で我が身も共に
俺は目を閉じ、その炎の波に身を
「…………っ!?これは……何だ?」
俺の
「
その霊力の源を探ろうと金の光に目を
『……龍を選んだのは、水の
いつかの真大刀の声が頭の中に
「真大刀……、お前は、どうしてこんな……」
水の霊力が、
その水の霊力にくるまれて、俺の身は再び別の形へと変化していった。人の
だが、俺の身は龍に変わることはなかった。精霊から神へと変わったばかりの俺に、完全に龍と化すだけの霊力は無く、俺は額に