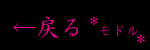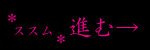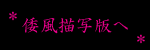| 第十二章 嵐の果て |
「真大刀……」
無理矢理引きずり出されたその記憶は、時を経 ても尚 褪 せることのない悲しみと怒りに彩 られていた。
なぜ鉄砂郷 や真大刀 が滅ぼされねばならなかったのか、あの時どうしていれば全てを喪 わずに済 んだのか、未だに答えは見つけられない。この胸に渦巻 く憎しみを、怒りを、後悔 を、絶望を、どこへ向ければ良いのか、そのやり場も分からない。行き場の無い感情の波は、ただ混沌 として身の内を荒れ狂う。
「思い出したであろう?人間 というものがいかに愚 かなものであるかを……。見よ、汝の大切なものたちを奪った霧狭司 の国民たちは、今も自分のことばかりを考え、互いに醜く争っておるぞ」
優しく諭 してでもいるかのような女神の声に、俺は促 されるまま、視線を下へ向けた。
屋根の破れた宮殿の内部では、人々が俺たちの方を指差しながら、何事か言い争っている。その中には溢 れてくる水を避 けようと、一人だけ厨子 の上に上がり、他の者を上がらせまいと足蹴 にしている者までいた。
「……何と愚かな。これが、霧狭司国 の宮殿……。真大刀を、鉄砂の郷を滅ぼした、霧狭司国の……」
ざわりと鱗 が震えた。魂 がふつふつと滾 っていく。心が荒ぶっていくのが分かる。
「昔も、今も変わらぬ。他人 の命を命とも思わぬ輩 ばかりだ。このような国など、滅びてしまえばいい」
その昏 い呟きに、泊瀬 と花夜 がはっとしたように息を呑 む気配が背中越しに伝わってくる。
「あんたまで、どうしたんだ!?ミヅハ様を説得するんじゃなかったのか!?」
「ヤト様!水神様のお怒りに引きずられてはいけません!ヤト様まで荒魂 となってしまっては駄目 です!」
花夜の声に、俺はわずかに正気を取り戻す。だが既 に湧いてしまった怒りは、そう容易 く治 まってはくれない。それは押し寄せる波のように、再び俺の意識を攫 っていこうとする。
「……駄目だ。この怒りは自らの力では抑 えきれぬ。このままでは俺は荒魂 と化してしまう……!」
今にも溢 れ出しそうな怒りや憎しみを必死に堪 えながら、俺は震える声を振り絞 り花夜に告げる。
「花夜……逃げよ!俺が正気でいるうちに、鳥羽 の翼を使って逃げるのだ!」
 だが
だが花夜 はその言葉を即座 に拒否 した。
「行けません!そんな風に苦しんでいらっしゃるあなたを置いて逃げるなど、できるはずがありません!私は、あなたの巫女なのですから……!」
「馬鹿 なことを言うな!荒魂 と化してしまえば、俺にもお前のことが分からなくなってしまうかも知れん。巫女だからと言って傷つけられないという保証など無いのだぞ!」
花夜を一刻も早く逃がしたいという一心で、思わず語気 が荒くなる。だが花夜は怯 むことなく静かに言葉を返してきた。
「馬鹿なことではありません。ヤト様の魂 を鎮 めるのは巫女である私の役目。私はあなたの巫女で、あなたは私の神様なのですもの。これは他の誰にも譲 ることのできない私の誇 りなのです。だから……」
言いながら、花夜は俺の背にうつ伏 せるように身を倒 し、その両腕 で俺の躯 を抱 きしめた。ほわりとしたぬくもりが、背中から伝 わってくる。
「私を遠ざけないでください。あなたのその苦しみを、私にも負 わせてください。独 りでは抱えきれないその感情を、私にも分かち合わせてください」
言葉と同時に優しい霊力が、触 れ合った花夜の身体 を通して俺の中に流れ込んでくる。
五鈴鏡 の中にわずかに残った鳥羽 の霊力と、花夜自身の霊力だ。それがまるで母が我が子を優しい手で撫 でるかのように、荒ぶる魂 を宥 めていく。
「……何という、深い悲しみと怒 りでしょう……。こんな感情を、あなたはずっと胸 の奥底に秘めていらっしゃったのですね……」
俺の躯 を抱きしめながら、花夜は悲しむように、あるいは愛 おしむかのように囁 きかける。
「駄目 だ、花夜!人間 の身で神の怒りに触れるなど、正気 の沙汰 ではない!下手 をすればお前まで魂 を狂わせてしまうぞ!」
花夜がその霊力を介 して俺の魂 の中の荒ぶる感情に“触れて”いることを悟 り、俺は血 の気 が引く思いで叫 んだ。
「いいえ。大丈夫 です。荒魂 になったりなどいたしません。私も、あなたも……」
魂 に渦巻 く怒りや憎しみがどの程度 のものなのか、自分自身が一番良く分かっている。制御 もできぬほどのそれを、霊力を介して確かに味わっているはずなのに、花夜はその怒りに引きずられることもなく、不思議 なほど穏 やかに言葉を続ける。
「……ヤト様。私、前に申 し上 げたことがありますよね。どんなものにでも存在 する意味があるのだと。“怒り”にもきっと、存在する理由はあります。怒りは、魂 を奮 わせる力です。心を普段の何倍にも強くし、困難に立ち向かうための活力を与えてくれる魂 の働きです。ひどい出来事 に遭 って、怒りを覚 えること自体は、きっと悪いことなんかじゃないんです。当たり前のことなんです。大切なのはきっと、その怒りをどう使うか なんです」
「怒りをどう使うか……だと?怒りに破壊 以外の使い道などあるものか。俺の大切なものたちを奪った霧狭司 の人間どもを滅 ぼさぬ限 り、俺の心は晴 れぬのだ……!」
「いいえ。それでは憎しみの連鎖 を生むだけです。あなたがなさりたいのは、本当にそんなことなのですか?あなたの大切なものを奪 った者たちと同じように、誰 かの大切なものを奪 い、あなたが憎んでいらっしゃるものと同じ存在になり果 てることが、本当にあなたのなさりたいことなのですか!?」
俺の魂 に触れる花夜の霊力が、一瞬だけ平手打ちでもするかのように激 しくなった。
その時、俺は雨の吹き荒 ぶ中空に刹那 の幻影を見た。
それは荒魂 と化し、全身に禍々 しい炎をまとわせ猛 り狂う俺自身の姿だった。その瞳 に宿るものは、人を人とも思わず、ただ自らの心を満 たすためだけに破壊を悦 ぶ、おぞましい光だ。まるで俺が嫌悪 する霧狭司 の姿そのもののような、変わり果てた俺の姿……。
「ねぇ、ヤト様……。そのお力を、破壊のために使う必要なんてありませんよ。もっと違 うことに使って良 いんですよ。そのお力があれば、ただ一時の憂 さを晴らすことなどよりもっと素晴らしいことができるはずです。そのお力があれば、きっと何かが変えられます。だから……そのお力を、もっと違うことに使いましょう。他人 を傷つけて憎しみの連鎖 を生み出すためではなく、ヤト様も私も、皆が幸せになれることに……」
俺の中で熱く滾 っていた荒ぶる霊力が、花夜の注 ぎ込 む優しい霊力と絡 み合い、溶 け合い、あたたかな奔流 となって躯 の中を駆 け巡 る。それは決して不快 なものではなく、むしろ炉 の中で熔 かされ生まれ変わっていったあの時のような心地良 さを伴 うものだった。
同時に、俺の躯 が銀の灯 を点 したように輝きだす。目も眩 むほどの光の中、俺の躯 はゆっくりと形を変えていった。手足が伸 び、鬣 が生 え、角 の形も変わっていく。
「な、何だ!?何が起こっているんだ!?これは……この姿は……まさか、龍!?」
泊瀬 の慌 てたような声を背に聞きながら、俺は自分の身に何が起きたかをすっかり理解していた。
俺の躯 は角 の生えた大蛇 から、銀の鱗 を持つ龍へとすっかり変貌 を遂 げていた。破壊へ向かおうとしていた俺の荒ぶる霊力を、花夜が優しい霊力に変換し、その霊力により俺は蛇神 よりさらに神格の高い龍神へと進化したのだ。
直後、俺の躯 の周りで白い光の羽根が一斉 に舞 い散 った。残り少なかった鳥羽 の霊力が尽 きた瞬間だった。
「母さま……。ありがとう」
花夜のか細 く震 える声が聞こえる。
「花夜……すまない。俺が魂 を荒ぶらせたばかりに、鳥羽の霊力まで……」
「……いいえ。遅 かれ早かれ、こうなっていたのですもの……。ヤト様のせいではありません」
怒 れる神の魂 に触れた影響か、花夜の声にはさすがに疲労 がにじみ、弱々しくなっていた。
「大丈夫 か?花夜姫……」
「ええ。少し、疲 れただけです。それよりも泊瀬王子 、今度はあなたの番です。水波女神を元に戻せるのは、きっとあなただけ……。難しいことを考える必要はありません。ただ、あなたの想いの全てを素直にぶつければ良いのです。私がヤト様に対してそうしたように……」
「……そうだな。分かった」
その声には先ほどまでの取り乱 した様子はまるで無く、ただ深い決意が感じられた。
泊瀬はそれまで俺の身にしがみつくようにうつ伏 せていた身を起こし、女神へ向け声を張り上げる。
「ミヅハ様!どうか御心を鎮 めて下さい!これ以上宮処 を壊さないで下さい!」
女神はゆっくりと首をめぐらせて泊瀬を見た。
「泊瀬よ、何故宮処を庇 う?王子 としての責任感からか?宮処に住むのがいかに身勝手で情の無い者達か、お前も知っていように。お前やお前の母が何度命を狙われてきたか、何度悲しい目に遭 わされてきたか、我は知っておるぞ」
その言葉に、泊瀬はその出来事を思い出すかのようにしばし無言になった。だが彼はすぐに女神の言葉を否定 する。
「……違 います。俺は王子 の責任だとか、そんな立派な理由であなたを止めたいわけではありません。この宮処 に住む人間全てを許せるような器の大きい人間でもありません。ただ俺は、あなたにもうこれ以上、辛 い思いをして欲しくないだけなんです」
「何を言うか。辛い思いなど、疾 うにしている。こんな思いをもうせぬために、我はこの国を清めるのだ」
「違う!そんなことをしても辛 い出来事はなくならない!正気に戻ったあなたが、今までより一層、罪の意識を感じて辛くなるだけだ!……たとえどんな不幸が襲 ってきたって、変わらない人間は変わらない。前にあなたがおっしゃっていたように、罰 を与えても改心しない罪人がいるのと同じことだ。自業自得 の災 いだって、他人 のせいにして嘆 くような人間だっているんだ。人間 の心の愚 かさはきっと、多かれ少なかれ誰 もが皆 、持っているもの。一人一人が何とかそれを克服 して生きていくしかないんだ。そしてその乗り越え方はきっと、人によって全く違 うんだ。だから、こんなことしても意味なんて無い!俺たちはただ、地道に一人一人の心を変えられる努力をして、そうやって世間を改めていくしかないんだ!」
その叫びに、女神の瞳 が心なしか哀しげに潤 んだように見えた。
「お前のように熱い志 を持ち、地道に人々を変えようとした者は今までにもいた。だがいつの時代も、そうやって世間を変えようと足掻 くのは、ほんの一握 りの人間ばかり。他の多くの者達は己や国の在 り方を変えることなど露 ほども考えておらぬ。そして一握りの人間の言葉や努力など、他の多くの愚 かな者達により容易 く踏 みにじられ、握 りつぶされてしまう。我はもう何度も見てきた。たとえ何年、何百の歳月を待ったとしても、世間は変わったりなどせぬ。もう、信じることにも希望を持つことにも飽 いた」
言って、女神は大きく顎 を開 いた。その喉 の奥から、背筋が凍 りつくような咆哮 が響 き渡 る。そしてその声に呼応 するかのように、宮処 の端 、土色に濁 った霊河 で、幾つもの水竜巻 が立ち上 った。それはまるで鎌首 を持ち上げる幾匹 もの大蛇 のようだった。
「霊河 よ、我が従神 たる霊河比売 よ、荒れ狂え。荒河 となり宮処 を破壊 せよ」
「やめてくれ!ミヅハ様!」
泊瀬は四 つ這 いになり、少しでも女神の近くへ行こうと必死に俺の頭の方へと上 っていく。
「頼 む!この国を壊さないでくれ!こんな国でも、こんな世界でも、俺は愛しているんだ!」
「何故だ?何故、愛せる?今までに何度殺されかけたか分からぬと言うに」
「あなたがいるからだ!あなたが教えてくれたんだ!この世にも、生きていて良かったと思えることがあると。あなたが俺を愛してくれたから、俺もこの世界を愛することができたんだ!そのあなたが、この国を壊してしまわないでくれ!」
「壊すのではない。一度洗 い浄 めるのだ。『たとえどんな不幸が襲 おうと変わらぬ人間は変わらぬ』とお前は言ったが、それでも大きな災厄 には国を動かし、歴史を変えるだけの力がある。我はそれを知っておる」
「ミヅハ様……」
泊瀬の唇 から絶望の呻 きが漏 れる。彼はしばらく無言で打ちひしがれたように俺の躯 に突 っ伏 していたが、やがて覚悟 を決めたように俺の首の上に立ち上がった。
「泊瀬王子 !そこで立ち上がっては危険 です!」
花夜の制止の声にも構 わず、泊瀬は静かに女神に話しかける。
「――『喪 って初めて気づくような重大なものを失くして初めて、人間は目覚め、心を改める』。あなたはそうおっしゃいましたね。あなたは人間ではないし、俺があなたにとってそれほど重大なものなのかは分かりません。でも、この身があなたをその怒りや憎しみから解 き放 つための贄 となれるなら、本望 です」
「泊瀬王子 、何を……。まさか……」
花夜が気づき、制止しようとする。だが極度 の疲労 で力を失った身体 は、泊瀬に近づくため俺の身の上を這 いずることもできない。
「ミヅハ様、今の俺があるのはあなたのおかげだ。宮中という狭 い世間しか知らなかった俺に、毎夜いろいろなことを教えて下さった。悲しいことが起こると、一緒に泣いて慰 めて下さった。俺の人生は、あなたとの思い出でいっぱいだ。あなたに辛 い思いをさせずに済 むのなら、そしてあなたの身の一部となって終われるのなら、悔 いはない。だから……俺の身一つを贖物 として、この国の全ての罪を赦 してくれ」
 そう言うと
そう言うと泊瀬 は静かに数歩下がった。そして気合 を漲 らせるかのような、あるいは恐怖や迷いを無理矢理打ち消そうとでもいうかのような雄叫 びとともに、俺の躯 の上を一気に背から頭まで駆 け抜 ける。
「いけません……っ、泊瀬王子 ……!」
花夜 が悲鳴じみた声で名を呼ぶ。
だが、泊瀬の身は既 に宙を跳 んでいた。俺の額 を蹴 り、走ってきた勢いそのままに、女神の身を目がけ跳躍 する。そのまだ大人になりきれぬ小さな身体 はゆるやかな放物線を描 き、さらなる嵐を呼ぶため大きく開 かれた女神の顎 の中へ真 っ直 ぐに飛び込んでいった。
「泊瀬王子 !」
花夜の悲鳴とともに、派手 な水音 が響いた。水で構成された女神の透 き通 った躯 に、泊瀬の身が沈んでいくのが見える。その口から空気の泡 がいくつも吐 き出され、その顔が苦悶 に歪 んでいくのが見える。
「はつ……せ……」
女神の碧 い瞳 が、呆然 としたように大きく見開 かれる。その口から、再び声が迸 る。だがそれは嵐を呼ぶための咆哮 ではなく、天地を引き裂 くかのように狂おしく、悲痛な叫びだった。
女神の躯 を満たす水が、沸騰 するかのように激しく泡立ち、震 える。静かな波模様 のように整然と並 んでいた鱗 も歪 に逆立 ち、その躯 自体も、まるで見えざる手で粘土 をこねくり回してでもいるかのようにぐねぐねと歪 み、形を失っていく。
「泊瀬 ……駄目 だ。死んではならぬ!我は、お前に命を捧 げてもらいたいわけではない!我が……妾 が欲しいのは……!」
その時、幾百もの稲妻が一斉 に天に閃 いた。天地の全てが青白く染め上げられ、何も見えなくなる。地の果てまでをも震 わせるような轟音 に、他の何も聞こえなくなる。
やがて眩 しさに眩 んだ眼 がやっと慣れてきた時、そこには既 に水の躯 を持つ龍の姿はなかった。激しい風雨もいつの間 にか止 み、黒雲も少しずつ薄らいでいく。そして水の龍が浮かんでいたはずの場所には一柱 の女神の姿があった。
「泊瀬 、泊瀬……何とばかな子だ……。妾 を救うために命を捧げるなど……。それで妾がどれほど哀 しむか、お前には分かっておらぬのか……?」
ずぶ濡 れの泊瀬の身を愛 しげに抱きしめ、はらはらと涙 を零 しているのは、銀の髪 に碧 い瞳 の女神――水波女神 。だがその姿は以前に見た幼女の姿ではなかった。
「いや……ばかなことをしたわけではないな。お前は妾 に思い知らせようとしたのだろう?人間 の心を改めさせるために大切なものを奪う――それがどれほど人間 の情や命を無視した、一方的で酷 い理屈なのかということを……。後になって目を覚 ましたところで、喪 ったものはもう取り戻せはしない。そうして喪われてしまうものが、どれほど妾 にとって、そしてこの世界にとって、必要で、貴重で、かけがえのないものか知れないと言うのに……」
「……水波女神 ……?」
花夜がおそるおそる呼びかけると、女神は涙に濡 れた目をこちらへ向け、儚 げに微笑 んだ。
「もう大丈夫 だ。妾 の魂 は和魂 へと戻った。泊瀬のおかげでな」
泊瀬の顔を覗 き込 み白い指で優しく頬 を撫 でる女神の姿は、すっかり大人 の女性のものへと変わっていた。一度荒魂 と化したことにより、長年の封印で失われていた霊力が戻り、大人の姿を取り戻したのだ。
「泊瀬王子 は……!?」
「大丈夫。気を失っているだけだ。妾 が元に戻るのがあと一歩でも遅 れていれば危 なかったがな……」
言って、女神は泊瀬の額に濡 れて貼 りつく前髪をそっと掻 きやる。
「水を通して、泊瀬の心が妾 に伝 わってきた。言葉を拒 む妾の中に、文字通り無理矢理飛び込んで、全身で想いをぶつけてきてくれた。今まであれほど辛 き日々を送ってきたというのに、この子の心には愛が溢 れている。妾 を、そしてこの世界を愛してくれている」
女神は涙 を拭 い、強い決意を秘めた眼差 しで地を見下ろした。
「お前がそれほどに愛し、祈 がうのであれば、妾 も赦 そう。この世界を。お前が妾とこの世界を愛してくれているように、妾 も泊瀬 の生きるこの時代を愛している。怒 りを覚 えるものも多く、全てを赦 せるわけではないが、それでもせめて、愛せるものたちだけでも愛して生きていこう。愛するものがそこに在 ってくれるというだけで、醜 く穢 れた世界でも美しく見えることがある。そうやって、少しずつでも、この世界を愛せるようになっていけば良いのだな。お前のように……」
雲間 から、金色 の布を垂 らしたように光が差し込んでくる。空を覆 っていた雲も、まるで澱 んでいた水が洗い流されていくかのように風に吹き流されていく。風雨の止 んだ地上を見下ろすと、そこには嵐の名残 りの水溜 りが、鏡のように静かに空の色彩 を映していた。
無理矢理引きずり出されたその記憶は、時を
なぜ
「思い出したであろう?
優しく
屋根の破れた宮殿の内部では、人々が俺たちの方を指差しながら、何事か言い争っている。その中には
「……何と愚かな。これが、
ざわりと
「昔も、今も変わらぬ。
その
「あんたまで、どうしたんだ!?ミヅハ様を説得するんじゃなかったのか!?」
「ヤト様!水神様のお怒りに引きずられてはいけません!ヤト様まで
花夜の声に、俺はわずかに正気を取り戻す。だが
「……駄目だ。この怒りは自らの力では
今にも
「花夜……逃げよ!俺が正気でいるうちに、
「行けません!そんな風に苦しんでいらっしゃるあなたを置いて逃げるなど、できるはずがありません!私は、あなたの巫女なのですから……!」
「
花夜を一刻も早く逃がしたいという一心で、思わず
「馬鹿なことではありません。ヤト様の
言いながら、花夜は俺の背にうつ
「私を遠ざけないでください。あなたのその苦しみを、私にも
言葉と同時に優しい霊力が、
「……何という、深い悲しみと
俺の
「
花夜がその霊力を
「いいえ。
「……ヤト様。私、前に
「怒りをどう使うか……だと?怒りに
「いいえ。それでは憎しみの
俺の
その時、俺は雨の吹き
それは
「ねぇ、ヤト様……。そのお力を、破壊のために使う必要なんてありませんよ。もっと
俺の中で熱く
同時に、俺の
「な、何だ!?何が起こっているんだ!?これは……この姿は……まさか、龍!?」
俺の
直後、俺の
「母さま……。ありがとう」
花夜のか
「花夜……すまない。俺が
「……いいえ。
「
「ええ。少し、
「……そうだな。分かった」
その声には先ほどまでの取り
泊瀬はそれまで俺の身にしがみつくようにうつ
「ミヅハ様!どうか御心を
女神はゆっくりと首をめぐらせて泊瀬を見た。
「泊瀬よ、何故宮処を
その言葉に、泊瀬はその出来事を思い出すかのようにしばし無言になった。だが彼はすぐに女神の言葉を
「……
「何を言うか。辛い思いなど、
「違う!そんなことをしても
その叫びに、女神の
「お前のように熱い
言って、女神は大きく
「
「やめてくれ!ミヅハ様!」
泊瀬は
「
「何故だ?何故、愛せる?今までに何度殺されかけたか分からぬと言うに」
「あなたがいるからだ!あなたが教えてくれたんだ!この世にも、生きていて良かったと思えることがあると。あなたが俺を愛してくれたから、俺もこの世界を愛することができたんだ!そのあなたが、この国を壊してしまわないでくれ!」
「壊すのではない。一度
「ミヅハ様……」
泊瀬の
「
花夜の制止の声にも
「――『
「
花夜が気づき、制止しようとする。だが
「ミヅハ様、今の俺があるのはあなたのおかげだ。宮中という
「いけません……っ、
だが、泊瀬の身は
「
花夜の悲鳴とともに、
「はつ……せ……」
女神の
女神の
「
その時、幾百もの稲妻が
やがて
「
ずぶ
「いや……ばかなことをしたわけではないな。お前は
「……
花夜がおそるおそる呼びかけると、女神は涙に
「もう
泊瀬の顔を
「
「大丈夫。気を失っているだけだ。
言って、女神は泊瀬の額に
「水を通して、泊瀬の心が
女神は
「お前がそれほどに愛し、