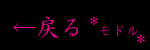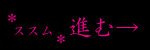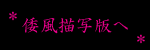| 第十一章 追憶に沈む大刀 |
だが、俺のような古びた大刀を
「何だ?嫌に無口なのだな。今さらになって
『何を言うか。我は恐がってなどおらぬ。ただお前のような
言い返そうとしたが、その声なき声は最後まで続けられることはなかった。
「……どうした?私が何かおかしな
『……いいや。お前……そのような顔をしていたのだな』
「……顔?……何だ、
真大刀は俺の言葉を勝手に
「確かに顔や
そう言う真大刀の二の
「こらこら。まだ育ち盛りだというのに腕の力ばかりを無理矢理
後から入ってきた鉄砂比古が困ったような顔でたしなめる。
「鉄砂比古様!」
真大刀が目を輝かせる。鉄砂比古は俺の方に目を向け、安心させるように
「心配は
そう言うと、鉄砂比古は次の瞬間にはもう
「では、始めようか」
その瞬間、鍛冶場の空気がぴりっと張り
それは俺にとって、まさしく生まれ変わりと呼ぶにふさわしいものだった。
炎の中で熔 かされ、元あった形を失 くし、鉄槌 により打ち叩 かれる。それは何日、何ヶ月にも及 んだ。炉 に入れられ熱されては、何度も何度も打ち延 ばされる。
だがそれは苦痛を伴 うものではなく、むしろ全身をもみほぐされているかのように心地 良いものだった。
刀身 の内に溜 まっていた禍々 しい怨 みの念が次々と叩き出され、魂 が浄 められていくのが分かる。
そのひたすら鍛錬 される日々の中、俺がはっきりと意識を保 っていられたわけではない。それは湯に浸 かりのぼせる間際 のような、あるいは目覚 めながらも半分夢の中に浸 っているかのような、そんな日々だった。
そんな夢現 の日々の中でも、俺は真大刀の鍛冶 としての力量を確かに感じ、舌 を巻いていた。
凄 まじい熱気の中、額 に玉の汗を浮かべ、火花を散らしながら懸命 に槌 を振 るい続ける真大刀の姿は、まるで普通の人間には見えなかった。人間というよりも、精霊 か神のようなものにでも憑 かれ、それに操 られるまま槌を振るっているかのように見えた。
おそらく彼には自分の手にある槌 と、目の前にある金属の塊 しか見えていない。そんな目をしていた。
真大刀が奏 でる、まるで唄 うような槌 の響 きにうとうとしながら、俺はその寝入 り端 のような朧 げな意識の中で、そんな真大刀の姿をただぼんやりと眺 め続けていた。
炎の中で
だがそれは苦痛を
そのひたすら
そんな
おそらく彼には自分の手にある
真大刀が
それからしばらくして、刀装 なども一通り全てが終わった時、俺は自分の姿が以前より大分 派手 になっていることに気づいた。
「う〜ん……精霊の宿る大刀なのだからそれなりの装飾 を、とは確かに言ったが、これは少し派手過ぎじゃないか?」
鉄砂比古が困ったように鼻の頭を掻 いている横で、真大刀は俺をその手に高く掲 げ持ち、惚 れ惚 れと見入 っていた。
「何を仰 るんですか、鉄砂比古様。こんなものは派手のうちに入りませんよ。地色は黒ですし、そこにごく控 えめに金と紅琉璃 を散らしただけですよ」
「いや、地色の問題ではなく、装飾が少々きらびやか過ぎないかということなんだが……。おまけに刀身には金象嵌 の龍、柄頭 の装飾は“玉を食 む双龍 ”……龍が全部で三頭とはね……」
鉄砂比古の言う通り、俺の刀身には金象嵌 でそれまでは無かった龍の姿が描 かれていた。そして柄頭の装飾には二頭の龍が玉を食 んでいる意匠 の透彫 が施されている。
「誤解をなさらないでください。何も私は自分が龍好きだからといって意匠 を決めたわけではございません。龍を選んだのは、水の眷属 たる“龍”を守り文様 とすることで、水の霊力の加護を得るためです。戦場で長年戦火を浴びてきたこの大刀には、火に属する負の霊力が息づきやすくなっておりますから」
踏鞴 の“風”によって起こした“火”で製錬される鋼 を素材とする大刀には、そもそも風と火の霊力が宿りやすい。大刀姿の俺が花夜 との魂振 で風や火を起こすことができるのもそれゆえだ。
真大刀はその火の霊力が再び負の霊力となって禍 をもたらすことを恐れ、それを相殺 するために水の眷属 たる龍を守り文様として描いたのだと言い張った。とは言え、そこに彼の趣味 が微塵 も反映 されていなかったとは到底 思えなかったが。
「……まぁ、それは良いとして。これからこの精霊 をどうするつもりだい?精霊の宿った大刀は使い手を自ら選ぶものだが、こんな豪華 な刀装では並 の兵士にはやれないぞ?」
『我は当分、主 など要 らぬ。戦場に連れ出されるのはもう御免 だからな。しばらくは身を休めさせてもらいたい』
「ならば、鍛冶神たる鉄砂比古様に捧 げられたご神宝 ということにして、この郷にいてもらえば良いではありませんか」
「う〜ん……俺は鍛冶場 と鍛冶の道具さえあればいいから、宝なんて要 らないんだが。……まぁ、良いか。その精霊 の意に沿 わない相手を主にして、また魂が歪 んでしまっても困るし……」
こうして俺は、鉄砂郷 に棲むこととなった。鍛冶神に捧げられた宝刀 とは言え、鉄砂比古は社 も持たず鍛冶場に祀 られているような神だったため、俺もまた鍛冶場を棲家 とすることになった。
それゆえ、当然のごとく毎日のように真大刀とは顔を合わせることになった。また、郷の中でも大刀に宿る精霊の声を聴 く霊力を持つ人間など真大刀くらいしかいなかったため、彼とは自然と友人のような関係になっていった。
真大刀の尊大な態度や他人をからかうような口振りは相変わらずだったが、それさえも慣れてしまえば気にはならなかった。何より、それまで誰 かと言葉を交 わし心を通 わすことなどなかった俺にとって、それはあまりにも新鮮 で、ささいな言い合いすら楽しく感じるくらいだったのだ。
鉄砂郷 での暮らしは、俺にとって生まれて初めての心安らげる日々――生まれて初めて幸せというものを知った日々だった。だがその平穏 は、わずか四年で失われることになる。
「う〜ん……精霊の宿る大刀なのだからそれなりの
鉄砂比古が困ったように鼻の頭を
「何を
「いや、地色の問題ではなく、装飾が少々きらびやか過ぎないかということなんだが……。おまけに刀身には
鉄砂比古の言う通り、俺の刀身には
「誤解をなさらないでください。何も私は自分が龍好きだからといって
真大刀はその火の霊力が再び負の霊力となって
「……まぁ、それは良いとして。これからこの
『我は当分、
「ならば、鍛冶神たる鉄砂比古様に
「う〜ん……俺は
こうして俺は、
それゆえ、当然のごとく毎日のように真大刀とは顔を合わせることになった。また、郷の中でも大刀に宿る精霊の声を
真大刀の尊大な態度や他人をからかうような口振りは相変わらずだったが、それさえも慣れてしまえば気にはならなかった。何より、それまで