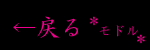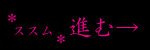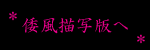狭い穴を何とかくぐると、
途端に天井が高くなった。
その
石室は四方の壁と天井をびっしりと
細かな文様で
埋め
尽くされていた。そして
松明で照らした先、部屋の中央にはなぜか小さな井戸が一つあった。
泊瀬は立ち止まり、目を閉じた。耳を
澄まし、肌で
微かな風を感じ、鼻をひくひくと小さく動かす。五感を
研ぎ澄ませて何かを感じ取ろうとしているようだった。
「……この感じ、
覚えがある。たぶん、ここだ。俺がいつも夢の中であの
方に会っていたのは」
小さくつぶやくと、
泊瀬は井戸に
駆け寄った。
「ミヅハ様!ミヅハ様、いらっしゃいますか!?俺です!
泊瀬です!」
その呼び声は石室中に
響き渡る。直後、井戸の底からぽたり、と水の
滴る音が聞こえた。
「……はつ、せ……?」
一つ、また一つと響く
水音に
混じり、夢を見ているかのようなあやふやな声が聞こえる。それと同時に井戸の底から少しずつ、ほのかな光が
漏れ始めた。
「そうです!俺です、ミヅハ様!あなたに会いにここまで来たんです!」
「……
泊瀬。本当に泊瀬なのだな」
初めあやふやだった声は
次第にはっきりとしていき、水音も光も
激しさを
増していった。やがて、井戸から光の
塊が飛び出してきた。それは石室の暗さに慣れた目には
眩し過ぎるほどの、青みを
帯びた銀色の光だった。
「ミヅハ様!」
泊瀬が
歓喜の声を上げる。
海石は
畏れ
敬うように深々と頭を下げ、
花夜は驚きに目を見張った。
「あの
方が……
水波女神……?」
光の中から現れた女神は水を
統べる姫神にふさわしく、水の持つありとあらゆる美しさを一つに
凝縮したかのような姿をしていた。
長い
髪は日の光を
浴びて流れる清水を思わせるなめらかな銀の色、瞳は透き通った湖の深い深い水の底を思わせる碧色。身にまとう
衣は水を織ったかのように
透き通る
薄物と、
泡のような
淡い銀の
模様を散りばめた
水浅葱の一枚布を組み合わせたもので、
縫い目も
裁ち切った
跡も無く、ただその身に巻きつけているだけだというのに、この上なく優美な形で女神の身を
飾っていた。
肩の辺りには
領巾の
代わりなのか、光を受けて虹色にきらめく水の
珠がいくつも連なり、女神が身動きするたびにしゃらしゃらと耳に心地良い音を
奏でていた。
だが、花夜が
驚いたのは女神の美しさにではなかった。
「泊瀬、
妾に会いにこのような場所まで来てしまったのだな」
憂いに
眉を
曇らせるその表情は
大人の女性のようだったが、その声は、姿は、まるで
違っていた。
澄んだ声は想像していたよりもずっと高く愛らしく、背の高さはまだ大人になりきれていない
泊瀬のそれよりもさらに低い。その姿は人間で言えば六、七才ほどの幼い女児のように見えた。
「ミヅハ様!俺は、あなたをお救いするためにここまで来たんです。
一緒にここを出ましょう。もうあなたは、こんな暗く
寂しい場所で孤独に
耐えていなくても
良いんです!」
泊瀬は幼い姫神に
恭しく手を差し
伸べ、熱く語った。だが
水波女神は首を横に振る。
「いいや、
妾はここを出ることはできぬ」
「なぜですか!?八乙女の結界は
既に破られた!あなたはもう自由なんだ!」
「……そうではないのだ」
水波女神は目を伏せ、
哀しげに
吐息した。
「水波女神様、
射魔海石です。
畏れながらお
尋ね
致します。あなた様は何故ここをお出になることができないのですか?」
海石が
恐る
恐る口を
開く。女神は海石に視線を向け、軽く目を
見開いた。
「
射魔海石……。かつて大宮に
仕えていた姫だな。覚えている。……すまなかったな。
妾はお前の友人を救ってやることができなかった」
その言葉に
海石も目を見開く。
「ご存知だったのですか。私と……
夏磯姫のことを」
「ああ。八乙女だった者の顔は皆知っている。それに、水辺で起きた物事は全て妾の目に入る。……霧狭司は惜しい巫女を亡くした」
遠くを見るような目でそう語った後、女神は表情を切り替え海石に向き直った。
「射魔海石、お前の問いに答えよう。妾がここを出られぬのは、八乙女に封じられているからではない」
その言葉に、
泊瀬は信じられないという表情で首を振る。
「何をおっしゃっているのですか、ミヅハ様。あなたは現に八乙女の結界の中にいらっしゃったではありませんか」
「そうではない。八乙女の結界など、妾にとっては何の障害にもならぬ。考えてもみよ、八乙女に
祈道を授けたのは妾なのだぞ。それに、そもそもいかなる霊力をもってしても、
人間の身で水を
統べる神たる妾を封じることなどできぬ。……妾がここを出られぬ理由はな……妾が、自分で自分を
戒めているからだ。決してここを出ぬように、とな」
その答えに、皆が息を
呑む。
「……何故、ですか?」
その問いに、女神はすぐには答えなかった。何かを深く憂えるような表情でしばし沈黙した後、女神は逆に俺たちに問いかけてきた。
「皆の者、この
宮処の東を流れる
霊河が、かつて何と呼ばれていたかを知っているか?」
花夜は戸惑うような顔で泊瀬を見、泊瀬は分からない、という顔で首を横に振る。その問いに答えを返すことができたのは海石だけだった。
「確か『
荒河』と呼ばれていたと、大宮にある何かの文書で読んだことがあります」
「そうだ。かつて
彼の河は毎年
増水を起こして荒れ狂った。ゆえに『荒河』と呼ばれ恐れられていた。公的には伏せられているが……実はそれは、妾のせいだったのだ」

その告白に皆が言葉を失う中、女神は沈痛な表情で先を続けた。
「神というものには、必ず二つの顔が存在する。人々に幸福と恵みを与える『
和魂』と、荒れ狂い人々に害をなす『
荒魂』だ。この二つの魂は、表裏一体のもの。平素は穏やかに
和いだ神の魂も、きっかけ
次第で激しく荒ぶる――
人間の心が怒りを得て荒れ狂うのと同じに、な。それを止めることは妾自身にもできぬ。そして一度
荒魂となれば、妾は我を失い、その荒ぶる霊力により嵐を呼び、辺りの河という河を荒れ狂わせ、人々に害をなすのだ。国王や八乙女は、それでも妾を鎮守神として留め置こうとする。だが妾は、妾の愛する国民の命を、自分の手で奪うことに耐えられなかった」
女神の瞳から一滴、涙がこぼれて頬をつたう。海石は呆然と、まるで独り言のように問いを口にする。
「『大いなる災い』……。まさか、古き文書に記されていたのはこのことだったのですか?」
「魂を荒ぶらせぬためには、
妾の身を世間と切り離してしまえば良い。だから妾はこうして独り、水の霊力を弱める『土』に囲まれた場所に
籠もった。そして妾がいなくても国を守れるよう、八乙女には妾の持てる限りの知識を『
祈道』として授けた。妾さえこの孤独に耐えれば、全てが丸く治まると、そう思っていたのだ」
「なるほど。その御姿は、長い歳月土の中に籠もり、水の霊力を削られたがゆえのこと……というわけですか。ですが、そんなあなたの御心も知らず、
霧狭司の国人は止める神がいないのを良いことに、その
祈道と武力で周りの国々を
脅かし始めた。さらには国民同士でさえ、争い、命を奪い合っている」
黙っていられずに言葉を
紡ぐと、女神は打たれたかのように俺を見、哀しげに目を伏せた。
「そなたは、
泊瀬に手を貸してくれた蛇神だな。まずは礼を言わせてもらおう。……そして、そなたの言う通りだ。
妾の考えが甘かったのかも知れん。国民達の
暴挙を、妾は止めることができなかった。心ある八乙女や
王子、
王女たちに夢で何度も呼びかけたが、彼らの訴えは他の氏族の者達に
握りつぶされた。それどころか、そのせいで他の者達に
疎まれ、命を落とした者さえいる」
「そんな……」
花夜は
衝撃に声を震わせる。女神は伏せていた目を上げ、哀しげな表情のまま泊瀬を見つめた。
「そもそも皆、信じないのだ。夢で
妾に会ったという者達の言葉を。
泊瀬、妾に会ったというお前の言葉を他の者達が簡単には信じなかったように、な」
女神の言葉に泊瀬はうつむき、自分の過去を振り返るかのように固く
拳を
握りしめた。
「……確かに。夢の中で神と会うことが国王の器を持つ
証だの何だのと言われているせいで、余計に皆、信じてくれなかった。ただの夢だと笑われたり、
嘘つき呼ばわりされたり……」
気遣うように泊瀬を見つめ、花夜がぽつりとつぶやく。
「自分の目に見えないもの、自分の耳には聞こえないものを、
人間はそう
容易く信じてはくれませんからね……」
「けれど、一度でも
鎮守神様が御姿をお見せになれば、皆きっと心を改めますわ!ですから鎮守神様、どうか皆の前に御姿をお見せください!そのまま永久に地上にお留まりくださいとは申しません。ただ一度だけで良いのです!ただ一度だけ……皆を
諭してくださいませ。そうすれば、きっとこの国は良くなります!」
海石が必死に
訴える。だが女神は全てを
諦めたかのように力無く首を振るだけだった。
「一度姿を現した
程度でこの国が変わることはないだろう。変わったとしても一時だけのこと。
妾の
諌めなどすぐに忘れ、あるいは
都合の良いように解釈をねじ曲げ、国民達は再び
過ちを犯し始める。妾が大宮にいた
頃から既に、国民達は表向きは妾の言葉に従いながら、裏では悪事を重ねていた。そして妾はそれを知るたびに心を乱し、やがて
荒魂となってこの国に災いをもたらした。もう、あのようなことを繰り返したくはない。妾はここを永久に出ないと決めたのだ」
「そんな……」
言葉を失う
海石に代わり、俺は再度口を
開いた。
「
畏れながら、その言い様は鎮守神としていかがなものかと存じます。鎮守神ならば己の加護する国民の
過ちは己の手で正すべきかと存じますが」
それは女神の怒りを買うことを
覚悟の
無礼な発言だった。そもそも鎮守神の中には己の加護する国ばかりを過度に重視し、他国のことはまるで眼中に無い神も多い。自分の言っていることが単なる理想論に過ぎないことは百も
承知だった。
だが女神は
怒りもせず、ただ静かに言葉を返すだけだった。
「……すまんな。
霧狭司国のことは、もはや
妾にもどうすることもできん。どうすれば皆が心を改めてくれるのか、妾にも分からんのだ。情けないことだが、人間の心がこんなにも動かし
難く、
難解なものだとは妾もこうなるまで全く知らなかった。もし霧狭司国を止めようとするならば、もはや、全てを
壊し
一から
創り直すより他に
術は無い。そして
妾は、
そのことを何よりも恐れているのだ」
「どういうこと、ですか?」
女神の
口調に
不穏なものを感じ取ったのか、問う泊瀬の声はひどく
硬い響きをしていた。
「
妾はここで長き間、
霧狭司の悪事を見つめ続けてきた。そしてこれを正すにはもはや国を壊すしかないと
考えてしまっている。……その妾がもしこの先、
荒魂になることがあったなら……、妾はその考えを、現実のものにしてしまうかも知れん、ということだ」
語る声は変わらず静かなものだったが、聞いていた者は皆、その言葉に身を
震わせた。相手は
水神だ。言葉通り、霧狭司国一つを
壊滅させるなど
造作もないことだろう。そして、
荒魂となった女神の心は自分自身でも制御することができない。もし怒りが
鎮まらなかったとしたら、事は霧狭司一国だけでは終わらないのだ。
「分かったであろう?だから
妾はここを出ることができないのだ。妾のために
命懸けでここまで来てくれたそなたらには悪いが、
許せ」
あまりにも恐ろしい可能性を示されて、それでも女神にここから出てくれとは誰も言えなかった。俺たちはただ、女神の言葉を受け入れるしかなかった。
呆然自失の
体で立ち
尽くす俺たちに、女神が鋭く告げる。
「皆の者、一刻も早くここを出よ。そして
射魔の家には戻らず、すぐに
宮処を離れるのだ。そなたらが結界を破ったことはすぐにでも八乙女に知れるだろう。追っ手がかかる前に逃げるのだ」
その言葉に皆ハッと顔色を変えた。
「……そうですわ。他の氏族の方々は
泊瀬様の御言葉を信じません。
下手をすれば神域を
侵した罪で
裁かれてしまうかも知れませんわ!」
「そんな……」
泊瀬はそれでも
離れ
難そうに女神を見つめ続ける。女神は泣き笑いのような表情で泊瀬を見つめ返し、そっとその
頬に
触れた。
「すまなかったな、泊瀬。
妾が一方的にお前との
交わりを
断ったせいで、お前をいたづらに苦しめた。あれはお前を
想ってのこと。かつて
妾の声を夢に聞いた他の
王子たちのように、お前を苦境に落としたくはなかった。妾の
本意ではなかったのだ」
「ミヅハ様……」
泊瀬は
戸惑うように女神の名を呼ぶ。女神は心から
愛しむように言葉を続けた。
「お前は
妾を救いたいと言ってくれたが、妾は
既にお前に救われていたぞ。長き孤独の中、夢の中だけでも妾と
交わってくれる存在があって、どれほど心が
癒されたことか……。何もしてくれなくても良い。ただ妾と言葉を
交わし、笑ったり泣いたりしてくれる……それだけで良かったのだ。その上、お前は妾を気にかけ、妾を想い、こうして危険を
冒してまで
駆けつけてくれた。そんな人間がいてくれるというだけで、心は救われるものなのだ」
言って、女神は
名残り
惜しそうにその指を
離した。
「行くのだ、泊瀬。必ず逃げ
延びよ。
妾はずっと、水を通してお前のことを見守っているぞ」
泊瀬はそれでも
躊躇うように立ち止まっていたが、
海石に
促されようやく歩を
踏み出した。
俺たちは重い足を引きずるようにして、女神の石室を後にした。