第九章 土の下の女神(3)
「一度姿を現した程度 でこの国が変わることはないだろう。変わったとしても一時だけのこと。妾 の諌 めなどすぐに忘れ、あるいは都合 の良いように解釈をねじ曲げ、国民達は再び過 ちを犯し始める。妾が大宮にいた頃 から既に、国民達は表向きは妾の言葉に従いながら、裏では悪事を重ねていた。そして妾はそれを知るたびに心を乱し、やがて荒魂 となってこの国に災いをもたらした。もう、あのようなことを繰り返したくはない。妾はここを永久に出ないと決めたのだ」
「そんな……」
言葉を失う海石 に代わり、俺は再度口を開 いた。
「畏 れながら、その言い様は鎮守神としていかがなものかと存じます。鎮守神ならば己の加護する国民の過 ちは己の手で正すべきかと存じますが」
それは女神の怒りを買うことを覚悟 の無礼 な発言だった。そもそも鎮守神の中には己の加護する国ばかりを過度に重視し、他国のことはまるで眼中に無い神も多い。自分の言っていることが単なる理想論に過ぎないことは百も承知 だった。
だが女神は怒 りもせず、ただ静かに言葉を返すだけだった。
「……すまんな。霧狭司国 のことは、もはや妾 にもどうすることもできん。どうすれば皆が心を改めてくれるのか、妾にも分からんのだ。情けないことだが、人間の心がこんなにも動かし難 く、難解 なものだとは妾もこうなるまで全く知らなかった。もし霧狭司国を止めようとするならば、もはや、全てを壊 し一 から創 り直すより他に術 は無い。そして妾 は、そのこと を何よりも恐れているのだ」
「どういうこと、ですか?」
女神の口調 に不穏 なものを感じ取ったのか、問う泊瀬の声はひどく硬 い響きをしていた。
「妾 はここで長き間、霧狭司 の悪事を見つめ続けてきた。そしてこれを正すにはもはや国を壊すしかないと考えてしまっている 。……その妾がもしこの先、荒魂 になることがあったなら……、妾はその考えを、現実のものにしてしまうかも知れん、ということだ」
語る声は変わらず静かなものだったが、聞いていた者は皆、その言葉に身を震 わせた。相手は水神 だ。言葉通り、霧狭司国一つを壊滅 させるなど造作 もないことだろう。そして、荒魂 となった女神の心は自分自身でも制御することができない。もし怒りが鎮 まらなかったとしたら、事は霧狭司一国だけでは終わらないのだ。
「分かったであろう?だから妾 はここを出ることができないのだ。妾のために命懸 けでここまで来てくれたそなたらには悪いが、許 せ」
あまりにも恐ろしい可能性を示されて、それでも女神にここから出てくれとは誰も言えなかった。俺たちはただ、女神の言葉を受け入れるしかなかった。
呆然自失 の体 で立ち尽 くす俺たちに、女神が鋭く告げる。
「皆の者、一刻も早くここを出よ。そして射魔 の家には戻らず、すぐに宮処 を離れるのだ。そなたらが結界を破ったことはすぐにでも八乙女に知れるだろう。追っ手がかかる前に逃げるのだ」
その言葉に皆ハッと顔色を変えた。
「……そうですわ。他の氏族の方々は泊瀬 様の御言葉を信じません。下手 をすれば神域を侵 した罪で裁 かれてしまうかも知れませんわ!」
「そんな……」
泊瀬はそれでも離 れ難 そうに女神を見つめ続ける。女神は泣き笑いのような表情で泊瀬を見つめ返し、そっとその頬 に触 れた。
「すまなかったな、泊瀬。妾 が一方的にお前との交 わりを断 ったせいで、お前をいたづらに苦しめた。あれはお前を想 ってのこと。かつて妾 の声を夢に聞いた他の王子 たちのように、お前を苦境に落としたくはなかった。妾の本意 ではなかったのだ」
「ミヅハ様……」
泊瀬は戸惑 うように女神の名を呼ぶ。女神は心から愛 しむように言葉を続けた。
「お前は妾 を救いたいと言ってくれたが、妾は既 にお前に救われていたぞ。長き孤独の中、夢の中だけでも妾と交 わってくれる存在があって、どれほど心が癒 されたことか……。何もしてくれなくても良い。ただ妾と言葉を交 わし、笑ったり泣いたりしてくれる……それだけで良かったのだ。その上、お前は妾を気にかけ、妾を想い、こうして危険を冒 してまで駆 けつけてくれた。そんな人間がいてくれるというだけで、心は救われるものなのだ」
言って、女神は名残 り惜 しそうにその指を離 した。
「行くのだ、泊瀬。必ず逃げ延 びよ。妾 はずっと、水を通してお前のことを見守っているぞ」
泊瀬はそれでも躊躇 うように立ち止まっていたが、海石 に促 されようやく歩を踏 み出した。
俺たちは重い足を引きずるようにして、女神の石室を後にした。
「そんな……」
言葉を失う
「
それは女神の怒りを買うことを
だが女神は
「……すまんな。
「どういうこと、ですか?」
女神の
「
語る声は変わらず静かなものだったが、聞いていた者は皆、その言葉に身を
「分かったであろう?だから
あまりにも恐ろしい可能性を示されて、それでも女神にここから出てくれとは誰も言えなかった。俺たちはただ、女神の言葉を受け入れるしかなかった。
「皆の者、一刻も早くここを出よ。そして
その言葉に皆ハッと顔色を変えた。
「……そうですわ。他の氏族の方々は
「そんな……」
泊瀬はそれでも
「すまなかったな、泊瀬。
「ミヅハ様……」
泊瀬は
「お前は
言って、女神は
「行くのだ、泊瀬。必ず逃げ
泊瀬はそれでも
俺たちは重い足を引きずるようにして、女神の石室を後にした。
※このページは津籠 睦月によるオリジナル和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」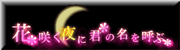 のモバイル版本文ページです。
のモバイル版本文ページです。
ページ内の文字色の違う部分をクリックしていただくと、別のページへジャンプします。
個人の趣味による創作のため、全章無料でご覧いただけますが、著作権は放棄していませんので、無断転載等はおやめください。
モバイル版はPC版とはレイアウトが異なる他、ルビや機能が少なくなっています。
