第四章 棄 てられた姫(2)
血の気 が引いていくのが自分でも分かった。
「花夜、今すぐ俺のそばから離れろ!……いや、ここで一人にさせるのは、かえって危ないか。しかし……」
考えもまとまらぬままに、とにかく花夜だけは逃がそうと俺は必死に怒鳴 る。だが花夜は当然戸惑 うばかりだった。
「何を焦 っておいでなのですか、ヤト様。何故 、離れろなどとおっしゃるのですか?」
「とにかく行くぞ!少しでも神社の場所から距離をとらねばならん」
俺は花夜の手をとり立ち上がらせると、すぐに茂 みを掻 き分け、森の奥へと駆 け出した。花夜は何も分からぬまま、それでも黙 って俺について来る。だが、ただでさえ長旅で疲 れている上、岐神 との闘いの傷も癒 えてはいないのだ。花夜は次第 に呼吸を荒くしていき、ついには足をもつれさせ、転んでしまった。
「花夜!」
「大丈夫、です……。先へ行って下さい」
「何を言う!お前、膝 が震えてまともに立てていないではないか!」
俺は己の不甲斐 なさに歯噛 みした。いつもそうだ。精霊だったあの頃 も、神となってからも、俺はただ一人の人間すら守りきれていない。
俺はその場に腰を屈 め、擦 り傷だらけの花夜の手当てを始めた。
「すみません。私がもっとちゃんと走れれば……」
「お前が謝 ることではない。悪いのは俺だ」
「あの、私にはまだ分からないのですが、何故 逃げなければならないのですか?」
「神使の一匹を捕らわれたと言っただろう。神使と俺は魂 の緒 で結ばれているのだ。それはすなわち……」
「すなわち、魂の緒をたどれば、その主の元へ行き着けるということ」
ふいに凛 とした声が森に響いた。ぎょっとして振り返ると、そこにはいつの間に現れたのか、一人の巫女の姿があった。つややかな黒髪を頭上高くから結 い垂 らし、白い上衣と燃えるような深紅 の裳 に身を包んだ、年の頃 十七、八と思 しき巫女だ。その手には、ヒサゴの蔓 で全身を縛 り上げられた、俺の神使の一匹が握 られていた。
「そなた達ですね。この白蛇 を神社に放 ったのは」
巫女は音も無くこちらに歩み寄って来る。兵士の一人も連れていないというのに、こちらを恐 れる様子など全く無く、それどころかその顔にはどんな表情も浮かんではいなかった。無駄 な動きが一切無く、感情ですら表さないその様 は、生きている人間のものとは思えず、まるで神か精霊か、あるいはよくできた人形でも目にしているかのような不気味さを醸 し出していた。
「……あなたは、霧狭司国 の八乙女の一人ですね」
花夜が警戒心 も露 に問う。目の前の巫女が相当に高い身分の姫であることは、その身につけた鮮 やかな裳 の色からも明らかだった。『紅 の八入 』と呼ばれるその色は、高価な紅花を惜 しみなく使い、さらにその染液に何度も何度も数えきれぬほど浸 し入れなければ出せない。花夜が身につけていた裳のような、茜 で染める茶色がかった緋色 とは根本からして違 う、贅 と手間を尽 くしたものなのだ。
巫女は花夜の問いにほんのわずか、美しい眉 をひそめた。
「自らは名乗らず、私に名乗りを求めるのですか。まあ、良いでしょう。たとえ礼を欠いていようとも、問われたからには答えて差し上げます。私は水響 む霧狭司国の八乙女が一人、雲箇 。国を治 める二十一氏族が一つ、葦立氏 の姫。そして霧狭司の国王の命により遣 わされた、花蘇利国 の新しき社首 です」
「花夜、今すぐ俺のそばから離れろ!……いや、ここで一人にさせるのは、かえって危ないか。しかし……」
考えもまとまらぬままに、とにかく花夜だけは逃がそうと俺は必死に
「何を
「とにかく行くぞ!少しでも神社の場所から距離をとらねばならん」
俺は花夜の手をとり立ち上がらせると、すぐに
「花夜!」
「大丈夫、です……。先へ行って下さい」
「何を言う!お前、
俺は己の
俺はその場に腰を
「すみません。私がもっとちゃんと走れれば……」
「お前が
「あの、私にはまだ分からないのですが、
「神使の一匹を捕らわれたと言っただろう。神使と俺は
「すなわち、魂の緒をたどれば、その主の元へ行き着けるということ」
ふいに
「そなた達ですね。この
巫女は音も無くこちらに歩み寄って来る。兵士の一人も連れていないというのに、こちらを
「……あなたは、
花夜が
巫女は花夜の問いにほんのわずか、美しい
「自らは名乗らず、私に名乗りを求めるのですか。まあ、良いでしょう。たとえ礼を欠いていようとも、問われたからには答えて差し上げます。私は
※このページは津籠 睦月によるオリジナル和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」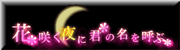 のモバイル版本文ページです。
のモバイル版本文ページです。
ページ内の文字色の違う部分をクリックしていただくと、別のページへジャンプします。
個人の趣味による創作のため、全章無料でご覧いただけますが、著作権は放棄していませんので、無断転載等はおやめください。
モバイル版はPC版とはレイアウトが異なる他、ルビや機能が少なくなっています。
