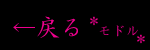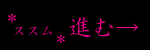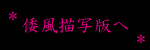第六章 |
「はい、花かんむりです」
断る暇 も、そもそもその選択肢 すら与えられず、俺の頭に花かんむりが載 せられる。目の前で満面の笑みを浮かべる花夜に対し、俺は半 ば諦 めの境地に入りながらも一応の文句 をつける。
「花夜、もういい加減 、毎年毎年俺に花かんむりを作るのはよさないか」
それは、俺と花夜が出会ってから四年後の春のこと。俺達は、霧狭司国 の西隣『山深き峡国 』を訪れていた。
すみれ、茅花 、片栗 に、山吹 、椿 、馬酔木 の花……、山道には色とりどりの花々が咲き乱れていた。
「なぜですか?約束したではありませんか。春になったら花かんむりを捧 げますと」
「あれは言葉の上だけのことだろう。実際に作らなくても良い。そもそも、俺に被 せたところで似合うわけがないではないか」
「いいえ、とてもよくお似合いですよ。花の方が恥 じらってしまうほどに。蛇身 に変化 する神は皆 、美しい外見を持つと聞きますが、その言い伝えは真実だったようですね」
「……そのようなこと、真顔 で言うものではない」
何の含 みもなく告げられる賛辞 に、こちらの方が気恥 ずかしい気分になる。俺はわざとぶっきらぼうな口調 でそう言い、花かんむりを外 した。
「ほら、これはお前が被 っていろ。俺などよりよほど似合う」
長く伸 びた花夜の髪の上にふわりと花かんむりを載 せる。花夜はくすぐったそうに笑った。
花蘇利 を出てから花夜は変わった。母のように立派な巫女らしくあろうと気負うのをやめた彼女は、年相応 の少女らしい表情も見せるようになった。育ちのせいで良くも悪くも世間知らずな彼女は、時に素直過ぎる言動 で俺をうろたえさせたりもするが、その様子はまるでサナギを脱 ぎ捨てた蝶 のように伸 びやかで生き生きとして見えた。
「それにしても、さすがに山神様の加護 の篤 い国だけあって、ここに咲く花はどれも見事 ですね。ここの土地に植えていけば、この花も無事 に育ってくれるでしょうか」
そう言って花夜は腰の小袋から幸有 の花の種を取り出した。
「そうだな。山神の加護ももちろんのことだが、この国の南の境界の不尽 の山には木花咲耶比売尊 もいらっしゃると言う。花々にとっては恵まれた土地かも知れないな」
俺の言葉を受け、花夜は種を植えるため、その場にしゃがみ込 もうとした。だがその時、ふいに俺の耳に不穏 な物音と人間の声が飛び込んできた。花夜にも聞こえたのか、ハッと顔を強張 らせて音のした方を見つめる。
「今のは……悲鳴ですか!?」
「ああ。それも一人や二人ではないな。何かの争い……いや、力の無い者達が一方的に襲 われているようだ」
「旅人を襲う賊 でしょうか。……ヤト様!」
花夜はただ振り返って俺を呼んだ。意図 を察し、俺はしぶしぶ変化 をとる。本当は危険なことに首を突 っ込 んで欲しくなどないのだが、彼女の性格がそれを許 さぬのだから仕方 がない。一瞬で大刀 へと変わった俺を掴 み取り、花夜は声のした方へと駆 け出した。頭に載 せていた花かんむりがぱさりと地に落ちる。
駆けつけた先では数人の農夫 が賊 に襲 われていた。道の上には荷車 が横倒しになり、そこに積 まれていたであろう の
の布 が辺 りに散らばっていた。おそらくは邑 に課 せられた調 物 を国府へ納めに行く途中 で襲われたのだろう。
「あなた達!何をしているのですか!?」
淡い桃花染 の衣を翻 し、俺を頭上高く振り上げて、花夜は叫んだ。
賊達は一瞬面食 らったように動きを止め花夜を見つめていたが、その顔には次第 に下卑 た笑 みが浮かんでいく。
「おい、見ろよ。こんな田舎 にゃ珍 しい香少女 じゃないか。おまけに持っている大刀 も相当な上物 だ。どうする?」
「分かりきったことを聞くな。両方いただくに決まっているだろう」
問いも、言葉自体さえも無視されながら、それでもなお、花夜は言葉での説得 を試 みる。
「今すぐ略奪 をやめなさい。あなた達が奪おうとしているものは、そこの農夫の皆さんが膨大 な時間と労力を費 やして作り上げた労苦の成果です。それを武力で踏 みにじろうと言うなら、容赦 しません」
だが、いかにも非力 な少女にしか見えない花夜のそんな言葉で、賊達が考えを変えるはずなどなかった。
「容赦 しない、だと?何をどう容赦しないって言うんだ?あんたみたいな娘さんが」
「馬鹿 な娘だなぁ。わざわざ自分から飛び込んで来るなんてな。大刀さえ握 れば俺たちに敵 うとでも思ったのか?」
花夜のことを端 から舐 めてかかっている賊達は、嘲 りの言葉を口にしながらじりじりと近づいてくる。花夜はため息をつき、俺の刀身 を振 り回し始めた。
「どうやら、改心する気は無いようですね。ならば、容赦 なく当てさせていただきます。……神罰 を」
俺を握 った腕 を大きく振り回しながら、花夜は踊 る。刀身が風を切り、刃先に火花が散る。それはやがて一点に集まり、朱 くゆらめく炎 を成 していく。賊達はぎょっとして後ずさった。
「な……っ、何だ、あれは……っ」
「分からん。だが、とにかく逃 げろ!」
「逃がしはしません。神使 よ、出 でませ!」
花夜が鋭 く叫ぶと、草野から神使の蛇 が次々と現れ賊達の退路 を塞 いだ。恐怖に顔を引きつらせる賊達へ向け、花夜は俺の刀身 を振るう。刃先に渦巻 いていた炎 は、まるで流星のごとく宙空 を駆 け、幾筋 かの炎の矢となって賊達に向かっていった。
「うわぁああぁッ!?」
賊達の全身が瞬 く間 に火焔 に包まれる。花夜は間 を置かずに再び俺の刀身 を振るった。今度は火花ではなく鎌鼬 のような風が巻き起こり、賊達の身を包む炎を一瞬で消し飛ばす。賊達は髪や衣を焼き焦 がした姿で、ただ呆然とその場に立ち尽 くしていた。そこへ花夜が静かに歩み寄る。
「ひッ!?」
「く、来るなっ!」
「殺さないでくれっ!頼 む!」
「その命乞 い、あなた達に襲 われたこの人達もしたのではありませんか?」
花夜はどこか可哀相 なものを見るような表情で賊達を見つめながらも、その喉元 に刃を突きつける。
「きっとあなた達は、今までにその罪に見合った罰 を受けてこなかったせいで高 を括 っているのでしょうけれど、悪事の報 いというものは受ける時には受けるものなのですよ」
あくまでも当たり前のことを言い聞かせるように、穏 やかな口調 で花夜は語りかける。だが、そんなその場の空気にそぐわない花夜の姿が余計に賊達の恐怖を煽 ったらしかった。彼らは奇妙な声を発し、後も見ずに走り出そうとした。だが、周りは既 に囲まれていて逃げ場などあるはずもなく、賊達はみっともない姿でその場に転がった。その身体の上を、すかさず神使の蛇達がにゅるりと這 い回る。賊達は恐怖に頬 を引きつらせ、そのまま気を失った。
断る
「花夜、もういい
それは、俺と花夜が出会ってから四年後の春のこと。俺達は、
すみれ、
「なぜですか?約束したではありませんか。春になったら花かんむりを
「あれは言葉の上だけのことだろう。実際に作らなくても良い。そもそも、俺に
「いいえ、とてもよくお似合いですよ。花の方が
「……そのようなこと、
何の
「ほら、これはお前が
長く
「それにしても、さすがに山神様の
そう言って花夜は腰の小袋から
「そうだな。山神の加護ももちろんのことだが、この国の南の境界の
俺の言葉を受け、花夜は種を植えるため、その場にしゃがみ
「今のは……悲鳴ですか!?」
「ああ。それも一人や二人ではないな。何かの争い……いや、力の無い者達が一方的に
「旅人を襲う
花夜はただ振り返って俺を呼んだ。
駆けつけた先では数人の
「あなた達!何をしているのですか!?」
淡い
賊達は一瞬
「おい、見ろよ。こんな
「分かりきったことを聞くな。両方いただくに決まっているだろう」
問いも、言葉自体さえも無視されながら、それでもなお、花夜は言葉での
「今すぐ
だが、いかにも
「
「
花夜のことを
「どうやら、改心する気は無いようですね。ならば、
俺を
「な……っ、何だ、あれは……っ」
「分からん。だが、とにかく
「逃がしはしません。
花夜が
「うわぁああぁッ!?」
賊達の全身が
「ひッ!?」
「く、来るなっ!」
「殺さないでくれっ!
「その
花夜はどこか
「きっとあなた達は、今までにその罪に見合った
あくまでも当たり前のことを言い聞かせるように、
「あの、大丈夫 ですか?お怪我 はされていませんか?」
花夜は道にうずくまる農夫達に歩 み寄り、声を掛けた。農夫達は花夜と、大刀から姿を変えた俺の姿を見て顔色を変え、地に頭を擦 りつけるようにして平伏 した。
「大刀に宿る神様とその巫女様!お助け下さり、真にありがとうございます!何とお礼を申し上げたら良いのか……」
農夫達のその態度に、花夜はむしろ恐縮 したようにあわてて口を開く。
「いえ、当然のことをしたまでですから。そのように畏 まらないで下さい」
「そのようなわけには参りません!もしあなた様方がお助け下さらなければ、我々はあのまま殺されていました!」
「そうです。是非 お礼をさせて下さい。我ら、田舎暮らしの農夫の身にて、大 したおもてなしはできませんが、せめて一夜の宿と御食 くらいは……」
『御食』という言葉に、花夜の眉 がぴくりと動いた。
「い、いえいえ。そのような……。私達は何も見返りを求めてあなた方を助けたわけではありませんし……」
口では遠慮 しながらも、その目はどこか期待するように輝きを帯 びていた。仮にも元は一国の姫であり、神と契 りを結んだ巫女としてあるまじき態度ではあるのだが、無理もないことだ。ここしばらくの間、口にしてきたものと言えば神使 の蛇達の集めてきた野草 や茸 ばかりだったのだから。
「花夜、どうせ今夜の宿の当ても無いのだ。ここは素直に礼を受けよう」
俺が促 すと、花夜は顔をほころばせてうなずいた。
花夜は道にうずくまる農夫達に
「大刀に宿る神様とその巫女様!お助け下さり、真にありがとうございます!何とお礼を申し上げたら良いのか……」
農夫達のその態度に、花夜はむしろ
「いえ、当然のことをしたまでですから。そのように
「そのようなわけには参りません!もしあなた様方がお助け下さらなければ、我々はあのまま殺されていました!」
「そうです。
『御食』という言葉に、花夜の
「い、いえいえ。そのような……。私達は何も見返りを求めてあなた方を助けたわけではありませんし……」
口では
「花夜、どうせ今夜の宿の当ても無いのだ。ここは素直に礼を受けよう」
俺が