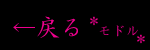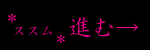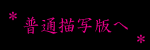第五章 花に |
半日ほども待った後 、ようやく花蘇利 の首長 ・萱津彦 は現れた。
どことなく花夜に似た面差 しを持つその男は、身体 つきや顔の造作 は聞いていた齢 より若く見えるほどだったが、その瞳は若々しさとはほど遠く、どこか疲れたように暗く虚 ろに陰 っていた。
「花夜……。戻って来てしまったか」
命懸けの旅から戻った娘に対し、彼は表情一つ動かすことなく、ただ『戻って来て欲しくはなかった』とでも言いたげにそう言った。その声音から感情は一切読み取れなかった。
「父 さま、答えて下さい。雲箇 姫の言葉は真実 なのですか?花蘇利は自ら霧狭司 の支配を受け入れたのですか?」
花夜が飛びつかんばかりの勢いで問う。萱津彦は静かに答えを返した。
「今ならば、単なる属国としてではなく、霧狭司を治める新たな氏族の一つとして迎え入れてくれるそうだ。これは破格の厚遇。この機を逃 せば次は無いやも知れぬ。花蘇利という国はなくなってしまうが、氏族の一つとして霧狭司の政 に携 われるのであれば、花蘇利に住む民の暮らしも保たれよう。それにこれでもう、霧狭司の影に怯 えて生きていくことはなくなるのだ」
「そのために、私を棄 てたのですか?霧狭司国に私を始末するよう言われて、それをそのまま呑 んだのですか?」
「私だとて努力はした。殺せと言うのを追放に止 めてもらうことができた。だが、それ以上はどうにもならなかった。私は首長だ。娘一人よりも国のことを優先させる義務がある」
花夜はそれを聞きながら、ぎり、と唇を噛みしめた。
「ならば、何故 私に嘘をついたのですか?花蘇利に鎮守神 を迎えて来いだなどと、生きて戻って来れぬかもしれぬ危険な旅を、何故 私にお命じになったのですか!?」
萱津彦は何も答えない。花夜は泣きそうな顔で言葉を続けた。
「真実 を言って私に詰 られるのが嫌で、その場凌 ぎの嘘をついたのですか!?あの時、私の頭を撫でて『幸 く有 れ』と言ってくださった、あれも偽りだったのですか?」
萱津彦は尚 も沈黙を続ける。花夜は消え入るような声で告げた。
「……嬉しかったのに。母 さまがいなくなってから、初めて優しい言葉をかけてもらえて……。勧請 の旅を無事に果たすことができれば、皆に許してもらえて、また昔のような暮らしに戻れると、信じていたのに……」
「……すまぬ」
萱津彦が返したのはただ一言だけだった。悲しみと怒りに震える花夜を納得させるには、到底 足りぬ言葉だ。
花夜は泣きそうに表情を歪 め、さらに何かを言おうと口を開きかけた。その時、花夜の腰で五鈴鏡にぼんやりと光が宿った。
『言葉が足りないところは変わりませんね。それでは想いは伝わりませんわ』
鏡から響いたその声に、萱津彦がハッと顔を上げる。直後、鏡面から光が飛び出した。光は瞬く間に独特な巫女装束を身につけた人の形へと変わる。
「花名女 !」
自らが付けた偽りの名を叫び、萱津彦が我を忘れたように駆け寄っていく。だが、その腕は鳥羽 の身をあっさりと突き抜けた。うっすらと向こう側を透かした鳥羽の身体を見つめ、萱津彦は息を呑 む。
『お久しぶりです、萱津彦様。このような姿ではありますが、あなたと再び見 えることができて嬉しく思います』
「花名女、お前は……最早 、霊 だけの存在と成り果ててしまったのか?」
萱津彦が絶望と諦念 の入り交じった顔で呟 く。鳥羽は哀しげに微笑んで頷 いた。
『萱津彦様、私はあなたの強さも弱さも、狡 さも優しさも、その全てを知っています。ですから、どうか花夜に真実をお話し下さい。あなたの御心の内に秘められた、一欠片 の優しさを、どうかこの子に示してあげて下さい』
鳥羽の言葉に萱津彦は大きく首を横に振る。
「そのようなこと、話してどうなる。全ては最早 、言い訳に過ぎぬ。私が花夜を棄 てた、そのことに変わりはないと言うのに」
『それは違います。父親にまるで愛されていなかったと誤解したまま生きるより、わずかでも愛されていたのだと知って生きる方が幸せなはずです』
「愛されて……いた?私が……?」
花夜が呆然と呟 く。萱津彦は鳥羽に促 され、ようやく重い口を開 いた。
「花夜、私はお前を、手放したくなどなかった。だが状況がそれを許さなかった。霧狭司の申し出を断れば戦になる。お前一人のために戦の道を選ぶなど、国人 の誰も納得してはくれぬ。だからとて真実を告げれば、お前は絶望し、生きる気力すら失くしてしまうかも知れぬと思った。そもそも、国を離れて女子 一人で生きていくことなど容易 いことではない。だから、偽りの命を下した。お前ならば困難な勧請の旅をも無事に成し遂げ、神と契りを交わすことができるやも知れぬと思ったのだ。そして神と契りを交わすことができたなら、たとえ国を追われ一人きりとなっても生きていくことができる。そのわずかな可能性に縋 ったのだ」
その言葉に、花夜は信じられぬとばかりに目を見開く。
「父さまは……私を憎んでおられたのではなかったのですか?」
「花名女が去ったあの時、お前を憎く思ったのは本当だ。その後も、憎しみが無かったと言えば嘘になる。全て元は私の咎 から始まったことと分かってはいても、お前の顔を見れば心が波立つ。お前があの時あの倉に忍び込んだりしなければ花名女が去ることはなかったのだと、どうしても考えてしまう。だから今まで私はお前を避けてきた。またお前に辛く当たってしまうのが恐かったのだ。……だが、お前のことはいつでも気にかかっていた。お前が社首 として皆に認められようと必死に努力してきたことも知っていた」
そこで一旦言葉を切り、萱津彦は初めて娘の顔をまともに見た。
「すまなかった、花夜。私は己の弱さに甘えていたのやも知れぬ。お前と向き合うのが恐くて、お前に全ての咎 を押しつけた己の醜 さに気づかされるのが恐くて、日々の忙 しさを言い訳に逃げてきたのだ。いづれ時が来れば、心の傷も癒 え、お前とも分かり合えるかも知れないと、なりゆきに身を任せ、自ら努力することをしなかった。お前を殺せと言われた時、ようやく私は己の本心に気づいたのだ。私はお前を喪 って平気ではいられぬ。蟠 りや擦 れ違 いがあろうとも、お前は私の娘であり、花名女の遺 した唯一 つの忘れ形見なのだから。今更 気づいたところで、最早 何もかもが遅いが……」
「父さま……」
花夜は躊躇 うように視線を彷徨 わせる。その肩に淡く透けた鳥羽の手が、そっと触れた。
『花夜、人間 の心とは複雑なもの。憎しみと愛とが共に胸の内に在 ることもあるのです。時に憎しみが勝り相手を傷つけても、その心から愛が消えてしまうわけではありません。憎しみに負けてしまうのは、人間 の心の弱さゆえのこと。辛いかも知れませんが、そのことだけは分かっておあげなさい。そしてあなたは憎しみに負けず、その心の内にある愛にしっかりと目を向けるのです』
花夜は拳をぎゅっと握りしめ、何かに耐えるように唇を震わせた。そして何かを決意したように、静かな目で父親を見据 えた。
「お互いを責め合うのは、もうやめにしましょう、父さま。どの道もう、こうしてお会いすることは叶 わぬのですから。私たちは、生き別れ、遠く離れてしまっても互いを想い合って暮らす親子―……それで良いではありませんか」
「花夜、良いのか?私はお前を棄 て、国の平和を択 ったというのに」
「首長 としては当然の選択です。私は父さまの決定に従います」
従順な言葉を述 べながらも、花夜の瞳は深い哀しみを必死に堪 えているように見えた。本当の想いを隠して無理矢理に作っているような、どこかぎこちない笑顔だった。
そして花夜は別れの言葉を告げた。これが今生 の別れであることを覚悟した言葉だった。
「では、父 さま。これにてお暇 申し上げます。父さまと花蘇利国に幸 く有らんことを祈 がっています」
そしてその後、花夜が花蘇利国に足を踏み入れることも、父親と見 えることも、二度となかった。
どことなく花夜に似た
「花夜……。戻って来てしまったか」
命懸けの旅から戻った娘に対し、彼は表情一つ動かすことなく、ただ『戻って来て欲しくはなかった』とでも言いたげにそう言った。その声音から感情は一切読み取れなかった。
「
花夜が飛びつかんばかりの勢いで問う。萱津彦は静かに答えを返した。
「今ならば、単なる属国としてではなく、霧狭司を治める新たな氏族の一つとして迎え入れてくれるそうだ。これは破格の厚遇。この機を
「そのために、私を
「私だとて努力はした。殺せと言うのを追放に
花夜はそれを聞きながら、ぎり、と唇を噛みしめた。
「ならば、
萱津彦は何も答えない。花夜は泣きそうな顔で言葉を続けた。
「
萱津彦は
「……嬉しかったのに。
「……すまぬ」
萱津彦が返したのはただ一言だけだった。悲しみと怒りに震える花夜を納得させるには、
花夜は泣きそうに表情を
『言葉が足りないところは変わりませんね。それでは想いは伝わりませんわ』
鏡から響いたその声に、萱津彦がハッと顔を上げる。直後、鏡面から光が飛び出した。光は瞬く間に独特な巫女装束を身につけた人の形へと変わる。
「
自らが付けた偽りの名を叫び、萱津彦が我を忘れたように駆け寄っていく。だが、その腕は
『お久しぶりです、萱津彦様。このような姿ではありますが、あなたと再び
「花名女、お前は……
萱津彦が絶望と
『萱津彦様、私はあなたの強さも弱さも、
鳥羽の言葉に萱津彦は大きく首を横に振る。
「そのようなこと、話してどうなる。全ては
『それは違います。父親にまるで愛されていなかったと誤解したまま生きるより、わずかでも愛されていたのだと知って生きる方が幸せなはずです』
「愛されて……いた?私が……?」
花夜が呆然と
「花夜、私はお前を、手放したくなどなかった。だが状況がそれを許さなかった。霧狭司の申し出を断れば戦になる。お前一人のために戦の道を選ぶなど、
その言葉に、花夜は信じられぬとばかりに目を見開く。
「父さまは……私を憎んでおられたのではなかったのですか?」
「花名女が去ったあの時、お前を憎く思ったのは本当だ。その後も、憎しみが無かったと言えば嘘になる。全て元は私の
そこで一旦言葉を切り、萱津彦は初めて娘の顔をまともに見た。
「すまなかった、花夜。私は己の弱さに甘えていたのやも知れぬ。お前と向き合うのが恐くて、お前に全ての
「父さま……」
花夜は
『花夜、
花夜は拳をぎゅっと握りしめ、何かに耐えるように唇を震わせた。そして何かを決意したように、静かな目で父親を
「お互いを責め合うのは、もうやめにしましょう、父さま。どの道もう、こうしてお会いすることは
「花夜、良いのか?私はお前を
「
従順な言葉を
そして花夜は別れの言葉を告げた。これが
「では、
そしてその後、花夜が花蘇利国に足を踏み入れることも、父親と
元来た道を辿 り、再び国境 の丘を登る。夕闇に包まれだした古里を見つめ、花夜は肩を震わせた。その唇から、嗚咽 に似た声が漏れる。だがその頬に泪 は伝っていなかった。泣くのを必死に堪 えている表情だった。
思えば俺はこの時まで、花夜が泣くところを見たことがなかった。泣きそうに瞳を潤ませても、いつも寸前で堪 え、泪 を流さずにいた。そのことに、この時になってようやく俺は気がついた。
「泣きたいならば思うままに泣けば良いではないか。誰もお前を咎 めたりはせぬ」
「い、いいえ……泣いたり、など……っ、しません。私は、そんなに……弱くなど、ありません……っ」
震えて思うままにならぬ声で、それでも花夜は必死に強がる。
「世の中の物事には、どんなものであれ存在する意味があると言ったのは、お前だろう。泣くことにも意味はある。人間 は弱さの証 のように言うが、泪 は泣沢女神 ――泪 と浄化を司る女神からの贈り物だ。女神の御力の宿った聖なる水が、身の内に溜まった哀しみや心の澱 を洗い浄 め、身体 の外へと流し出してくださるのだ」
「…………っ」
言葉にならぬ声を上げ、花夜が泣き崩れる。俺はその身を包み込むように抱き締めた。
「……どうして、こうなってしまうのですか?私、頑張ったのに。皆に許して欲しくて。無視したり、ハレモノに触るように扱うのではなく、普通に接して欲しくて……。だから、必死に努力したり、危険な旅にだって出たのに……っ。なのに、全部無駄でした。全部、失くしてしまいました。私は、どうすれば良かったのですか?これから、どうすればいいのですか……?」
俺の腕 に縋 りつき、心の内に溜 まったもの、今まで必死に堪 えてきた何もかもを吐き出すように、花夜は問いをぶつける。
それは、今にして思えば最初で最後の花夜の泣き言だった。
だが、俺には上手い慰 めの言葉が見つからなかった。花夜がこれまで実際にどれほどの努力を重ねてきたのか、俺は知らない。知っていたとしても、報われずに散ったその努力に見合うだけの慰めを、俺が与えられるとは思えなかった。だから慰めの代わりに一つだけ、その時の俺にできることをした。
「祈言 を言え、花夜」
「え……?」
花夜は弾 かれたように顔を上げ、俺を見た。『何を言っているのか分からない』とでも言いたげなその表情に、俺は再び口を開 く。
「たとえ鎮守 となるべき国が俺を拒んだとしても、俺とお前との契りは失われてはおらぬ。俺はお前の 神だ。だから祈 がいを言え。俺に叶えられるものならば何でも叶えてやる」
花夜の顔がくしゃりと歪 んだ。余計にひどくなった嗚咽を抑えようとでもするように俺の衣 に深く顔を埋 め、花夜は祈 がいを口にした。相変わらず、あまりに無欲でささやかな祈がいを……。
「……私を、ひとりにしないで……いっしょに、いて下さい。死ぬまで、ずっと……」
「当たり前だろう。俺はお前の神なのだぞ。お前から離れたりなどせぬ」
その言葉を、俺はごく自然に口にしていた。人間 の生涯を見守るということがどういうことなのか、俺は既に知っていたはずなのに、この時はまるで頭に浮かばなかった。
花夜は俺にしがみつき、泣き続けた。泣いて、泣いて、泣き疲れ、やがて気を失うように眠ってしまうまで。俺はその小さな身体 を、暁 まで離さず抱き締めていた。
思えば俺はこの時まで、花夜が泣くところを見たことがなかった。泣きそうに瞳を潤ませても、いつも寸前で
「泣きたいならば思うままに泣けば良いではないか。誰もお前を
「い、いいえ……泣いたり、など……っ、しません。私は、そんなに……弱くなど、ありません……っ」
震えて思うままにならぬ声で、それでも花夜は必死に強がる。
「世の中の物事には、どんなものであれ存在する意味があると言ったのは、お前だろう。泣くことにも意味はある。
「…………っ」
言葉にならぬ声を上げ、花夜が泣き崩れる。俺はその身を包み込むように抱き締めた。
「……どうして、こうなってしまうのですか?私、頑張ったのに。皆に許して欲しくて。無視したり、ハレモノに触るように扱うのではなく、普通に接して欲しくて……。だから、必死に努力したり、危険な旅にだって出たのに……っ。なのに、全部無駄でした。全部、失くしてしまいました。私は、どうすれば良かったのですか?これから、どうすればいいのですか……?」
俺の
それは、今にして思えば最初で最後の花夜の泣き言だった。
だが、俺には上手い
「
「え……?」
花夜は
「たとえ
花夜の顔がくしゃりと
「……私を、ひとりにしないで……いっしょに、いて下さい。死ぬまで、ずっと……」
「当たり前だろう。俺はお前の神なのだぞ。お前から離れたりなどせぬ」
その言葉を、俺はごく自然に口にしていた。
花夜は俺にしがみつき、泣き続けた。泣いて、泣いて、泣き疲れ、やがて気を失うように眠ってしまうまで。俺はその小さな