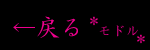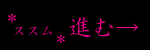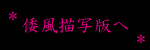第三章 |
「あれが
国境間際の丘の上、わずかに
『
「まずはとにかく、ある
「はい」
花夜は
(……あの時のようにはさせぬ。今度こそ守ってみせる。せめて、ただ一人だけでも……)
俺達は国府へ向け慎重 に歩みを進めた。だが、わずかに進んだ後、ふいに花夜が足を止めた。
「どうした、花夜」
「……変です。この辺りには確か、国境の目印となる杖があったはずですのに……」
花夜は何かを探すように周囲を見渡しながら、何度も首をひねる。
「霧狭司 の国の人間によって引き抜かれでもしたのではないか?行くぞ」
「はい……」
花夜は釈然としない顔をしながらも、再び先に立って歩きだした。
直後、その身がふいに宙に浮いた。
「きゃあっ!?」
身動き一つもできない間に、花夜の身体 が元来た方角へと吹き飛んでいく。それはまるで、視 えざる手につまみ上げられ、放り投げられたかのようだった。俺は血相 を変えて駆 け寄る。
「花夜っ!無事か!?」
「……はい、なんとか。でも、一体何が……」
花夜は手足に負った擦 り傷に顔をしかめながら、よろよろと立ち上がる。その時、俺たちの行く手から声が上がった。
「外より来たりし者達よ。ここより先、一歩でも中に踏み入ることは、我が許さぬ」
視線を移せば、先ほど花夜が踏み越えようとしていた辺りに、いつの間にか一人の男が立っていた。道を塞 ぐようにして立つその見知らぬ男は、頭にヒサゴの葉と蔓 でできた冠をかぶっていた。
「ここより先は、水を司る尊 き姫神・水波女神 の治 められる国。他国の者は即刻立ち去られよ。さもなくば、力づくで排除する」
びりびりと空気を震わせるその声には、聞く者の心に畏 れを抱かせる強い言霊 が籠 もっていた。俺はハッと男の顔を凝視する。この男は、人間ではない。神だ。人の姿をとった男神 なのだ。
「花蘇利が水神 様の治める国……?そんな……、それでは、もう既 に国府は陥落 していると……?」
男神の言葉に、花夜は目を見開き、糸が切れたようにくたりとその場に膝 をついた。
「花夜……」
俺は花夜の震える肩に、そっと手を置いた。
「どうする、花夜。守るべき国が既になくなったとなれば、お前が今、命を賭 けてまで戻ることはないと思うが。一度退 いて万全 の準備をした後に戻るのも一つの手段ではないのか?」
言いながらも、花夜がここで退くはずがないと、俺には分かっていた。そしてその予想に違 わず、花夜は首を横に振って立ち上がった。
「いいえ。今行かねばなりません。今行かねば救えぬ命もあるでしょう。それに、たとえ国が滅んだとしても花蘇利の民の最後の一人までを守り抜くのが花蘇利の姫たる私の義務です」
花夜はまだ震える足で男神の前へ進み出て、精一杯声を張り上げた。
「私は千葉茂る花蘇利国の社首 ・花夜です。そこをお通し下さい」
花夜の名乗りを、男神は鼻で嘲笑 った。
「花蘇利の首長 の娘か。汝 はもはや、社首ではない。花蘇利の神社には既に霧狭司の八乙女 の一人が入っている」
「八乙女……。そうか、汝を召 んでここを守らせたのは、その八乙女なのだな」
八乙女は、霧狭司の有力氏族 の姫達により構成される、高位の巫女集団だ。幼い頃より神宮でひたすら祈道 の修行に励 み、その霊力は並の巫女が十人束 になっても敵 わないと言われている。
花夜はきゅっと唇をひき結び、俺を見た。
「ヤト様、御力を貸して下さい。私はどうしても花蘇利へ戻らなくてはいけないんです。だから……っ」
力を貸せば、花夜を戦いへ向かわせることになる。俺はわずかの間、ためらった。だが結局は、花夜のすがるような目にうなずかざるを得なかった。
「……ああ。俺はお前の神だ。その祈 がい、叶えよう」
「どうした、花夜」
「……変です。この辺りには確か、国境の目印となる杖があったはずですのに……」
花夜は何かを探すように周囲を見渡しながら、何度も首をひねる。
「
「はい……」
花夜は釈然としない顔をしながらも、再び先に立って歩きだした。
直後、その身がふいに宙に浮いた。
「きゃあっ!?」
身動き一つもできない間に、花夜の
「花夜っ!無事か!?」
「……はい、なんとか。でも、一体何が……」
花夜は手足に負った
「外より来たりし者達よ。ここより先、一歩でも中に踏み入ることは、我が許さぬ」
視線を移せば、先ほど花夜が踏み越えようとしていた辺りに、いつの間にか一人の男が立っていた。道を
「ここより先は、水を司る
びりびりと空気を震わせるその声には、聞く者の心に
「花蘇利が
男神の言葉に、花夜は目を見開き、糸が切れたようにくたりとその場に
「花夜……」
俺は花夜の震える肩に、そっと手を置いた。
「どうする、花夜。守るべき国が既になくなったとなれば、お前が今、命を
言いながらも、花夜がここで退くはずがないと、俺には分かっていた。そしてその予想に
「いいえ。今行かねばなりません。今行かねば救えぬ命もあるでしょう。それに、たとえ国が滅んだとしても花蘇利の民の最後の一人までを守り抜くのが花蘇利の姫たる私の義務です」
花夜はまだ震える足で男神の前へ進み出て、精一杯声を張り上げた。
「私は千葉茂る花蘇利国の
花夜の名乗りを、男神は鼻で
「花蘇利の
「八乙女……。そうか、汝を
八乙女は、霧狭司の有力
花夜はきゅっと唇をひき結び、俺を見た。
「ヤト様、御力を貸して下さい。私はどうしても花蘇利へ戻らなくてはいけないんです。だから……っ」
力を貸せば、花夜を戦いへ向かわせることになる。俺はわずかの間、ためらった。だが結局は、花夜のすがるような目にうなずかざるを得なかった。
「……ああ。俺はお前の神だ。その
「良いか花夜、しっかりと握 っていろ」
俺は花夜の手のひらに己の手を重ね、眼 を閉じた。その瞬間、俺の身体は銀の光と化し、熔 けるように形を失 くす。光は一瞬、蛇のように長く細く伸びた後、一振 りの大刀 へと変わる。銀色に光る刀身には金 象嵌 で龍の姿が彫 り込まれ、柄頭 には透彫 を施 した環 っか状の飾 りがきらめく。花夜の肩の高さに達するほどの長さの直刀 ――それが、俺の本性だった。
「なんて見事な御神刀……。それに、なんて軽いのでしょう……。まるで空気をつかんでいるようです」
花夜は見惚 れたようにつぶやいた後、ハッとしたように顔色を変えた。
「お待ち下さい、ヤト様!私、大刀を握ったことなどありません!私ごときの腕 で神に挑 むなど、無理です!」
『心配するな。お前は巫女。戦士のように刃 を交 える必要はない。魂振 で戦うのだ』
その言葉に、花夜は目をみはり、驚いたように俺を見つめた。
「魂振 を……!?よろしいのですか?」
魂振を許すということは、神体と神の霊力をともにその手にゆだねるということ。よほど信頼している相手でなければ許すことができない。だが俺に迷いは無かった。
『ああ。お前にならば許そう。お前は俺が契 りを交 わしたただ一人の巫女だからな』
俺の言葉に花夜は神妙に頭を下げると、柄を握 り直し、改めて男神を見据えた。
「男神様、どうかそこをお退 き下さい。でなければ、力づくで通らせて頂きます」
「我に戦いを挑むか。少女と言えど、容赦 はせぬぞ」
男神は不敵な笑みを浮かべ、片脚を大きく振り上げた。その脚をそのまま、地を揺るがすような勢いで地面に突き立てる。呆気 にとられる花夜をよそに、男神は片脚を膝下近くまで地にめり込ませたまま叫んだ。
「クナ!」
その声は風となり、俺達の身に真 っ向 からぶつかってくる。踏ん張っても耐え切れず、花夜はその風に吹き飛ばされ、悲鳴を上げて地に転がった。
『花夜っ!』
「大丈夫です。でも、今のは一体……?」
『おそらくは言霊の力だ。『来な 』は侵入を阻 む言葉。すなわち俺たちを侵入者と見なし、言霊の霊力を振 って阻んでいるのだ。そして、地に脚を突き刺す動作は言霊の霊力を増すための何らかの呪術だろう。もしかすると、地の深くより霊力を吸い上げているのかも知れん』
「では、あの一連の動きを封じなくてはなりませんね」
花夜は俺の刀身を頭上高く持ち上げ、踊るように振り回し始めた。
魂振 とは、神体を振り動かすことにより、神の魂を震 わせることを言う。そしてその魂の内にある霊力を、昂 ぶらせ、引き出し、発動するのだ。後の時代の祭で、神体の乗った神輿 を担 ぎ、激しく振り動かすのも、この魂振の名残 りと言われている。
花夜の手により刀身を振り回されるうちに、俺は胸の奥底で何かが熱く滾 るのを感じた。興奮とも衝動ともつかぬそれが、身の内に湧 き溢 れ、霊力へと変わっていく。
「ハッ!」
霊力が満ちたのを見計らい、花夜が気合の声と共に俺を振り下ろした。霊力は風の刃となり、真っ直ぐに男神へと向かっていった。
「クナ!」
再び男神が叫ぶ。言霊を帯びた風は、俺達の巻き起こした風の刃とぶつかり合い、互いを打ち消し合って消えた。
『花夜!攻撃の間合いが長過ぎる!相手に反撃の隙 を与えるな!霊力を溜 めきってから攻めるだけでなく、魂振の合間にも細かく攻撃を加えるのだ!』
「はい!」
花夜は必死に俺の声に応 えようとする。だが、今まで神棲 まぬ国にいた花夜にとって、これが初めての魂振。勝手も分からぬまま、知識だけを頼りに行っているのだ。即座にそんな器用な真似 ができようはずもない。俺達は男神に傷らしい傷一つ負わせることもできず、ただ体力ばかりを削 り取られていった。
『……このままでは埒 が明 かんな』
俺の呟きに、花夜は荒い息で、ただ頭だけを縦 に振る。
『何か別の手を考えねばならぬのやも知れぬ。せめてあの男神の真名 を明かせれば、弱みが分かるやも知れぬが……』
「あの神様の真名……。正体、ということですか」
息も切れ切れに答えてから、花夜はしばし考え込む。
「あの神様、初めからずっと、あの場を動きませんね。そして攻撃の際には、必ず地に脚を突き刺し、霊力を得ています。あの神様の霊力の源は……『土』?……いいえ、もしかしたら、あの『場』なのかも知れません」
『あの『場』……。国境に立つということは、境界神 か。しかし境界神にもいろいろあるが……』
「国の境……、片脚を地に衝 き立てる……、外からの侵入を防ぐ神……」
花夜は次第に自分の考えに没頭 していく。だが男神はその隙を黙って見過ごしたりなどしなかった。
「クナ!」
言霊が風となり襲ってくる。
『まずい、避 けろ!花夜!』
叫んだが、遅かった。花夜は跳ね飛ばされ、悲鳴を上げて倒れる。
『大丈夫か!?』
俺の声に、花夜はむくりと起き上がる。だがその目は俺ではなく、男神にひたと向けられていた。何か重大なことに気づいたかのような顔で。
「『クナ』……。そうでしたか。その言霊にも意味があったのですね。分かりました。あなたの正体が」
花夜は男神を正面から見据え、毅然 と告げた。
「国の境の岐路に衝 き立ち、外から来るモノを『来な 』と阻む、視えざる戸――あなたは、国境の目印に立つ杖の神ですね。……『衝立岐神 』様」
それは、国の境目を守る境界神の名だった。国境を示し、そこを守るために突き立てられる杖に宿る神の名――花夜がその名を口にした途端 、男神の顔が苦しげに歪 みだした。
「よくも……我が真名を……っ!」
男神は怒りに顔を染め、花夜に掴 みかかろうと手を伸ばす。しかし、その腕は泥 のようにぐにゃりと曲がり、胴体と同化して消え失せた。否 、腕だけでなく、男神の全身が、くねり、歪み、色を変え、別のものへと変わっていく。驚き立ちすくむ花夜の目の前で、男神は地に突き立つ一本の杖へと姿を変えた。上部にヒサゴの蔓 がからまった、大きな木の杖だ。
花夜はおそるおそるその杖に近づき、触れてみる。
「これは間違いなく、花蘇利の国境にあった杖……!でも、どうして元に戻ったのでしょう?」
花夜は何が起きたのか全く分かっていない顔で俺を見る。
『化生 の神は、穢 れを知らぬ幼子 にその本性を見破られると、変化 を保てなくなると聞いたことがある。俺もこの目で見るのは初めてだが……』
軽い感動さえ覚えて言うと、花夜は頬 をふくらませた。
「『幼子』って……、私はもう十四です。幼くなどありません!」
「そういうことではない。お前の心が幼子のように無垢 で穢れがないという話だ」
俺は大刀から人の姿へと戻り、杖に歩み寄る。そして手指を真っ直ぐに伸ばし、杖の上部へ向け一閃させた。杖に巻きつけられたヒサゴの蔓 だけが、手刀 に切り裂かれ地に落ちる。花夜はそれをじっと見つめ、硬 い声で言った。
「ヒサゴは水神様の象徴、でしたよね」
「ああ。おそらく、この蔓 に霧狭司の巫女の呪術がかけられていたに違いない。これを断ち切った以上、岐神 が霧狭司側に味方することは、もう無いと思うが」
「神さえも従わせるほどの霊力の持ち主なのですね、霧狭司の八乙女は」
花夜の声には隠 しきれない恐怖がにじんでいた。
「今からでも遅くはない。引き返すか?」
国境の岐路 の上で、俺は問う。だが花夜は、自らを奮 い立たせるように強く拳 を握り、首を振る。
「いいえ、行きます。行かなければならないのです」
「……そうか」
俺はただうなずいた。胸を塞 ぐ暗い予感から目をそらしながら。
俺は花夜の手のひらに己の手を重ね、
「なんて見事な御神刀……。それに、なんて軽いのでしょう……。まるで空気をつかんでいるようです」
花夜は
「お待ち下さい、ヤト様!私、大刀を握ったことなどありません!私ごときの
『心配するな。お前は巫女。戦士のように
その言葉に、花夜は目をみはり、驚いたように俺を見つめた。
「
魂振を許すということは、神体と神の霊力をともにその手にゆだねるということ。よほど信頼している相手でなければ許すことができない。だが俺に迷いは無かった。
『ああ。お前にならば許そう。お前は俺が
俺の言葉に花夜は神妙に頭を下げると、柄を
「男神様、どうかそこをお
「我に戦いを挑むか。少女と言えど、
男神は不敵な笑みを浮かべ、片脚を大きく振り上げた。その脚をそのまま、地を揺るがすような勢いで地面に突き立てる。
「クナ!」
その声は風となり、俺達の身に
『花夜っ!』
「大丈夫です。でも、今のは一体……?」
『おそらくは言霊の力だ。『
「では、あの一連の動きを封じなくてはなりませんね」
花夜は俺の刀身を頭上高く持ち上げ、踊るように振り回し始めた。
花夜の手により刀身を振り回されるうちに、俺は胸の奥底で何かが熱く
「ハッ!」
霊力が満ちたのを見計らい、花夜が気合の声と共に俺を振り下ろした。霊力は風の刃となり、真っ直ぐに男神へと向かっていった。
「クナ!」
再び男神が叫ぶ。言霊を帯びた風は、俺達の巻き起こした風の刃とぶつかり合い、互いを打ち消し合って消えた。
『花夜!攻撃の間合いが長過ぎる!相手に反撃の
「はい!」
花夜は必死に俺の声に
『……このままでは
俺の呟きに、花夜は荒い息で、ただ頭だけを
『何か別の手を考えねばならぬのやも知れぬ。せめてあの男神の
「あの神様の真名……。正体、ということですか」
息も切れ切れに答えてから、花夜はしばし考え込む。
「あの神様、初めからずっと、あの場を動きませんね。そして攻撃の際には、必ず地に脚を突き刺し、霊力を得ています。あの神様の霊力の源は……『土』?……いいえ、もしかしたら、あの『場』なのかも知れません」
『あの『場』……。国境に立つということは、
「国の境……、片脚を地に
花夜は次第に自分の考えに
「クナ!」
言霊が風となり襲ってくる。
『まずい、
叫んだが、遅かった。花夜は跳ね飛ばされ、悲鳴を上げて倒れる。
『大丈夫か!?』
俺の声に、花夜はむくりと起き上がる。だがその目は俺ではなく、男神にひたと向けられていた。何か重大なことに気づいたかのような顔で。
「『クナ』……。そうでしたか。その言霊にも意味があったのですね。分かりました。あなたの正体が」
花夜は男神を正面から見据え、
「国の境の岐路に
それは、国の境目を守る境界神の名だった。国境を示し、そこを守るために突き立てられる杖に宿る神の名――花夜がその名を口にした
「よくも……我が真名を……っ!」
男神は怒りに顔を染め、花夜に
花夜はおそるおそるその杖に近づき、触れてみる。
「これは間違いなく、花蘇利の国境にあった杖……!でも、どうして元に戻ったのでしょう?」
花夜は何が起きたのか全く分かっていない顔で俺を見る。
『
軽い感動さえ覚えて言うと、花夜は
「『幼子』って……、私はもう十四です。幼くなどありません!」
「そういうことではない。お前の心が幼子のように
俺は大刀から人の姿へと戻り、杖に歩み寄る。そして手指を真っ直ぐに伸ばし、杖の上部へ向け一閃させた。杖に巻きつけられたヒサゴの
「ヒサゴは水神様の象徴、でしたよね」
「ああ。おそらく、この
「神さえも従わせるほどの霊力の持ち主なのですね、霧狭司の八乙女は」
花夜の声には
「今からでも遅くはない。引き返すか?」
国境の
「いいえ、行きます。行かなければならないのです」
「……そうか」
俺はただうなずいた。胸を