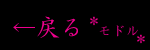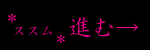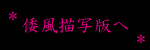第二章 神の生まれ出づる杜 |
「ヤト様、大丈夫ですか?」
我に返った花夜が心配そうに顔を覗 き込んできた。
「あの……っ、あなた様のお気持ちを無駄 にするような真似をして申し訳ございません!決してあなた様のことをおろそかにしているわけではなく、ただ、できる限り死者を出したくないという、その一心で……!」
天探女 をその身に降 ろしていた間のことをまるで覚えていない花夜は、俺の呆 けた顔を別の意味に解釈 したらしい。必死に弁解してきた。
「気にしてはおらんから、謝る必要はない。俺を止めたお前の判断は間違ってはおらん。まさか天探女を出してくるとは思わなかったが」
人心を惑 わす天探女を快 く思う者はあまりおらず、崇 めるどころか、後世では神であったことすら半ば忘れ去られ、妖怪のように扱 われることとなる。そんな女神に祈りを捧 げ祭祀 る娘がいるなど、俺はこの時まで想像したこともなかった。
「世の中の物事には、どんなものであれ存在する意味があるのだと、母が申しておりました。ですから……きゃっ!?」
花夜の言葉は彼女自身の悲鳴によって途切 れた。
目を移せば、俺達はいつの間にか人ならざるモノたちに囲まれていた。緑の髪に花や果実をからませた彼らは、こちらをじっと見つめ、何事かを口にする。だがその唇から零 れるのは、まるで木の葉擦 れのような『ざわざわ、ざわざわ』という音ばかりだった。
「……ヤト様っ」
花夜がおびえたように俺の衣袖 を握 ってきた。救いを求めるようなその瞳に、何か言葉を返そうと口を開きかけたその時、藤の木の元で光が弾 けた。白に、黄金に、虹の七色――ありとあらゆる色彩をひとつに凝縮 したような美しい光だった。
「お守り下さり、心より感謝申し上げます。蛇の姿を持つ神、そしてその巫女姫」
光の中から現れたのは、一柱の女神。白藤を思わせる純白の髪に藤紫の瞳、肩にまとった花の領巾 を風にひらめかせるその姿は、まさに藤の木の女神にふさわしいものだった。
「藤の木の女神様……。無事にお生まれになったのですね……」
女神の姿にうっとり見惚 れる花夜のそばに、人ならざるモノたちが歩み寄る。あいかわらず、ざわざわと言葉にならぬ声を出しながら、花夜に向かって手に持った何かを差し出す。困惑 する花夜に、女神が優しい声で語りかけた。
「この霊 たちは木霊 。この杜 の木々に宿る精霊が人の姿をとったものです。あなたに杜 の木を守ってくれたお礼をしたいのだそうですよ。どうか受け取ってあげて下さい」
「そうでしたか。ありがとうございます」
花夜が両手を差し出すと、木霊 たちは次々とその上に木の実や木の皮などを乗せていった。
「これは団栗 の実、それは黄櫨 の木の樹皮。どちらも染料として使えます。そちらは呉桃 の実、油が採 れますよ」
木霊たちの贈 り物はどれも森ではありふれた、しかし使いようによっては日々の暮らしを豊かにしてくれる品ばかりだった。藤の木の女神はそれら一つ一つを木霊 の言葉を通訳しながら説明してくれる。
やがて最後に、ひどくおずおずと遠慮 がちに、花夜の手のひらに幾粒かの種が置かれた。その種を渡してきたのは、他の木霊 たちより一回り小さな木霊の少女。彼女は消え入りそうに小さな声で『さわさわ』と囁 きかける。
「あの……彼女は何と言っているのでしょうか?」
「それは花の種だそうです」
他の木霊の陰 から顔だけを出し、恥ずかしそうにこちらを見る木霊の少女を、藤の女神は優しい目で見つめる。
「何の役にも立たないかも知れませんが、今の自分に用意できるのはその種だけですから、ぜひ持っていって欲しい、と言っています」
「役に立たないなんて、とんでもありません。郷 の皆に良いおみやげができました」
花夜の言葉に藤の女神は笑 みを深くする。
「その花にはまだ名がありません。よろしければ、あなたが名付け親になってあげてくれませんか?」
「え!?私が!?そんな……、よろしいのですか?」
「ええ。あなたなら良い名を付けてくれるでしょうから、きっとあの霊 も喜びます。それと、木霊たちとは別に、私からもぜひお礼をさせて欲しいのですが、何か望みはありますか?」
女神の問いに花夜はしばし考え込んだ。女神に望みを叶えてもらう機会など、一生に一度巡 ってくるかどうかも分からないものだというのに、花夜が選んだのは、あまりにもささやかな望みだった。
「では、私の故郷 ・花蘇利国 の今の様子を確認していただくことはできますか?」
俺は思わず花夜の衣袖 を引き、囁 いていた。
「お前、いくら何でも欲が無さ過ぎるだろう。もう少し、じっくりと考えたらどうだ?」
「でも私が今一番気にかけているのは花蘇利のことですし、それに……」
花夜は一旦 言葉を切って俺を見た。
「今までで一番叶えたかった望みがこうして叶っている以上、他の望みなどそうそう思いつきません」
その笑顔に無性 に気恥ずかしさを覚え、俺は知らずそっぽを向く。
「では、花蘇利の国内に立つ藤の木の木霊 たちに、巫女姫の故郷の今の様子を訊 いてみましょう」
藤の女神はそう言うと、髪から藤の花のかんざしを一つ引き抜き、耳へと押し当てた。しばらくの間、声無き声で遠く離れた木霊たちと話をしていたようだが、その顔は次第 に険 しいものへと変わっていった。
息を詰 めて見守っていた花夜に向き直り、女神は悲痛な顔で告げた。
「巫女姫、あなたの国には今、他国の兵士が数多く入り込んでいるそうです」
「え……」
花夜は一瞬呆 けたような顔をした後、すぐに青ざめ、悲鳴を上げた。
「花夜!」
崩れそうになる身体をとっさに支えると、花夜は震 える腕 で俺にしがみついてきた。
「そんな、まさか……こんなに急に……。よりにもよって、私のいない、こんな時に……っ」
「心当たりがあるのか、花夜!」
うわ言のように呟 く花夜に問うと、花夜は泣きそうな顔で頷 いた。
「心当たりは一つしかありません。ずっと、花蘇利を属国にしようと狙ってきた大国、そして直路 の地 をこんな風にしてしまった国……『水響 む霧狭司国 』……」
その名に、再び俺の脳裏 に過去の光景があふれかえる。過ぎ去りしあの日、俺のいた国を襲ったのも、そして俺の大事な人間を死へと追いやったのも、霧狭司国 だった。
水響 む霧狭司国 ――風火水土のうちの一柱、水神 を鎮守神 に持つこの大国は、己の勢力をより強大強固なものとするため、周りの小国を次々と攻め滅ぼしてきた。
「早く……、早く戻らなければ……皆がっ」
「ああ、そうだな。すぐに行こう。花蘇利国 へ」
嫌な予感に胸を塞 がれながらも俺は言った。できることならば、そんな危険な地へ花夜を戻らせたくはなかった。だが決して彼女を止められないことも分かっていた。たとえ死の危険を伴 おうとも、最期 まで国を守るのが、社首――国の神社を統 べる長 たる者の役目なのだ。
「お気をつけ下さい。花蘇利国には兵士だけでなく、霊力の強い巫女も来ているようです」
藤の女神の忠告に、俺はただ黙して頷 いた。
我に返った花夜が心配そうに顔を
「あの……っ、あなた様のお気持ちを
「気にしてはおらんから、謝る必要はない。俺を止めたお前の判断は間違ってはおらん。まさか天探女を出してくるとは思わなかったが」
人心を
「世の中の物事には、どんなものであれ存在する意味があるのだと、母が申しておりました。ですから……きゃっ!?」
花夜の言葉は彼女自身の悲鳴によって
目を移せば、俺達はいつの間にか人ならざるモノたちに囲まれていた。緑の髪に花や果実をからませた彼らは、こちらをじっと見つめ、何事かを口にする。だがその唇から
「……ヤト様っ」
花夜がおびえたように俺の
「お守り下さり、心より感謝申し上げます。蛇の姿を持つ神、そしてその巫女姫」
光の中から現れたのは、一柱の女神。白藤を思わせる純白の髪に藤紫の瞳、肩にまとった花の
「藤の木の女神様……。無事にお生まれになったのですね……」
女神の姿にうっとり
「この
「そうでしたか。ありがとうございます」
花夜が両手を差し出すと、
「これは
木霊たちの
やがて最後に、ひどくおずおずと
「あの……彼女は何と言っているのでしょうか?」
「それは花の種だそうです」
他の木霊の
「何の役にも立たないかも知れませんが、今の自分に用意できるのはその種だけですから、ぜひ持っていって欲しい、と言っています」
「役に立たないなんて、とんでもありません。
花夜の言葉に藤の女神は
「その花にはまだ名がありません。よろしければ、あなたが名付け親になってあげてくれませんか?」
「え!?私が!?そんな……、よろしいのですか?」
「ええ。あなたなら良い名を付けてくれるでしょうから、きっとあの
女神の問いに花夜はしばし考え込んだ。女神に望みを叶えてもらう機会など、一生に一度
「では、私の
俺は思わず花夜の
「お前、いくら何でも欲が無さ過ぎるだろう。もう少し、じっくりと考えたらどうだ?」
「でも私が今一番気にかけているのは花蘇利のことですし、それに……」
花夜は
「今までで一番叶えたかった望みがこうして叶っている以上、他の望みなどそうそう思いつきません」
その笑顔に
「では、花蘇利の国内に立つ藤の木の
藤の女神はそう言うと、髪から藤の花のかんざしを一つ引き抜き、耳へと押し当てた。しばらくの間、声無き声で遠く離れた木霊たちと話をしていたようだが、その顔は
息を
「巫女姫、あなたの国には今、他国の兵士が数多く入り込んでいるそうです」
「え……」
花夜は一瞬
「花夜!」
崩れそうになる身体をとっさに支えると、花夜は
「そんな、まさか……こんなに急に……。よりにもよって、私のいない、こんな時に……っ」
「心当たりがあるのか、花夜!」
うわ言のように
「心当たりは一つしかありません。ずっと、花蘇利を属国にしようと狙ってきた大国、そして
その名に、再び俺の
「早く……、早く戻らなければ……皆がっ」
「ああ、そうだな。すぐに行こう。
嫌な予感に胸を
「お気をつけ下さい。花蘇利国には兵士だけでなく、霊力の強い巫女も来ているようです」
藤の女神の忠告に、俺はただ黙して