- 葉桜【はざくら】
- 花が散り、若葉が出始めた頃のサクラのこと。
- 葉桜【はざくら】※合色目
- 合色目のひとつ。主に春に用いられた。
表が萌黄、裏に二藍(藍染の上に「呉の藍(=くれない。紅花の赤)」を重ね染めしたもの)を組み合わせたもの。
- 花曇【はなぐもり】
- サクラの花が咲く頃の曇り空。
サクラが咲く頃は天気が変化しやすく、よく晴れていると思っても、すぐに薄雲が現れて曇ってしまうことがある。
- 花曇の雨【はなぐもりのあめ】
- サクラの花が咲く頃に降る雨のこと。「桜雨」とも言う。
- 花染【はなぞめ】
- サクラの花の色に美しく染めること。また、その染めた色のこと。
(露草の花で染めることを言うこともある。)
この「花染」で染めた衣は「花染衣」あるいは「花の衣」などと呼ぶ。
- 花疲れ【はなづかれ】
- 花見に出歩いて疲れてしまうこと。
- 花冷え【はなびえ】
- サクラの花が咲く頃に寒さが戻って思わぬ冷え込みがあること。
- 花芽【はなめ】
- やがてサクラの花になる芽のこと。
6〜7月頃形成され、10月頃に越冬のための休眠に入り「冬芽」となる。
休眠からの目覚めには冬の寒さが必要で、1月中・下旬頃10℃以下の低温にさらされると休眠から目覚め、水分と気温の上昇があればいつでも咲ける花芽(蕾)となる。
- 朱桜【ははか】
- ウワズミザクラの古名。
あるいはカバノキの総称とも言われる。
占合などに用いた。
- 半八重咲き
- サクラの花の形で、花弁の数が7〜10枚の花。
この咲き方のサクラの種類は極めて少ない。
- 一重咲き
- サクラの最も基本的な花の形で、花弁が五枚。
この咲き方がサクラの種類の過半数を占める。
- フィオーレ・ディ・シリエージョ/フィオーレ・ディ・チリエージョ
【fiore di ciliegio】
- イタリア語でサクラ(の花)のこと。
- フィンガープリント法
- ソメイヨシノのクローン性の研究として初期に用いられていた方法。
現在用いられているものほど精度は高くない。
- 福禄寿【ふくろくじゅ】
- サトザクラ系のサクラの品種のひとつ。
淡紅色で花弁の縁が濃紅色をした八重咲きの花をつける。
- 普賢象【ふげんぞう】
- サクラの品種のひとつ。
大輪の八重咲きで淡紅色の花をつける。
実をつけないサクラ。
- 不断桜【ふだんざくら】
- ヤマザクラ系のサクラの品種。一年に二度、秋と春に咲くサクラ。
一重で小輪の白色の花を咲かせる。
原木は三重県鈴鹿市白子町にあり、10月頃から春まで咲き続けるというが、八王子市の多摩森林科学園の桜保存林にあるものは10月上旬〜12月下旬と、3月上旬〜4月中旬の2度咲くといわれている。
- 冬桜【ふゆざくら】

一年に2度、秋と春に花を咲かせる「小葉桜」のこと。
- フルール・ド・スリジェ【fleurs de cerisier】
- フランス語でサクラ(の花)のこと。
- フロル・デ・セレジェイラ【flor de cerejeira】
- ポルトガル語でサクラ(の花)のこと。
- ベニヤマザクラ
- ヤマザクラの一種。
中部以北から北海道にかけて分布する。
|
|
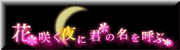 の
の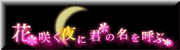 の
の