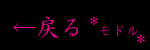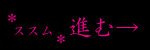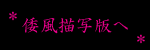それからしばらくのことは、自分でも何をしていたのかよく覚えていない。喪失の痛みを
埋めることもできぬまま、ただ、あてもなくあちこちを
彷徨っていた。
時折は知人に会うこともあったが、皆、俺の死んだような瞳を見ると困惑したように口を
噤み、言葉
少なに去っていく。だが、
彼の女神だけは違っていた。
「お久しぶりですわね。今は『
夜刀神』と名乗っているのですって?」
髪や瞳の色を変え、
人間のふりをして訪れた
峠の茶店。そこで
偶然再会した
彼の女神は、そう言って
妖艶に微笑んだ。
「
天探女か。
何故このような場所にいる?」
「
相変わらず失礼な神ですこと。私が
何処にいようと私の勝手ではなくて?」
俺のあからさまに邪険な態度に眉をひそめながらも、
天探女は勝手に俺の隣に腰掛け、茶飲み話を始める。
「私もあなたと同じですのよ。これまで
契りを
交わしていた
男巫が
逝ってしまったものですから、あてのない旅をしている最中ですの。
人間に化けてあちこちの国をのぞいて、新しい
巫でも探そうと思っていますのよ」
「……新しい
巫、か。よくもまあ、そう
容易く切り替えられるものだな。その死した
男巫に対して情は無いのか」
「情なら彼が生きているうちに、たっぷりかけてあげましたわ。ですから死した後に
悔いや未練を残したりはしませんの。だいたい、私が薄情なのではなくて、あなたが情に厚過ぎるのですわ。百年余りもの間、たった一人の巫女に縛られて……。おまけにその名も、巫女の名から一字を取っているのですって?よくもまぁ、そこまで
人間に思い入れられるものですわ。今もこれからその巫女に会いに行くところなのでしょう?」

「会いに行く……?」
問いの意味をつかめず
訊き返すと、
天探女はきょとんと目を
見開いた。
「あら、違いますの?あなたの巫女が眠っているのはこの近くの山の中なのではなくて?あなたの
慟哭がそれはそれは激しく長く響き渡っていたせいで、この辺りの神々や
木霊達には有名な場所ですのに」
「……そうか。ここはあの場所の近くなのか」
花夜を
喪って以来、俺はあの花園に一度も足を踏み入れていなかった。この時、いつの間にか花園の近くまで来ていたことも、天探女に言われて初めて気がついたほどだった。
「
呆れたものですわ。それほど大切にしている巫女の元へ、一度も足を運んでいないだなんて。そんなに、思い出すのが
辛いんですの?」
俺は答えず、無言で茶をすする。天探女は
大袈裟なため息をついた。
「とにかく、一度くらいは会いに行っておあげなさいな。胸の傷が痛むからと言って、あんな人も訪れないような寂しい場所に
葬ったまま、会いにも行ってあげないようでは、あの巫女も
哀しみますわよ」
花夜が哀しむというその一言が、俺の胸に突き
刺さった。
こうして俺はあの日以来、初めてあの花園に足を踏み入れることとなった。
季節は春。
崖の上にある花園からは美しい花びらがひろひろと、空を舞う
蝶のように風に運ばれて来る。
俺はそれを見るともなしに
眺めながら、なかなか花園へ入るふんぎりがつけられずにいた。あの場所に再び立てば、あの日の悲しみが生々しく
蘇ってくるような気がして、恐ろしかった。
だがその時、そんな俺の
逡巡を吹き飛ばすかのように、幼い声が響いた。
「たす……けて……っ。だれかっ……!」
ぎょっとして見上げると、花園へと
至る崖の途中、年の頃八つか九つほどの
童女が一人、岩にしがみつくようにしてぶら下がっていた。
「何をやっているのだ!」
俺はすぐさま崖を登り、童女を助ける。俺に
抱えられて崖を下りた童女は、深々と頭を下げて礼を言ってきた。
「どうもありがとう、お兄さん」
「お前、
何故あんな場所にいた。落ちたらただでは
済まん所だったぞ」
「あの……。この崖の上から、毎年すごくきれいな花びらが飛んで来るんです。だから、どんな花なのかどうしても気になって、
確かめてみたくなって……」
「それで崖を登る途中、足を踏み
外してぶら下がっていたということか。そうまでして見てみたいほど綺麗な花びらなのか」
「はいっ!まるでお空を
転がっているみたいにひらひらしてて、その裏に表に風にひるがえる様子が、まるでお日様を
浴びてきらきら
瞬いているみたいに見えて……まるで冷たくない雪みたいで、見ていると心がふわぁーっとあたたかくなるんです。すごく、幸せな気持ちになるんです!」
瞳を輝かせて言う童女に、俺は気まぐれに問いかけた。
「ならば、見せてやろうか」
「え……?」
「俺が崖の上まで連れて行ってやろう。どうだ?行ってみたくはないか?」
今にして思えば、
独りで立ち入るのが
辛いこの場所に、誰か一人でも別の人間がいれば気が
紛れると、そういう気持ちがあったのかも知れない。
「はいっ!」
童女は満面の笑みで
頷く。俺はその
幼子を背負って崖を登り、百数十年ぶりに花園へと足を踏み入れた。
「うわぁー……。すごい!やっぱり、きれい!こんな花、見たことない!」
童女は歓声を上げ、花園を走り回る。俺は呆然とその光景に見入った。
崖を登りきった
途端目に飛び込んできたのは、
丈の低い花々の中にあって一本だけ、高く
天へと伸びた花の木だった。
ちょうど花夜の身を埋めた辺りに、
墓標のように立つその花は、俺にとってあまりにも
見覚えのあるものだった。
「この花、何という名前の花なんでしょう。お兄さんは知っていますか?この花の名前を」
無邪気な声に、俺は
呆けたまま答えを返す。
「この花は、
幸有の花。誰かの幸せを
祈がう
人間の優しさを
糧として育ち、見る者全てに幸を与えてくれる花だ」
童女はきょとんとした顔で俺を見上げ、舌足らずな声で花の名を繰り返す。
「さく…ら……?」
薄紅色の淡い花びらが、雪のように
降り
注ぐ。
名付けた者の
祈がいをそのまま表したかのような、あたたかく、優しい花びらだ。その
花吹雪に包まれて、俺は、
視えない誰かの腕にあたたかく抱きしめられているかのような
錯覚を
覚えた。
「あれ?お兄さん、どうしたの?」
泣きそうで泣けない俺の顔を、童女が不思議そうに
覗き込む。俺は答えず、花を見上げたまま童女に問いかけた。
「お前、この花が好きか?」
「え?はい。好きです。すごく、きれいだから」
「ならばお前に、この花の種をやろう。今は持っていないが、俺は毎年必ずここへ来ることにするから、その時にでも……」

――私、この花がこの世界を
埋め
尽くす
様を見てみたいです。
誰かに
幸く
有るようにと
祈がいを
籠めて名付けたこの花が、その名の通りに誰かに幸せをもたらしながら、この世界に広がっていく様子が……。
いつかの花夜の言葉が、胸の中で蘇る。
「広めてくれ、この花を。いつかこの世界を、この優しい花で埋め尽くせるように……」