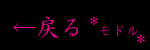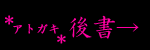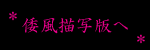| 結 花咲く夜に君の名を呼ぶ |
長い長い追想から還り、俺は空を見上げた。いつの間 にか雨は止 み、雲間 からは下弦 の月が覗 いている。二十三夜の、月待 の月だ。
いつしか『さくら』と呼ばれるようになった花は、俺の頭上で月光に照らされ、花びら一枚一枚に灯 を点 したかのように淡く輝いている。
俺はあれからずっと、この花の種を蒔 き続けている。あれからさらに何百もの年が過ぎ、気づけば花は国中に広まっていた。
病気に負け、害虫に負け、何百という木が駄目 になったことがあった。木材や薪 として、何百という木が伐 り倒されたこともあった。だがいつの時代にも、不思議とこの花に深く魅 せられる者が現れ、脈々と花の系譜 を繋 いでいく。
いつしか花は人々に愛され、国の境 も海峡 も越えて広まった。
そして今や春となれば、至 る所に薄紅 の花の海が生まれる。人々は花に引き寄せられたかのように木の下に集まり、心和 んだような笑 みを浮かべる。
きっと、これで良かったのだろう。その本当の名や意味は忘れられても、この花を見た人々が、ほんの束 の間 でも世の辛 さや哀しみを忘れ、幸せな気持ちや、優しい気持ちになれるなら……君はそれで充分だと言って微笑 ってくれるだろう?花夜 ……。
答えの返ることのない呼びかけを再び心の中で囁 き、さくらの木を見上げる。そこで俺はふと違和感を覚 えた。
さくらの花は相変 わらず、その花びらに淡い輝きを点 している。だが、それが月光に照らされているせいだけではないことに、俺はようやく気がついた。
「これは……祈魂 ?」
それはいつか花夜と見たのと同じ光景だった。花の周り、青闇 に包まれた空 に、蛍火のような光を放 ちながら漂 うものがある。
それは、さくらを愛する人々の想いが形を成 したもの。――さくらに寄せる人々の想いが、今この木に新たな神を降臨させようとしている。
俺は息をつめてその様を見守った。祈魂 の光は徐々 に一箇所 に集まり、人の形を成していく。優美に広がる長い裳裾 に、それが女神であることが分かる。肩にはさくらの花をつなぎ合わせたような形の領巾 が、髪には枝垂 ざくらの花簪 が揺 れる。まだ大人になりきれていないような、華奢 で未成熟な印象を与える女神だ。その姿が鮮明になるにつれ、俺の胸は奇妙な既視感 にざわめきだした。
目の前で、光が弾 ける。さくらの香りが一段と濃 くなった。白に、黄金に、虹の七色……ありとあらゆる色彩を凝縮 したようなその光の後に現れたのは、どこか頬 にあどけなさを残す、一柱 の姫神。
「あなたは……龍神?何故 、ここに……?」
女神は目の前に立つ俺を見つめ、不思議そうに両眼を瞬 かせる。小さな唇から零 れたのは、俺のことがまるで分からぬというような、疑問を宿した声だった。だが、それは記憶の中のものとまるで変わらない、懐 かしい声音 をしていた。
俺はすぐには返事ができなかった。胸がつまって、上手 く言葉が出て来ない。いつかの問いの答え――神や精霊の魂 が何処 から巡 り来るのかを、俺は今、初めて知った。
枯 れたはずの涙 が頬を伝 う。それを拭 うこともしないまま、俺は微笑み、名を呼ぶ。もう幾百年もの間、呼びかけても答えの返ることのなかった君の名を。
きっと君は、全てを忘れてしまっているから、今度は俺が教えてあげよう。春には花かんむり、夏には川辺の木陰 、秋には黄葉 、冬には満天の星……君と共に見た景色、君が教えてくれた全てのことを。
君の生まれたこの世界は、とても美しいところだから。
いつしか『さくら』と呼ばれるようになった花は、俺の頭上で月光に照らされ、花びら一枚一枚に
俺はあれからずっと、この花の種を
病気に負け、害虫に負け、何百という木が
いつしか花は人々に愛され、国の
そして今や春となれば、
きっと、これで良かったのだろう。その本当の名や意味は忘れられても、この花を見た人々が、ほんの
答えの返ることのない呼びかけを再び心の中で
さくらの花は
「これは……
それはいつか花夜と見たのと同じ光景だった。花の周り、
それは、さくらを愛する人々の想いが形を
俺は息をつめてその様を見守った。
目の前で、光が
「あなたは……龍神?
女神は目の前に立つ俺を見つめ、不思議そうに両眼を
俺はすぐには返事ができなかった。胸がつまって、
きっと君は、全てを忘れてしまっているから、今度は俺が教えてあげよう。春には花かんむり、夏には川辺の
君の生まれたこの世界は、とても美しいところだから。