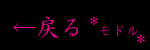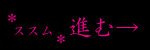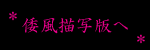屋根はあちこち
破れ、庭園には
泥が
溜まり、すっかり
みすぼらしくなった宮殿に女神を
伴い
降り立つと、すぐに
海石が走り
寄ってきた。
「
泊瀬様!泊瀬様は
御無事ですか!?」
女神の
腕に
抱かれ力無く
瞳を閉じている泊瀬に気づき、海石の顔は
蒼白になる。
「大事無い。気を失っておるだけだ」
「
鎮守神様……。元の御姿に戻られたのですね……」
女神の言葉に海石は
安堵の息をつき、視線を俺達の方に移した。
「花夜姫!
大丈夫なのですか?お顔の色が
優れませんわ」
「大丈夫です。……少し、
疲れてしまっただけです。それよりも海石姫。何だか、宮殿内の
雰囲気が
不穏な気がするのですが……」
俺の背から
降りようとする花夜に手を差し
伸べながら、海石はその頬に
皮肉な笑みを浮かべた。
「……ええ。嵐が
鎮まった後、この
騒ぎの原因を求めて多くの人が集まって来たのですわ。
葦立氏の
企みは今や宮殿中の知るところとなり、皆がその罪を
糾弾しているところですの」
海石の言う通り、そこには俺達が飛び立つ前にはいなかった多くの人々が集まっていた。葦立氏はその中で一箇所に集められ、周りを他の氏族に囲まれてうなだれている。宮殿には彼らを
非難し、
侮蔑し、
罵倒する声が満ちていた。
女神はその様子に一瞬
眉を
曇らせたが、すぐに
毅然とした顔で泊瀬を抱いたまま
歩を進める。
人々は女神に気づくと
一斉に
口唇を閉ざし、その場に
平伏していった。
「……
皆の者、迷惑をかけたな。
謝って
済むこととも思えぬが、せめて
謝罪をさせてくれ」
女神が謝罪の言葉を口にすると、人々の間から
恐縮するような声が上がった。
「もったいないことでございます!そもそもこの
度の
騒ぎは、葦立氏が
泊瀬王子を
弑し
奉ろうとしたことが
発端。鎮守神様の罪ではございません!全ての
咎は葦立氏にあります。鎮守神様、どうかこの
者共に
罰をお与え下さい!」
人々は口々に葦立氏への
断罪を求める。女神は再び
哀しげに眉を曇らせた。
「……相変わらず
醜いものだ。何か事が起これば
嬉々として
互いを断罪し合う。この宮殿の者共は全く、哀しいくらいに何も変わらんものだな。……ここにいるのは皆、大なり小なり何らかの罪を
犯してきた者ばかりだろうに」
皆一様にうなだれ、身を
縮めている葦立氏の中にあって、
雲梯だけは己の状況も周囲の声も
我関せずとばかりに笑う。その態度に周りを囲む男の一人が
苛立ったように声を上げた。
「雲梯様。あなたはもう少し、今の御自身の置かれている立場をお考えになった方がよろしいかと
存じますが。王太子と言えど、
泊瀬王子弑逆の
企てに
加担なされた罪は重大ですぞ」
だが雲梯は
怯むこともなく余裕に
満ちた表情で言い返す。
「お前達の方こそ、もう少し考えて物を言った方が良いぞ。先ほどの私の言葉が
偽りでないことは鎮守神様も
既に
御存知だ。お前達の犯した“罪”は私の血を通して既に鎮守神様の知るところとなっているのだからな」
その言葉に、ざわめいていた室内が再び一瞬にして静まりかえる。雲梯は女神に目を向け、大国の王太子にふさわしい優雅な
笑みで問う。
「さて、鎮守神様。我らへの罰はどのようなものになるのでしょうか?心優しきあなた様のこと、他の一族の罪も知りながら、我らだけを
罰するような不公平なことはなさりますまい」
女神はわずかに目を
逸らし、そっと
溜め息を
零した。
「……
妾は初めからお前達を罰する気など無い。
人間の罪は人の間で
裁くべきものと思っておるからな。いかなる罰を与えるかは、皆でよく話し合って決めるが良い。……必ず泊瀬を
交えて、な」
淡々と語るその声には、女神の
憂いの心がにじみ出ているかのようだった。
海石に
肩を
支えられた
花夜が
気遣わしげに見つめると、その視線に気づいた女神が
苦く
微笑む。
「心配するな。少々気の
滅入るような状況ではあるが、このようなことで
荒魂になったりはせん。もう泊瀬にあのようなことはさせられんからな」
他の者達に聞こえぬようひそりと
囁いて、女神は
腕の中で眠る泊瀬の
髪をそっと
梳く。それはまるで母が赤子に
触れるかのような、心から愛しいものに触れているのだと
傍目にも分かる、優しく
慈愛に満ちた手つきだった。
その様子を、
食い
入るように――どこか
狂おしいまでの
眼差しで見つめる者があった。
執拗なその視線の
主は……
魂依姫・
雲箇。
髪は
乱れ、
衣裳は
汚れ、かつての
凛とした姿が
嘘のようにみじめな姿で葦立氏の中に座らされていた彼女は、
突然ふらりと立ち上がった。

「……
鎮守神様。あなた様にとってその
王子は、一体何なのですか?」
そのままふらふらと女神に
歩み寄ろうとする彼女を、
皆が制止しようとする。だが
雲箇が小さく
祈道の
詞を
呟くと、肩に羽織った
領巾がふわりと揺れ、止めに入った人間の
ことごとくを風の霊力で
薙ぎ倒した。同時に雲箇の手を
縛めていた縄も鋭い風の刃に断ち切られてぱらりと地に落ちる。
「
魂依姫を捕らえておきながら、
神宝を取り上げておかなかったのですか!?」
海石が
眦を
吊り上げ、
葦立氏を取り囲んでいた人々へ向け非難の声を上げる。
「そうは言われても、実際に
御神宝を目にしたことのない我らには、どれが御神宝でどれがそうでないのかなど、分からんのだ……」
巫であれば特別な霊力の宿った神宝を見分けることなど
造作も無いことだ。だがそもそも霊力を感じ取る能力を持たぬ俗人から見れば、それは単なる
領巾としか思われなかったのだろう。
致命的な失敗に、海石は
苦々しげに
唇を
噛みしめた。
「……
花夜姫、申し
訳ありませんが、しばらくここで
我慢していてくださいませ」
一言
謝り、花夜の身を手近にあった
厨子にもたせかけると、海石は
覚悟を決めたような表情で雲箇の前に立ちはだかった。
「止まりなさい!
葦立雲箇!仮にも
魂依姫であるあなたが鎮守神様に
刃向かうなど、
許されることではありませんわ!」
「“
魂依姫”……。そうです。私は魂依姫。この国の
筆頭巫女なのです……」
雲箇の瞳は海石を映しているようで、まるで映していない。その目はただひたすらに女神へと向けられていた。
「鎮守神様。
何故私に目を向けてくださらないのですか?私は魂依姫。あなた様の筆頭巫女です。あなた様にとって、この国で一番大切な人物は、その
王子などではなく、この私ではないのですか?何故、私の鎮魂の祈りを聞き届けてくださらなかったのですか?何故、私を見てすらいただけないのですか?」
そこにあったのは悲しみでも
嘆きでもなく、ただ純粋な疑問の声だけだった。彼女は
未だ
己の立場を、己の
所業を、疑ってすらいないのだ。
「あなた様にお
仕えするためだけに、長年
尽くして
参りましたのに。この地位に
昇りつめるために、多くの
犠牲を払って参りましたのに……。その
王子が、あなた様の御心を
惑わせたのですか?その
王子さえいなくなれば、私に目を向けていただけるのですか?」
言いながら、雲箇は
懐に手を差し入れ、何かを取り出す。それは、
別宮の古墳の中で海石が落とした短剣だった。
「海石姫!」
花夜が悲鳴のように名を呼ぶ。海石は青ざめながらもその場を
退かない。
「
葦立雲箇!自分が何をしようとしているか、分かっているのですか!?」
「何ですか、その目は。私が正気ではないとでも言いたげですね。私はもちろん正気です。鎮守神様があのような、
宮処で
騒動を起こすしか能のない
王子に御目をかけられるはずがありません。鎮守神様はきっと、何かおかしな霊力で
惑わされているのです。あの
王子さえいなくなれば、御目を
覚まして頂けるはずです」
「あなたはまだ己の
過ちに気がつかないのですか!?あなたのその地位は、あなた自身の努力や
犠牲ではなく、他人の犠牲や涙の上に成り立ったもの。そのようなものに意味があるとでも思うのですか!?」
亡き親友を想ってか、雲箇をなじる海石の目には涙がにじんでいた。だが雲箇は己がなぜ責められているのか分からないとでも言いたげに
眉をひそめた。
「何人もの人間で地位を
競い合えば、
敗れていく人間がいるのは当然のことではありませんか。力無きものが敗れるは世の
摂理。そうして敗れた人間が泣こうが命を落とそうが、
自業自得。私には関係の無いことです。生き残りたければ、どのような手段を使ってでも力を手に入れれば良いだけの話ではありませんか」
そもそもの物の考え方があまりにも
違い過ぎる相手に、こちらの常識や
道理をただ
説いて聞かせたところで通じはしない。――言葉の通じない相手というものは世の中に必ずいるものだ。そしてそれに気づかされた時、ほとんどの人間は、理解されるための努力や
工夫をしようと考えるより先に、絶望や
焦燥に目が
眩んで何も考えられなくなるものらしい。
海石もまた
呆然と目を
見開き、しばし言葉を失った。やがてその口元に、ひきつった
笑みが浮かぶ。
「……話になりませんわね。あなたにはきっと一生分かりませんわ。
何故あなたでなく、
泊瀬様が鎮守神様のご
寵愛を
得たのかなど……」
その皮肉を
帯びた
眼差しに、雲箇の
眉がぴくりと上がる。
「何ですか、その顔は。私がそこの
王子より
劣っているとでも言う気ですか。……そう言えば、あなたはそこの
王子付きの
宮女でしたね。あなたもそこの
王子と
共謀し、鎮守神様を惑わせていたのでしょう。ならば今この場で、魂依姫たる私がその罪を
裁いて差し上げます!」
言うなり、雲箇は短剣を振り回し海石に
踊りかかる。海石は悲鳴を上げ、
間一髪で
刃を
避けた。
「
止めよ!
葦立雲箇!
妾は惑わされてなどおらん!」
「いけません、鎮守神様!雲箇はあなた様のお言葉さえ耳に入る状態ではありませんわ!
泊瀬様と共にお
逃げくださ……」
海石が思わず
背後を振り返り、女神へ向けて
叫んだその時、再び雲箇が短剣を
構え飛び出してきた。だが海石は
反応が
遅れ、すぐには動けない。
避けられぬ
刃がその身に
突き立つかと思われた瞬間――二人の間に割り込んだ影があった。
「御二人とも、おやめくだ…………ッ」
制止の声は
途切れ、意味を
成さない悲鳴に変わる。胸に
刃を受け
床に
倒れるその人影を、俺は信じられない思いで見つめた。
呆然と、ただ立ち
尽くすばかりだった自分のうかつさを、俺は
呪った。
彼女がこんな場面を
黙って見ていられるはずなどなかったのに……。
ただ
成り
行きを見つめるだけだった俺のそばで、彼女は自分の
為すべきことを
逸早く
悟り、ほとんど体力の残っていない
身体を強引に動かしてまで行動を
起こしてしまっていたのだ。
「……花夜!」
名を
叫び、
駆け寄る。花夜は苦痛に
潤む
瞳で俺を見上げてくる。その
衣にはじわじわと血の
染みが広がりだしていた。
「……
何故です?何故、自分と関係の無い人間を救うために身を投げ出すのです?それが一体何になると言うのです……?」
混乱と
動揺に
震える雲箇の
呟きが背後に聞こえる。
「世の中にはそういう人間もいるということだ。そなたの知るものだけがこの世界の全てではない。自分に
都合の良い真実ばかりを受け入れて、それをこの世界の真理だと思い込もうとしたところで、世の中はいとも簡単に“それ”とはまるで
違う
理で動いていったりするものだ。……我々は鳥や
獣と違って、なまじ心が
発達しているがゆえに、弱肉強食の
摂理だけでは生きていけない。強さや力が求められる世の中であっても、どこかで心を求めてしまう
生物なのだ。そなたが弱さや
偽善と
吐き捨てて持とうとしなかったものを、この姫や泊瀬は
確かに持っているし、それゆえそなたは鎮守神様に御目をかけられることはなかった。そなたがいくら否定しようと
足掻いたところで、その真実は変えられない。……一族の
思惑により
意図的に心を封じられ、情を
奪われてきたそなたにとっては
酷なことであろうがな……」
雲梯が雲箇へ向け
憐れむように、だがそれでいてどこか
突き
放すような
口調で
何事か語りかけていたが、その時の俺にはどうでも良いことだった。
「花夜姫!」
海石が涙目で花夜の
傍らに
膝をつき、胸に
沈む短剣を引き抜こうと手を
伸ばす。だがすぐに女神に止められた。
「待て!うかつにそれを
抜いてはならん。
下手をすれば血が
噴き出して、すぐに死に
至ってしまうぞ」
女神は泊瀬の身を海石に
預け、花夜の傷口に手を当てた。女神の霊力が土に
染み
込む水のように、花夜の身に
注がれていく。花夜の顔から
徐々に苦痛の色が消えていくのを見て、俺はほっと息をついた。
流血が止まったのを
見計らい短剣を引き抜いた女神に、俺は感謝の言葉を
述べようと口を
開く。だが、女神の浮かべる表情に気づき、その言葉を発することができなくなった。
「……すまん。
妾にできるのはここまでだ」
沈痛な
面持ちで
俯く女神に、俺は
上手く回らぬ頭で問いかける。
「何を言われるのだ?傷は
癒えたのではないのか?あなたの御霊力で」
だが女神は首を横に振る。
「
妾は水を
司る神。妾にできるのは、血を止め、傷口を
塞ぎ、体の中の水の流れを
操って苦痛を感じないようにすることだけだ。ここまで傷ついてしまった臓器を修復する能力は持っておらん。花夜姫の命は、あと半日と
保たずに
尽きるだろう。……妾には
最早どうすることもできん」
「どうすることもできぬ、だと?何か手は無いのか!花夜は
霧狭司国の民を
庇って倒れたのだぞ!なのに……!」
「……やめて、下さい、ヤト様。それより……ここへ来て、手を
握って下さい」
思わず
激昂する俺に、弱々しく花夜が
哀願する。その声に俺はハッと我に返る。他人を
責めているような場合ではないと気づき、すぐに花夜の顔を
覗き
込んでその手を
握った。
「花夜、花夜……っ。苦しくはないか?何か、して欲しいことはないか?」
「……苦しくは、ありません。ただ……何だか、ひどく
怠いような、眠たいような気がして……目を開けているのが
辛い、です……」
途切れ途切れにそう言った後、花夜はひどく
切実な眼差しで俺を見つめた。
「ヤト様……、私を……どこか静かな場所へ、連れて行ってもらえませんか?……どこか、きれいで……二人きりになれる場所へ」
そのささやかな
祈言を、俺は何も言えぬまま受け入れた。どうにもならぬ
喪失の予感から、必死に目を
逸らしながら……。