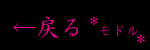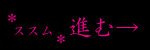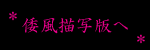| 第十一章 追憶に沈む大刀 |
かつての俺は神ではなく、大刀 に宿る精霊 に過ぎなかった。
物にも魂 は宿 る。作り手の祈 がい、使い手の祈 がい、その物に対する感謝の気持ちや様々な想 い……そういった小さな祈魂 が徐々 に積もり積もっていき、やがてその物に魂 を降臨 させる。
神とはほど遠いちっぽけな魂 で、霊力のある人間の目にしか映らぬものだが、それでも心を持ち、確かに存在しているのだ。
だが俺の魂 は他の精霊とは違い、禍々 しく歪 んでいた。
“大刀 ”とはその名の通り、人間の肉体 を『断 ち』切るための道具だ。そんな“大刀”に寄せられる想いは、決して綺麗 な祈 りばかりではない。
大刀を持つ側の凶暴なまでの闘争心 や野望 、斬 りつけられた側の怨 みや憎 しみが、いつしかどす黒い負 の念の塊 となって俺の魂 を侵食 し、禍々 しく歪 めていった。そしてその歪んだ魂が持ち手にまで影響を及 ぼすようになった頃 、俺は持つ者を不幸に陥 れる“凶刀”と呼ばれるようになっていた。
事実、俺の主 となった者たちは俺の歪 んだ魂に呼び寄せられた災厄 により、次々と悲惨 な死を遂 げていった。そんな俺を手にしたがる者はおのずといなくなり、俺は度重 なる戦で刀身が傷 んだのを機 に、荒れ果てた魚眼潟国 の森の中に置き捨てられた。
それから何年もの時が過ぎ、このまま誰 からも忘れ去られ静かに朽 ちていくのだろうと、俺自身も思っていた。そこに、あの若者が現れた。
物にも
神とはほど遠いちっぽけな
だが俺の
“
大刀を持つ側の凶暴なまでの
事実、俺の
それから何年もの時が過ぎ、このまま
「やっと見つけた。そなたか。主を殺 める凶刀と言うのは」
地を覆 い隠 すように生 い茂 る草を踏 み分け俺を拾い上げたその若者は、まだ子どもと言って良い年頃 に見えた。
衣 や顔をわざと泥 でよごし、背に草木の葉の入った竹籠 を負 ったその姿は、一見、杣人 の子か何処 かの邑 の農夫の子のようにしか見えなかった。
『童 が我に何の用だ。去 れ。軽い気持ちで我を手にすれば痛い目を見るぞ』
言っても聴 こえぬだろうと思いながらも、俺は声無き声で警告を発した。
今まで俺を手にしたどんな人間も、俺の声を聴くどころか、俺の存在に気づくことすらなかった。また今度も意に反して戦場に連れ出され、血を浴びることになるのだろうと、半 ば諦 めの境地で俺は彼の行動を待っていた。だが彼はさも当然のように、さらりと俺の“声”に言葉を返してきた。
「やはり、魂 の宿る大刀 であったか。なるほど、ひどく傷 んではいるが、精霊が降 りるにふさわしい見事な大刀だ。もっともその魂も、数多 の血に染 まり歪 んでいるようだがな」
彼は俺を手に取ると、目の高さに掲 げ持ち、魂 の奥底まで覗 き込むかのような眼差しで見つめてきた。どこにでもありふれたその姿にそぐわず、その言葉や眼差しはまるで神に仕 える巫 のそれだった。
『お前は何者だ。何処 かの国の男巫 か?』
「いいや、私は鍛冶 だ。『青葉 騒 ぐ鯨鯢国 』の鍛冶部にして、技師長・矢筈 の一子 、真大刀 。鉄鉱 の声を聴き、大刀と心を通じ合わせことを生業 としている」
傲慢 にすら見えるほどの誇 りと自信に満ちた声で、彼は名乗りを上げた。野心にぎらついた将の眼や戦に疲れた兵士の顔とはどこか違 うその若々しさが、俺にはひどく眩 しく映った。
「どうだ?私と一緒に来ないか?戦に傷つき、人間 の怨 みの染 みついたその刀身 を、私が打ち直してやろう」
不敵な笑 みをその口元に刷 き、彼はそう誘 いかけてきた。
不思議 な若者だった。声音 や態度は高慢 で不遜 なものにも思えるのに、その瞳はどこまでも真っ直ぐに輝いていた。
俺は心が揺 らぐのを感じていた。だが、彼の言葉をそのまますんなりと受け入れることはできなかった。
『そうして打ち直して、我を再び戦場へと送り出すのか。この身に人間 の血を浴びるのはもうたくさんだ。我はここでひそかに朽 ちていく。放っておいてもらおう』
冷たく突 っぱねたつもりだった。だが彼はその頬 に刻んだ笑みを消すことなく、さらに言葉を掛 けてきた。
「ならば私は、他を滅 ぼすための力でなく、大切な何かを守りきるための力をそなたに授 けよう」
俺には初め、その言葉を信じることができなかった。
『大切な何かを守りきる力?そのような力、あるものか。大刀には所詮 、人間 の肉を断ち命を奪 うことしかできぬ。何かを守るためと言いながらも、結局はそのために人を殺 め血を流すのではないのか』
その言葉に、真大刀 はくすりと笑った。
「違 うな。大刀の役目は人を殺 めることだけではない。真の名刀は人間の肉体ではなく、心を斬 るのだ。相手の戦意を砕 き、降伏させ、そこに存在するというだけで大切なものを守る――それこそが、我ら鍛冶部の目指す究極の大刀作りだ。既 に精霊を宿らせたそなたのような大刀であれば、そんな名刀となれる可能性を充分に秘めている。そなたもせっかくこの世に生まれ出たのだから、血にまみれた記憶しか持たぬまま朽ちていきたくはなかろう?もっと美しい、新たな記憶を共に刻んでいこうではないか」
真大刀はそこで初めて、年相応 の屈託 の無い笑みを浮かべた。
黙 って立っていれば野山に山菜 でも採 りに来た邑の子のようで、口を開けば巫 のような威厳 と不思議な神秘性を感じさせ……、だがそうして無邪気 に笑っている顔は、まるでただの少年でしかない。
くるくると印象を変え、なぜだか目が離 せない。不思議な魅力を持つ若者だった。
『……まあ、共に行ってやっても良いだろう。だが、お前のような童 に我を打ち直せるのか?』
素直になりきれずにそんな憎 まれ口をたたくと、真大刀はほんの少しだけ不機嫌 そうな顔になった。
「“童 ”ではない。他人 より育ちは遅 いが、私はこれでも十四 だ」
これが、俺と真大刀の出会いだった。こうして俺は彼の暮らす郷 へ共に行き、生まれ変わることとなったのだった。
地を
『
言っても
今まで俺を手にしたどんな人間も、俺の声を聴くどころか、俺の存在に気づくことすらなかった。また今度も意に反して戦場に連れ出され、血を浴びることになるのだろうと、
「やはり、
彼は俺を手に取ると、目の高さに
『お前は何者だ。
「いいや、私は
「どうだ?私と一緒に来ないか?戦に傷つき、
不敵な
俺は心が
『そうして打ち直して、我を再び戦場へと送り出すのか。この身に
冷たく
「ならば私は、他を
俺には初め、その言葉を信じることができなかった。
『大切な何かを守りきる力?そのような力、あるものか。大刀には
その言葉に、
「
真大刀はそこで初めて、
くるくると印象を変え、なぜだか目が
『……まあ、共に行ってやっても良いだろう。だが、お前のような
素直になりきれずにそんな
「“
これが、俺と真大刀の出会いだった。こうして俺は彼の暮らす
その名の通り青葉が風に
真大刀の
「真大刀。まったく君ときたら、何て無茶をするんだい?たった一人で郷を抜け出して
郷に帰り着いた真大刀に向かいそう言っておっとりと笑ったのは、背に
郷と同じ名を持つその神は、郷に住む鍛冶部達の
「申し
しおらしく頭を下げて見せながらも、真大刀の声に反省の色は全く無かった。その様子に鉄砂比古は
「こら。そういう問題じゃないだろう。君が何でもできる子だっていうのは知ってるけど、家族や皆に心配をかけてはいけないよ。もちろん、この俺にも、だ。君は俺が見込んだ百年に一人の才能を持つ
鉄砂比古の言葉に、真大刀は照れたように
「で、その
鉄砂比古は俺を一目見るなり、そう言って眉根を寄せた。
「はい。そのことにつきまして、実は鉄砂比古様にお
「うんうん。分かっているよ。
「はいっ!」
真大刀はきらきらした
『信じられんな。あれが本当に神なのか?神とはもっと物静かで厳格なものだと思っていたが』
思わず本音をこぼすと、すぐさま真大刀の
「失礼なことを言うな。あの
そう言われて俺は、神であるのに神らしくない
「
真大刀の声音には、鉄砂比古に対する敬愛の情が
『神、か……。いつか我もなれるであろうか』
「何だ?そなた、神になりたいのか?」
思わずこぼれたつぶやきに問いを返され、俺はあわてた。
『べ、べつにそんな
「何を
『
自分の才能をまるで
「ああ、そうだ。私がそなたを、いずれは神にもしてみせよう」
いずれは神にもしてみせる――その言葉が、俺達が望んでいたのとはまるで