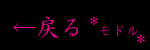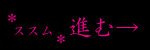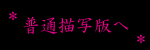| 第十章 嵐の |
やがて水柱は完全に形を変えた。天 高くに浮かぶそれは、水を統 べる神に相応 しく、どこまでも透 き通った水の躯 を持つ、とてつもなく大きな龍 だった。
眸 の色はそれまでよりも更 に青く深みを増して輝き、水精 のように澄んだ鱗 は日の光を浴びて虹 の色に煌 めく。それはまるで選 りすぐりの珠 を集めて作ったかのような、眩 いばかりの姿を持つ龍だった。
だが、その口から放 たれるものは身が凍 てつくかと思うほどに冷たく、恐ろしい咆哮 だった。
龍となった女神が吠 えるたび、風がざわめき、雲が吹き寄せられてくる。天 は見る間 に黒雲に覆 われ、すぐに雨が降り出した。滝津比古 と戦った時のような、一寸先も見えぬ土砂降りの雨だった。
雲梯 は激しく打ちつける雨を全身に浴びながら、喜びとも悲しみともつかぬ表情 で天 を仰 ぐ。
「……そうだ。これで良い。清めの雨がこの国の全ての罪・穢 れを洗い流す。そして神の怒りに触れれば、人々も心を改めよう。この国は生まれ変わるのだ」
雨は庭園の池をたちまちに溢 れさせ、宮殿 はまるでそれ自体が水の上に浮いているかのように、激しく波打つ水に取り囲まれていった。それでも嵐は止 むことなく、鳴神 と雹 を伴 い更 に激しさを増していく。人々は逃げ惑 い、少しでも雨風を凌 げるよう衝立 や几帳 の陰 などに潜 り込んでいた。
「何ということだ!この有様 では宮処 も酷 いことになっているぞ。この勢いでは今にでも霊河 が溢 れかねぬ」
「まさか、水神 様に護 られし我が国が、水による災 いで滅びると言うのか……!?」
「それゆえ私はこの企 てに異 を立てたのだ!鎮守神 様の泊瀬親王 に対するご寵愛 が真実 であるなら、途轍 もないことになると!」
「今更 何を言われる!こうしてこの場にいるだけで、そなただとて同じ罪人ではないか!」
「嫌だ!助けてくれ!誰かこの嵐を止めてくれ!」
罪をなすりつけ合い醜 く言い争う者に、他に救いを求め縋 るように泣き叫ぶ者――この場にいるほとんどの者が、この有様 に対して為 す術 を持たず、あるいは端 から為す気もなく怯 え騒 ぐばかりだった。
そんな中、怯 えもせず惑 いも見せず、己 が為すべきことを悟 っているかのように凛と声を上げた者がいた。
「水 統 べる水波女神 が一の巫女・雲箇 。これより鎮魂 の祭祀 を執 り行います」
このような状況にあっても尚 、雲箇は変わらぬ無表情でその場に立っていた。そして迷いなど一切ない眸 で空 に浮かぶ水波女神を見据 え、当たり前のように鎮魂 の舞 を始める。吹き荒 ぶ雨風に時折よろめき、わずかに動きを乱しながらも、それはまるで舞の手本を見ているかのように型に正しく沿 った、きちりとした舞だった。
雲箇は手足を大きく振り動かし、手首に巻かれた手纏 や、首に巻かれた頸飾 を揺らして拍子 を刻もうとする。だが、その音 は雨音 に遮 られて誰の耳にも届かない。そして女神はその舞に心動かすどころか、懸命に舞う雲箇をほんのわずかも振 り返ることなく嵐を呼び続けている。
衣裳 が雨で肌に貼 りつき、黒髪が乱れ崩れ、時に雹 に身を打たれながらも、雲箇は舞い続ける。だがどれほど舞っても全く変わらぬ女神の様に、初めてその顔に焦 りのような色が浮かび始めた。
「水波女神、我が鎮魂 の祈 がいはそのお耳に届かないのですか?我が霊力 が足りぬのでしょうか。それとも、それほどまでにあなた様の魂 は荒 んでいらっしゃるのですか」
その声には初めて己を――あるいは、己の今まで信じてきたものを疑うかのような迷いの色がにじんでいた。
「……無駄 なことですわ。どれほど高き霊力 を備 えていようと、どれほどの数の人間 を蹴落 としてその高き位 を手に入れようと、あなたは詰 まる所、鎮守神 様が御自 らお選びになったわけでもない仮初 の巫女。己 が位を守るためには手立てを選ばぬ、あなたのような者の祈 がいを、鎮守神様がお聞きになるはずがありませんわ」
海石 の冷たい声に、雲箇は怒りの眼差しを向ける。
「最早 八乙女 ですらない者が何を言うのです。たとえこれまで一度 も鎮守神様の御目にかかったことが無くとも、私は紛 うことなく彼 の女神の一の巫女です。鎮守神様が荒水宮 にお籠 もりになる前に定 められた大宮の掟 に従い、魂依姫 の座に就 いたのですから」
「掟など所詮、真 の理 に敵 うものでは……」
海石は雲箇の言葉に異を唱 えかけ……だが、何かを思いついたようにふいに黙 り込んだ。
「……そうですわね。あなたが真に鎮守神様の一の巫 であるならば、神を和 ぐための弥終 の手立てを成し遂 げる務 めがありますわよね?」
海石は酷薄 に歪 んだ笑みで問う。その問いに、再び雲箇の顔から表情が消えた。
「神を和 ぐ……?鎮守神様をお止めする手立てか!?そのようなものがあるのか!?」
「あるのであれば早くしてくれ!このままでは宮殿 が保 たぬ!」
二人のやり取りに気づいた葦立氏の面々が一斉 に雲箇に群 がり詰 め寄る。
「こうなってしまってはもう、手立ては一つしかありませんわ。鎮守神様にお許しを乞 うため、贖物 を捧 げるのです。数多 の人間 の命を奪った罪を贖 うとなれば、並の財物 や供物 では受け入れていただけません。この罪に釣り合う贖物となれば人間の命――それも、それなりに高き位に在 る巫 の命でなければいけませんわ」
その言葉に皆の眼が雲箇に――霧狭司国 で最も位 の高い巫 である魂依姫 に集まる。
「雲箇を人柱に捧 げると言うのか?だが、それでは大宮から葦立 の血を引く姫がいなくなってしまう」
「なに、案ずることはない。まだ幼いが弟姫 の雲潤 を代わりに八乙女に据 えれば良い。さすがに魂依姫 の位に上るまでには時間 がかかろうが、止 むを得 まい」
葦立氏たちは初めのうちこそ戸惑いを見せていたものの、終 いにははひどく呆気 なく雲箇の命を見放した。
「いかがですの?他人 の勝手で己 が命を振り回されるご気分は。でもあなたは文句 など言える立場ではありませんわよね。あなただってご自分を魂依姫の位に就 けるため、数多 の人間 の命を振り回してきたのですもの」
どこか勝ち誇 ったような海石の声に無表情のまま振り返り、雲箇は心に内の読めぬ声で静かに告げた。
「何か心得違 いをしているようですが、私は魂依姫としての己に誇 りを持っています。命を惜 しみこの務 めを疎 かにするつもりなど露 ほどもありません」
雲箇はそのまま迷いのない足取りで、巨大な水海 と化 った庭園に向かう。
「水波女神 よ!一の巫女・雲箇がこの身をもって全ての罪を贖 います。どうかそのお怒りを鎮 め、和魂 へとお戻りください」
女神へ向けて声を張り上げ、そのまま雲箇は荒れ狂う水面 へその身を投げようと床を蹴 る。――だが、後ろから伸 ばされた手が既 の事でその腕 を捕 らえ、引き留 めた。
「駄目 だ!そんなこと、あの方 は望んでいない!」
己 が背より高い雲箇の身を無理矢理羽交 い絞 めにし、懸命に動きを封じようとする泊瀬に、海石が怒りの声を上げる。
「泊瀬様!どうしてお止めになるのです!?これがその婦女 の運命 なのです!自らの罪を贖 って死ぬのが、その婦女 に最も相応 しい死に方なのですわ!」
「たとえ如何 なる罪人 であろうと、国人 の命が喪 われればあの方 が哀しむ!それがあの方が荒魂 となったが故 のことならば、余計に御自らを責めて辛 い思いをなさってしまう!それに……」
泊瀬は一旦言葉を切り躊躇 う様を見せたが、すぐに意を決したようにその言葉を口にした。海石を確かに止められる、狙 いすました一言を。
「海石姫が憎しみに駆 られて他人 を死に追い込むような人間 になってしまったら、夏磯 姫が哀しむだろう!」
その言葉に海石は打たれたように動きを止め、目を見開 いた。その眸 はそのまま何かを探すように空 を見つめ、うろうろと彷徨 う。
「夏磯姫……。そうですわよね。もしもあなたが見ていらしたら、きっとこのような醜い私のことは、嫌いになってしまいますわね……。私はもう、あの頃の私ではありませんの。もう、あなたに合わせる顔など無いのですわ……」
己を嘲 るようにそう呟 くと、海石はその顔を隠すように両手 で覆 い、泪 を零 し始めた。泊瀬はそれを痛ましげに見つめるが、掛 ける言葉を探しあぐねているような有様だった。
「放 しなさい、泊瀬親王 。私には務めがあります。鎮守神様を鎮 めるという務めが!」
雲箇は尚 も抗 い、もがく。泊瀬は舌打ちし、怒鳴 るように叫んだ。
「あんたが身を投げたって、ミヅハ様が和魂 に戻られると決まったわけでは無いだろうが!」
その時、花夜がそっと俺の袖 を引いた。
「ヤト様。真に他に手立てはないのですか?水神 様を鎮 める手立ては」
その囁 きに、俺はしばし考え込んだ後 、答えた。
「確かではないが、あるにはある。雲箇姫は八乙女とはいえ、水神が直 に選び契 りを交 わしたわけではない、言わば仮初の巫 だ。だがこの場に、仮初ではない、水神の真の巫 として最も相応 しい者がいる」
「泊瀬親王 ですね」
「ああ。己 が課した戒 めを破って助けるほどに寵愛 する親王 だ。彼 の親王の言葉にならば、荒魂 となった水神も応 えてくれるやも知れぬ。しかし、この嵐の中ではいくら声を上げたとて、天 に浮かぶ水神の耳には届くまい。俺に翼でもあったならば、親王を背に乗せて水神の元まで昇 っていってやるのだが」
「翼なら、あります」
言って、花夜は腰 から五鈴鏡 を外し、俺の前に差し出した。俺は問うように花夜の顔を見つめる。
「分かっているのか、花夜。鳥羽 の霊力 は最早 尽 きる間際 の所まで来ている。鳥羽は霊 だけでこの世に在 るもの。霊力 が全て尽 きれば、この世から消え去り、二度 会うことは叶 わなくなるのだぞ」
「何時 かこのような日が来ることは分かっていました。心構 えは元よりできています。ここで何もせず悔 いを残したくはありませんから。それに……」
一旦言葉を切り、花夜は五鈴鏡を愛 しげに胸に抱きしめた。
「たとえ今は別れても、何時 かまた、何処かで会えるかもしれませんから。もしかしたら私はそれに気づくことができないかも知れませんが……。それでもまた何時か、この世界 のどこかで触れ合うことができると、私は信じていますから」
「生まれ変わり、か……。だがそれはおそらくこの世界 の外 にある理 だ。それが如何 なる形なのか、そもそも真にあるのか否 か、神たる俺にも分からぬのだぞ」
「良いのです。分からないからこそ、信じて、祈 がうのです。きっとそれこそが、人間 がこの世を生きるための力なのだと、私は信じていますから……」
そこから先は言葉にせず、花夜はただ強い決意を秘めた眼差しで俺を見た。俺は頷 き、泊瀬へ向け呼びかける。
「泊瀬親王 よ、命を賭 す気があるならば共に来い。水神 に声が届く所までお前を連れて行ってやろう」
だが、その口から
龍となった女神が
「……そうだ。これで良い。清めの雨がこの国の全ての罪・
雨は庭園の池をたちまちに
「何ということだ!この
「まさか、
「それゆえ私はこの
「
「嫌だ!助けてくれ!誰かこの嵐を止めてくれ!」
罪をなすりつけ合い
そんな中、
「
このような状況にあっても
雲箇は手足を大きく振り動かし、手首に巻かれた
「水波女神、我が
その声には初めて己を――あるいは、己の今まで信じてきたものを疑うかのような迷いの色がにじんでいた。
「……
「
「掟など所詮、
海石は雲箇の言葉に異を
「……そうですわね。あなたが真に鎮守神様の一の
海石は
「神を
「あるのであれば早くしてくれ!このままでは
二人のやり取りに気づいた葦立氏の面々が
「こうなってしまってはもう、手立ては一つしかありませんわ。鎮守神様にお許しを
その言葉に皆の眼が雲箇に――
「雲箇を人柱に
「なに、案ずることはない。まだ幼いが
葦立氏たちは初めのうちこそ戸惑いを見せていたものの、
「いかがですの?
どこか勝ち
「何か
雲箇はそのまま迷いのない足取りで、巨大な
「
女神へ向けて声を張り上げ、そのまま雲箇は荒れ狂う
「
「泊瀬様!どうしてお止めになるのです!?これがその
「たとえ
泊瀬は一旦言葉を切り
「海石姫が憎しみに
その言葉に海石は打たれたように動きを止め、目を
「夏磯姫……。そうですわよね。もしもあなたが見ていらしたら、きっとこのような醜い私のことは、嫌いになってしまいますわね……。私はもう、あの頃の私ではありませんの。もう、あなたに合わせる顔など無いのですわ……」
己を
「
雲箇は
「あんたが身を投げたって、ミヅハ様が
その時、花夜がそっと俺の
「ヤト様。真に他に手立てはないのですか?
その
「確かではないが、あるにはある。雲箇姫は八乙女とはいえ、水神が
「
「ああ。
「翼なら、あります」
言って、花夜は
「分かっているのか、花夜。
「
一旦言葉を切り、花夜は五鈴鏡を
「たとえ今は別れても、
「生まれ変わり、か……。だがそれはおそらくこの
「良いのです。分からないからこそ、信じて、
そこから先は言葉にせず、花夜はただ強い決意を秘めた眼差しで俺を見た。俺は
「
「母 さま、どうか霊力 をお貸しください!その御霊力でヤト様の御背中に翼を……!」
花夜 が五鈴鏡をかざすと、鏡面から鳥の形をした白い光が飛び出してきた。それは大蛇 に変化した俺に向かい真っ直ぐに飛んで来る。現身 の無いそれは、そのまま俺の身に融 けるように吸い込まれ、まるで熱き血潮が巡 るように身の内を駆 け巡る。やがてそれは潮 が噴 き出すように背から噴き出し、白く大きな光の翼と化 った。
花夜はその姿を惚 れ惚 れと眺 め、深く頭を下げてから俺の背に跨 る。泊瀬 もまた花夜に続き、恐 る恐 るといった体 で背に乗った。光の翼は力強く羽ばたき、背に乗った二人ごと俺の身を天 高く――水波女神 の浮かぶ場所まで運んでいく。
水神 の周りは相も変わらず凄 まじい嵐が吹き荒れていたが、その風雨が俺達の身に届くことはなかった。背に生えた光の翼がその羽ばたきの力により風を打ち消し、雨を遮 り、俺達を守ってくれていたからだ。だがその霊力 は目に見えて削 られていく。白く光る羽根が一枚 一枚 、翼から抜 け落ち、風に散って消えていくのが俺達の目にもはっきりと映っていた。
「ミヅハ様!どうかお鎮 まりください!このままでは多くの宮処人 が死んでしまいます!宮殿 や大宮の者達だけでなく、罪も無き巷 の民達さえもが死んでしまいます!」
泊瀬は声を振り絞 り、女神に呼びかける。目を下へと移 せば、既 に川と化した宮処 の道を腰 まで水に浸 かりながら逃げ惑 う人々の姿が小さく見える。市 などに設 けられた粗末 な造 りの小屋などは既に幾つも壊 れ、その材木が波の間 に漂 っていた。宮処のそばを流れる霊河 は土の色に濁 り、その川幅 を増 していた。この大河が溢 れれば、宮処に途方 もない害が及 ぶことは察するに難 くない。
だが女神はそんな泊瀬に対し、それまでとは全く異 なる、冷たく光る眸 を向けてきた。
「罪なき人間 などおらぬ。巷 の民達だとてそうだ。己 が欲のため容易 く他人 を裏切り、また身近で悪 しき罪が行われていようと見て見ぬ振 りをする。妾 はそのような穢 れた世間 を、水を通してずっと見てきた。荒魂 とならぬよう酷 き事から目を逸 らしていても、それでも分かってしまうのだ。人間 の心は救いようもなく荒 んでいる。この国は疾 うの昔にもう腐 り果てておるのだ」
その声には、優しさも慈 しみも哀しみも、一切感じることができない。伝わってくるのはただ、激しい怒 りのみだった。
「この国は変わらねばならぬ。そのためには血と泪 が要 る。時代 の生贄 となるものが要るのだ。――喪 って初めて気づくような重大なものを失 くして初めて、人間 は目覚め、心を改める。人間 はそうして争いと平安を繰 り返し、人の世 を紡 いできたのだから」
それは時代 の流れに振り回され、弄 ばれることしかできない人間 の身からしてみればあまりにも情 の無い、冷たく酷 い理 だった。泊瀬は頬 を打たれたかのように目を見開 き、呆 けたように女神の姿を見つめる。
「ミヅハ様!どうしてしまわれたのですか!?そのような、人間 を駒 か道具のように見下 した冷たい理 は、あなたには似合わない!あなたはもっと優しい方 だったはずです!国人 ひとりの死にさえ泪 を流すような、そんな方だったはずです!」
「親王 よ、荒魂 とは斯様 なものなのだ。怒りや絶望に心を奪 われ、それまでと同じ物の考え方ができなくなってしまう。まるで恰 も人が変わってしまったかのように、な。これまでと同じ心積 もりでいては言葉など通じぬぞ」
俺は泊瀬を諭 すように言葉を掛 ける。
「だが、だとすれば何を言えば良いのだ!どうしたら元のミヅハ様に戻ってくださるのだ!」
どうすれば良いのか分からず癇癪 を起こしたように叫ぶ泊瀬に舌打ちし、俺は女神に向き直った。
「水統 べる女神よ、どうかその魂 を鎮 め給 え。お怒りはご尤 もなれど、弱く、愚 かしく、己 が欲さえ碌 に御 することもできぬ人間 という生き物が罪を犯すは仕方のなきこと。罪を犯さずには生きられぬ彼らを、どうか憐 れみ、赦 し給え」
その言葉に、女神はひどく冷 めた眼 で俺を見た。
「その言葉を汝 が口にするのか。我が眷属 たる蛇神 の身でありながら、我に逆 らう神よ。我には視 えるぞ。汝の心の奥深く、未 だ癒 えぬ深い傷があるのを」
その言葉に、俺はぎくりと身を強張 らせた。先ほどの言葉が俺の本心から出たものではない、女神を宥 めるための上辺 だけの言葉であることを、俺自身がよく知っている。本当は俺も、人間 の愚 かさを赦 せてなどいない。俺もかつて愚かな人間 と人間 との争いにより、大切なものを失っているからだ。
胸の底の秘めた所に封じ込め、いつもは見ないようにしている深い傷――それを、どこまでも青く透 き通った女神の眸 に見透 かされている気がした。
「汝 も未だに憎んでいるのであろう。汝の大切なものを奪った人間 の愚かさを。汝はそれを人間 の弱さゆえ赦 せると申すのか」
その声は冷たく厳しいままだというのに、俺にはどこか甘く誘うようにさえ聞こえた。
俺の大切なものを奪った国を、者たちを、壊してやりたいと幾度 思ったことだろう。だが、俺にはそれを為 すだけの力など無かった。
ずっと忘れようとしていた怒りや憎しみが、女神の言葉により胸の底から湧 き上がり、心が激しく揺 さぶられる。
「思い出すが良い。そして解き放て、その憎悪 の念を。共にこの国の者達に我らが怒りを知らしめようぞ」
まるで命を下すかのようにそう言い、女神は俺に視線を合わせてきた。刹那 、眼 の奥を雷 の矢に射抜 かれたかのような衝撃が走った。
眼 から浸入 り込 んだ何か途轍 もなく熱いものが、脳 にまで達し、そのままその奥へ奥へと潜 り込んでくるような感覚だった。
頭に激しい痛みが走る。それは脳 の奥深くを抉 られ、そこから何かを無理矢理引きずり出されるかのような、激しく、耐 え難 い痛みだった。
「や、やめろ……っ!頭が……頭が、割れ……っ。うぁ、あ、あぁああぁあぁああぁっ!」
気が狂いそうな痛みと共に、奔流 のようにめまぐるしく、眼裏 に蘇 る光景があった。
それは、俺が神となる前の記憶。俺が生まれて初めて友と呼べる人間と過ごした、愛しく……だが、癒やせぬほどに深く暗冥 い哀しみに彩 られた記憶だった。
花夜はその姿を
「ミヅハ様!どうかお
泊瀬は声を振り
だが女神はそんな泊瀬に対し、それまでとは全く
「罪なき
その声には、優しさも
「この国は変わらねばならぬ。そのためには血と
それは
「ミヅハ様!どうしてしまわれたのですか!?そのような、
「
俺は泊瀬を
「だが、だとすれば何を言えば良いのだ!どうしたら元のミヅハ様に戻ってくださるのだ!」
どうすれば良いのか分からず
「水
その言葉に、女神はひどく
「その言葉を
その言葉に、俺はぎくりと身を
胸の底の秘めた所に封じ込め、いつもは見ないようにしている深い傷――それを、どこまでも青く
「
その声は冷たく厳しいままだというのに、俺にはどこか甘く誘うようにさえ聞こえた。
俺の大切なものを奪った国を、者たちを、壊してやりたいと
ずっと忘れようとしていた怒りや憎しみが、女神の言葉により胸の底から
「思い出すが良い。そして解き放て、その
まるで命を下すかのようにそう言い、女神は俺に視線を合わせてきた。
頭に激しい痛みが走る。それは
「や、やめろ……っ!頭が……頭が、割れ……っ。うぁ、あ、あぁああぁあぁああぁっ!」
気が狂いそうな痛みと共に、
それは、俺が神となる前の記憶。俺が生まれて初めて友と呼べる人間と過ごした、愛しく……だが、癒やせぬほどに深く