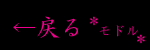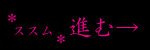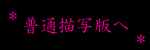第八章 雨下の攻防 |
「私は
偽りの名を告げ、用意した割符を見せ、
衛士達は割符を
ぎこちないながらも笑みを浮かべる
「そこの采女、
「え……っ、その……」
あわてて弁解を図ろうとする泊瀬を手で制し、海石は動じる様もなく、ただその笑みにほんの少し苦笑の色を混ぜた。
「申し訳ありません。その子は
その言葉と表情は芝居とはとても思えぬほどに自然で、衛士達も得心がいったように
「なるほど、一人だけいやに
「ばか、言葉を
衛士達の
「垢抜けぬ
複雑な思いで肩を落とす泊瀬に、花夜がひそめた声で
「仕方がありませんよ。美しく身を飾る
「いや、だから
すっかり海石を本物の
「失礼致しました。どうぞお通りください」
しかし海石は歩み出そうとはせず、手に持っていた漆塗りの
「これは衛士の皆様へ大宮からの差入れの品ですわ。いつも
「なんという
問いかけに海石はとびきりの笑みを返す。
「
「これが唐菓子か!まさかこの目で見られる日が来るとは……。しかし、我らは今はまだ
「ならばこの場で立ったまま召し上がればよろしいではありませんの。ここには滅多に人など来ませんし、お行儀が悪くても
「それもそうだな。我々がここを守るようになって大分
「それに、
衛士達は顔を見合わせ
「おお……、何と甘く柔らかいのだ」
衛士達は
「このような味、初めてだ。何だ、この不可思議な風味は……」
衛士達は互いに味の感想を言い合いながら唐菓子を口に運び続けていたが、その言葉は次第に
「え……っ!?一体何が!?まさか、毒でも盛ったのですか!?」
何も知らされていなかった花夜はぎょっとして衛士達に駆け寄り、おそるおそるその顔を
「毒ではありません。眠り薬です。この
海石は地に転がっていた
「
先ほどまでの海石の芝居に花夜が素直に賞賛を贈る。だが海石はそんな花夜の瞳の輝きから目を
「凄くなどありませんわ。大宮ではこのくらい肝が
門をくぐり抜けると、塀 の内にはさらに三重 の宮垣 がめぐらされていた。慎重な足取りでそこを抜けると、やっと別宮 そのものが姿を現す。
だがそれは、俺達の思いもよらなぬ姿をしていた。
「これが……別宮 なのですか?」
花夜が呆然と呟 く。それは社 などによくある素木 造りの高殿 などではなく、それどころか建物ですらなかった。
土を高く盛り、その外面 を石で葺 いて整えたその姿は、まるで上古之時 の王の奥墓 のように見えた。
「ええ。この古墳 が荒水宮です。この中に水神 様がいらっしゃるのですわ」
言いながら、海石はてきぱきと持ってきた荷を解いていく。取り出したものは奇妙な形の松明 だった。
「なるほど、古墳 の内に入るから手火 が必要だったのか。だが、何故そんな妙な形をしているんだ?」
「これは鰻 の松明ですわ。干してから幾度 も油を塗った蒲黄 の上に鰻 の皮を巻くと、雨の日でも火が消えないのです」
「雨?何を言っているんだ、海石姫。天 はこんなに晴れているのに」
泊瀬が采女の束装 を脱ぎ捨て、下に着ていた衣褌 を整えながら問う。
「水への備えは、しておくに越したことがないのです。八乙女の結界に現れるものは、おそらく水の霊力 を持つ精霊 か神なのですから」
海石は神妙な顔で古墳 の方を指差す。
「花夜姫、墳 の周 りに四つの柱と、その間を結ぶ標縄 が見えますわね?あれが八乙女の手による結界です。彼 の結界より一歩 でも内に踏み入れば、八乙女の召 び出した精霊 か神が襲いかかってくるはずです」
「……花蘇利 の神社 を守っていたのは水霊 でした。鎮守神 のいらっしゃる別宮を守るものであれば、きっとそれ以上のものなのでしょうね」
花夜は衣袖 を襷 でたくし上げ、額 に緋色 の蘰 を締める。沓 は脱ぎ捨て、首や手足には幾重 にも珠 を巻く。祭祀 にあたる巫女の正装だ。
花夜は大刀 姿の俺を両手で掲 げ持つと、両の眼 を閉じ、俺だけに聞こえる声でそっと囁 きかけた。
「ヤト様。お祈 がい致します。どうか私に力をお貸しください」
『ああ、無論だ。共に闘 おう、俺の巫女よ』
「はい!」
花夜は頷 き、泊瀬と海石を振り返った。
「では、参ります。お二人はどうか安全な場所に隠れていてください」
花夜は俺の手柄 を強く握りしめ、結界を踏み越えた。
途端、俄 に辺りが暗くなった。つい先刻まで晴れていたはずの天 はいつの間にか雲に覆われ、突如 として滝 のように雨が降り注ぐ。
「痛……ッ!何ですか、これ!?」
石塊 のような大粒の雨が俺の刀身 を、花夜の肌を叩きつける。それは単なる雨というよりも、まるで上から巨大な何かに押し潰 されようとしているかのような感覚だった。
目を開けても、息を吸っても、容赦なく水が入ってくる。花夜は俺を握りそこに立っているのがやっとだった。
『花夜、風だ。大刀 の風を起こし、雨を切り裂くのだ!』
「……はい……っ!」
花夜は呼吸もままならず、雨に視界を奪われながらも無我夢中で俺を振り回す。
刀身から巻き起こった鎌鼬 が周りの雨を吹き飛ばし、一瞬身が軽くなる。だが、それはほんの刹那のことだった。
切り裂いても切り裂いても、絶え間なく降りしきる雨はすぐに再び俺達を捕え、全身にまとわりつく。まるで雨の檻 の中で無為に踊らされ続けているかのように、一歩もそこを動くことができない。
『相手が雨では、いくら切り裂いても無駄ということか……。ならば、雲だ!花夜、天 へ向けて俺を振れ!雨雲 を吹き飛ばすのだ!』
「はい……っ!」
花夜はすぐさま俺を振る手を高く掲げ、天 へ向けて一閃した。だが、風の刃は雲までは届かず虚空 に儚 く消えてしまう。
『く……っ、俺の霊力 では届かぬのか……。どうすれば良いのだ』
「いいえ、ヤト様。雲を切り裂くというお考え自体は間違っていないと思います。届かぬと言うのなら、届くようにすれば良いのです」
言うなり花夜は俺を握ったまま、その場で弧を描くように踊りだした。
拍子をとって足を踏み、くるくると回りながら大きく俺を振り回す。
やがて、刀身から生 れた風が花夜の周りで渦を巻き始めた。それは徐々に大きくなり、雨粒を巻き込みながら上へ上へと高く立ち昇っていく。それはさながら、天 へ駆け昇る竜のようだった。
『竜巻 か……!なるほど、これなら雲にも届く!』
竜巻は見る間にその高さを増し、やがて雲の底に達した。黒雲に矛先で穿 ったかのように穴が開く。それはどんどん大きく広がり、やがて俺達の頭上にはぽっかりと蒼天 が顔を出した。
花夜は全身濡 れ漬 ち、肩で息をしながら口を開 く。
「……何だったのでしょうか。今の雨が八乙女の召 び出した『何か』なのでしょうか?」
『分からん。だが、鎮守神 を守る結界がこれで終わるとは思えん。気を抜くな花夜。古墳 の中に入るまでは何があるか……』
言い終わらぬうちに、再び天 がかき曇 る。墨色の雲は雷光を帯び、獣の唸 りのような鳴神 の音を轟かせた。
『何故 に神域を侵 すのだ。大刀の姿持つ神よ、そしてその巫女たる人の子よ』
薄闇の中、俺達の前に一人の人間……否、一柱の神の姿が浮かび上がった。
激しく流れ落ちる滝の水を思わせる白い髪が、稲光を受け時折蒼 く光って見える。その姿に、遠くで海石が息を呑 み叫んだ。
「あれは……滝津比古尊 !」
それは本来であれば恵みの雨をもたらす神の名。旱 の年に雨乞 いの祈りを捧げる神の名だった。
『大刀神とその巫女よ、今すぐ去 ね。さもなくば、再び滝 の雨を浴びせようぞ』
「滝津比古尊 !どうか聞いて下さい!私達は水神様に害を及ぼす気はありません!水神様をお救いするために参ったのです!」
花夜は声を張り上げて叫ぶ。だが滝津比古 は聞き入れなかった。
『水波女神 は自らの御意思でお籠 もりになっている。それを妨げる者は皆、彼 の女神の御意思に背く者。祓 うべき敵 だ』
「自らの意思でお籠もりになっている……!?」
『惑わされるな、花夜!滝津比古は八乙女の呪術 をかけられている!その言葉を真っ当に取り合ってはならぬ!』
「でも、これでは言葉でいくら説 いたところで分かってはいただけません。闘うしかないのでしょうか?」
花夜が迷うように瞳を揺らしたその時、海石がハッとしたように声を上げた。
「花夜姫!『石神 』を探して下さい。相手が滝津比古尊であれば、結界の内の何処 かに彼 の神の魂 が宿る御依代 の石があるはずです。その石神さえ砕いてしまえば、彼 の神の魂 はこの地に留まることができず、本国 へお戻りになるはずです」
「海石姫……。分かりました!ありがとうございます!」
海石へ向け一つ頭を下げ、花夜は石神を探すため走り出した。
『我に従わぬか。ならば容赦はせぬ』
低く唸るような滝津比古の声の直後、再び雨が降り出した。花夜は風の刃で雨を切り裂きながら古墳 の周りを回り、石神を探す。それは苦も無く見つかった。だが……
「……あった」
そう呟いたきり、花夜は途方に暮れたように立ち尽くした。ようやく見つけた石神は、花夜の背丈ほどもあろうかという巨石だった。しかもそれが、さながら天 の石屋戸 のように、しっかりと古墳 の入口を塞 いでいる。
『花夜、呆けている時ではない!とにかく大刀風 で切り裂いてみるのだ!』
「はい!」
花夜は石神へ向け、必死に俺の刀身 を振る。だが風の刃は石神に巻かれた標縄 を断ち切るばかりで、石そのものには疵 一つつけられない。降りしきる雨と闘いの疲れとで、花夜の体力はもう限界に達しようとしていた。
『もう良い、花夜!一度 退 き、策を練り直そう』
「でも、一度退いたら、次は警戒が増して余計に困難になるのでは……」
その時、花夜の腰の五鈴鏡 から声がした。
『花夜、鏡を天 へ向けてかざしなさい』
「母さま!」
花夜が鏡をかざすと、鏡面から鳥の形をした白い光が飛び出した。花夜の母・鳥羽 の霊 だ。
しかしその姿はかつてとは比べ物にならぬほど小さく儚くなり、うっすらと向こう側を透かしていた。この四年 の間に大分霊力 を削り、その存在自体を保てなくなりつつあるのだ。
鳥羽はそのまま一筋 に空 を駆 け、黒雲に飛び込んで見えなくなる。
直後、雲の中で稲妻の閃きが一層激しさを増した。鳥羽は雷雲の中を激しく飛び回る。まるで雲の中をわざと掻 き回しているかのようだった。
「母さま、一体何をなさっているのでしょう?」
雲間に見え隠れする鳥羽の姿を雨水を拭 って仰ぎ見ながら、花夜が疑問の声を洩 らす。その時、鳥羽が雲を突き破り戻ってきた。その全身には、ぱりぱりと音を立てて火花を散らす青白い光が宿っている。威火霊 の光だ。
『花夜、雷雲より集めたこの威火霊 の霊力 を、あなたの神に注ぎ込みます。構えなさい』
「はい……っ!」
花夜は慌 てて俺を握る両手を前へ突き出す。そこへすぐさま鳥羽の霊が真っ直ぐにぶつかってくる。鳥羽が全身にまとっていた威火霊 の霊力 が勢い良く俺の刀身 に注ぎ込まれ、吸い込まれていく。全身に霊力が漲 るのが分かった。
『行けるぞ、花夜!石神へ向け俺を振り下ろせ!この威火霊 の霊力、一気に解き放つ!』
「はい!ヤト様!」
花夜は残った気力を振り絞り俺の刀身 を持ち上げると、思いきり振り下ろした。大刀の先から光が迸 り、青白い炎が龍と化 り空 を駆ける。直後、視界が眩 い白光に染め尽くされ、凄まじい轟音が天地 を震わせた。
だがそれは、俺達の思いもよらなぬ姿をしていた。
「これが……
花夜が呆然と
土を高く盛り、その
「ええ。この
言いながら、海石はてきぱきと持ってきた荷を解いていく。取り出したものは奇妙な形の
「なるほど、
「これは
「雨?何を言っているんだ、海石姫。
泊瀬が采女の
「水への備えは、しておくに越したことがないのです。八乙女の結界に現れるものは、おそらく水の
海石は神妙な顔で
「花夜姫、
「……
花夜は
花夜は
「ヤト様。お
『ああ、無論だ。共に
「はい!」
花夜は
「では、参ります。お二人はどうか安全な場所に隠れていてください」
花夜は俺の
途端、
「痛……ッ!何ですか、これ!?」
目を開けても、息を吸っても、容赦なく水が入ってくる。花夜は俺を握りそこに立っているのがやっとだった。
『花夜、風だ。
「……はい……っ!」
花夜は呼吸もままならず、雨に視界を奪われながらも無我夢中で俺を振り回す。
刀身から巻き起こった
切り裂いても切り裂いても、絶え間なく降りしきる雨はすぐに再び俺達を捕え、全身にまとわりつく。まるで雨の
『相手が雨では、いくら切り裂いても無駄ということか……。ならば、雲だ!花夜、
「はい……っ!」
花夜はすぐさま俺を振る手を高く掲げ、
『く……っ、俺の
「いいえ、ヤト様。雲を切り裂くというお考え自体は間違っていないと思います。届かぬと言うのなら、届くようにすれば良いのです」
言うなり花夜は俺を握ったまま、その場で弧を描くように踊りだした。
拍子をとって足を踏み、くるくると回りながら大きく俺を振り回す。
やがて、刀身から
『
竜巻は見る間にその高さを増し、やがて雲の底に達した。黒雲に矛先で
花夜は全身
「……何だったのでしょうか。今の雨が八乙女の
『分からん。だが、
言い終わらぬうちに、再び
『
薄闇の中、俺達の前に一人の人間……否、一柱の神の姿が浮かび上がった。
激しく流れ落ちる滝の水を思わせる白い髪が、稲光を受け時折
「あれは……
それは本来であれば恵みの雨をもたらす神の名。
『大刀神とその巫女よ、今すぐ
「
花夜は声を張り上げて叫ぶ。だが
『
「自らの意思でお籠もりになっている……!?」
『惑わされるな、花夜!滝津比古は八乙女の
「でも、これでは言葉でいくら
花夜が迷うように瞳を揺らしたその時、海石がハッとしたように声を上げた。
「花夜姫!『
「海石姫……。分かりました!ありがとうございます!」
海石へ向け一つ頭を下げ、花夜は石神を探すため走り出した。
『我に従わぬか。ならば容赦はせぬ』
低く唸るような滝津比古の声の直後、再び雨が降り出した。花夜は風の刃で雨を切り裂きながら
「……あった」
そう呟いたきり、花夜は途方に暮れたように立ち尽くした。ようやく見つけた石神は、花夜の背丈ほどもあろうかという巨石だった。しかもそれが、さながら
『花夜、呆けている時ではない!とにかく
「はい!」
花夜は石神へ向け、必死に俺の
『もう良い、花夜!
「でも、一度退いたら、次は警戒が増して余計に困難になるのでは……」
その時、花夜の腰の
『花夜、鏡を
「母さま!」
花夜が鏡をかざすと、鏡面から鳥の形をした白い光が飛び出した。花夜の母・
しかしその姿はかつてとは比べ物にならぬほど小さく儚くなり、うっすらと向こう側を透かしていた。この
鳥羽はそのまま
直後、雲の中で稲妻の閃きが一層激しさを増した。鳥羽は雷雲の中を激しく飛び回る。まるで雲の中をわざと
「母さま、一体何をなさっているのでしょう?」
雲間に見え隠れする鳥羽の姿を雨水を
『花夜、雷雲より集めたこの
「はい……っ!」
花夜は
『行けるぞ、花夜!石神へ向け俺を振り下ろせ!この
「はい!ヤト様!」
花夜は残った気力を振り絞り俺の
「花夜姫!無事か!?」
「雷電 が落ちたように見えましたが、大事ありませんか!?」
泊瀬と海石が蒼白な顔で駆けつけて来たその時、花夜はばらばらに砕け散った石神の前で疲れ果ててへたり込んでいた。
いつの間にか雨は止 み、滝津比古 の姿も消えていた。そして石神のあった場所には、古墳 の内へと至る穴がぽっかりと暗い口を開けていた。
「大丈夫です。怪我はありません。泊瀬様、海石姫、ここから中へ入れそうですよ。早速 参りましょう」
言って花夜は立ち上がる。だがその身体はふらりとよろめき傾 いだ。俺は咄嗟 に人の形に戻り、その身を支える。
「無理をするな。まだ一人で立ち上がれぬのだろう?」
「でも、今の音を聞きつけて他の衛士達が飛んでくるかも知れません。もたもたしているわけには……」
俺はため息を一つつき、花夜の身を横抱きに抱え上げた。
「これならば文句はあるまい」
「ちょ……っ、ヤト様っ!」
顔を真っ赤に染めて慌 てふためく花夜を無視し、俺はそのまま古墳の中へ足を踏み入れた。
中は古の王の墓と同じように入口から石の壁に覆われた細い道が延びていた。ひいやりと冷たい風の流れるその道を、赤く揺らめく松明の灯を頼りに進む。
やがて細い道は終わり、少し開 けた室 に出た。壁には色鮮やかな文様が描かれ、突き当たりには人一人がやっとくぐれるほどの狭い穴が開いている。
「彼 の先に、ミヅハ様が……」
泊瀬は譫言 のように呟 くと、その穴へ向けふらふらと走り出した。しかし、泊瀬の身がその穴をくぐる寸前で制止の声が投げられる。
『待て』
その声は石室 の壁に谺 し、幾重 にも重なって聞こえてきた。
「何者だっ!?」
『人の子よ、その門 をくぐることは罷 りならぬ。今すぐここを立ち去るのだ』
暗闇にぼんやりと神らしきものの姿が浮かび上がる。それは一つだけではなかった。一柱、また一柱と、次々に姿を顕 した神々は、石室の壁に沿い、俺達をぐるりと取り囲んだ。
「天水分神 に地水分神 、太水神 に花浪神 、御井神 に大水主尊 まで……!」
海石が居並ぶ神々の名を呟 き息を呑む。それは全て水に関わる神々の名だった。
「水に関わる神々よ!どうかそこを通してくれ!ミヅハ様に会わせてくれ!」
泊瀬は必死に懇願する。だが神々は首を縦には振らない。
『ならぬ。水波女神 はここを出ることを望んではおられぬ』
「嘘だ!だって、彼 の方はずっと泣いていらっしゃるんだ!国で悪いことが起こるたびに、ご自分を責めて、嘆いて……。ミヅハ様がお出ましになられれば、国の悪事は減る!彼 の方があれほどに嘆かずに済むんだ!俺はもう、彼 の方のあんな顔は見たくない!俺は、彼 の方に笑って欲しいんだ!」
『その口振り、まるで水波女神と見 えたことがあるとでも言いたげだな』
『久しくここに籠もられておいでの水波女神と見える人の子などあろうはずがない』
『汝 は何者だ?名を何と申す?』
泊瀬は神々の訝 しみ値踏 みするような目にも怯 むことなく、堂々と名乗りを上げた。
「我が名は泊瀬。霧狭司 の国王と射魔 氏 の出の后・波限 との間に生まれた親王 ・泊瀬だ」
その名乗りに神々はざわめく。
『なんと……。霧狭司国 の親王 か』
『その名は聞いたことがある。そうか、汝 が水波女神 の寵愛を受けし親王 か』
しばし沈黙し顔を見合わせた後、神々はすっと道を開けた。
『通るが良い。汝であれば水波女神 もお会いになるであろう』
泊瀬の顔がぱっと輝く。
「水に関わる神々よ、感謝する!この恩は忘れない!」
泊瀬は神々に向け丁寧に頭を下げると、矢の勢いで穴の向こうに駆け込んでいった。俺達もその後に続く。だが最後に穴をくぐった俺にだけ、神々の洩 らした呟 きが聞こえてきた。
『……お会いにはなるだろう。しかし、それだけだ。水波女神は決してここをお出にはならない。決して、な』
「
泊瀬と海石が蒼白な顔で駆けつけて来たその時、花夜はばらばらに砕け散った石神の前で疲れ果ててへたり込んでいた。
いつの間にか雨は
「大丈夫です。怪我はありません。泊瀬様、海石姫、ここから中へ入れそうですよ。
言って花夜は立ち上がる。だがその身体はふらりとよろめき
「無理をするな。まだ一人で立ち上がれぬのだろう?」
「でも、今の音を聞きつけて他の衛士達が飛んでくるかも知れません。もたもたしているわけには……」
俺はため息を一つつき、花夜の身を横抱きに抱え上げた。
「これならば文句はあるまい」
「ちょ……っ、ヤト様っ!」
顔を真っ赤に染めて
中は古の王の墓と同じように入口から石の壁に覆われた細い道が延びていた。ひいやりと冷たい風の流れるその道を、赤く揺らめく松明の灯を頼りに進む。
やがて細い道は終わり、少し
「
泊瀬は
『待て』
その声は
「何者だっ!?」
『人の子よ、その
暗闇にぼんやりと神らしきものの姿が浮かび上がる。それは一つだけではなかった。一柱、また一柱と、次々に姿を
「
海石が居並ぶ神々の名を
「水に関わる神々よ!どうかそこを通してくれ!ミヅハ様に会わせてくれ!」
泊瀬は必死に懇願する。だが神々は首を縦には振らない。
『ならぬ。
「嘘だ!だって、
『その口振り、まるで水波女神と
『久しくここに籠もられておいでの水波女神と見える人の子などあろうはずがない』
『
泊瀬は神々の
「我が名は泊瀬。
その名乗りに神々はざわめく。
『なんと……。
『その名は聞いたことがある。そうか、
しばし沈黙し顔を見合わせた後、神々はすっと道を開けた。
『通るが良い。汝であれば
泊瀬の顔がぱっと輝く。
「水に関わる神々よ、感謝する!この恩は忘れない!」
泊瀬は神々に向け丁寧に頭を下げると、矢の勢いで穴の向こうに駆け込んでいった。俺達もその後に続く。だが最後に穴をくぐった俺にだけ、神々の
『……お会いにはなるだろう。しかし、それだけだ。水波女神は決してここをお出にはならない。決して、な』