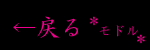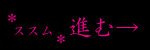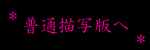第八章 雨下の攻防 |
「俺があの方と初めてお会いしたのは、まだ物心もつくかつかないかほどの幼い頃のことだった。お会いしたその時にはまだ、あの方の正体にも気づかず、ただ夢のように美しい方だと
「その夜、俺は
女神は、
『
驚いて顔を上げた泊瀬の目に映ったのは、それまで
『そうか、
『え!?なぜ、俺や母さまの名を……!?』
見ず知らずの相手に突然名を言い当てられ、思わず驚いた声で問うと、女神は淡く微笑んだ。
『霧狭司の
言って、女神はそのほっそりとした指でそっと泊瀬の
『そうか。この泪は
未だ何も話していないにも関わらず、女神は泊瀬の泪の
『……うん。皆が、母さまにひどいことをするんだ。
『あれは絶対に
女神は
『
『どうして!?』
女神の言葉に到底納得がいかず、泊瀬の語気は
『
険しい目で
『
言って、女神は諭すように言葉を続けた。
『泊瀬彦よ。
泊瀬はそれまでとは別の意味で呆然と女神を見つめ返した。姿形が美しいだけではない。これほどよく物を
『あなたは……一体……』
泊瀬にとって、それは生まれて初めて覚えた感情だった。こんなにも相手の名を知りたいと思ったのは初めてだった。
女神はそんな泊瀬の心を知ってか知らずか、
『
こうして、幼い
「初めのうち、俺はその夢をただの夢だと思っていた。だが、あの方はそれからも毎夜の如 く俺の夢に現れた。いや、違うな。あの方が『現れた』のではなく、実のところは俺の方が眠りのうちに霊 だけの存在となり、あの方の元へ通っていたらしい。何でも神の加護を受けた国の王の血脈 には、時折そういう霊力 を持った人間が生まれるらしい」
「泊瀬様は霧狭司の王室 の中でもとりわけ強い御霊力 を持ってお生まれになりましたから」
海石 が誇らしげな顔で説明を加える。泊瀬は一瞬ひどく煩 わしげな顔になったが、すぐに気を取り直すように表情を改めた。
「とにかく、さすがに俺もおかしいと気づいた。いつも同じ所、同じ方が出てくる夢など、ただの夢ではありえないからな。そのうちに俺は、あの方がこの国の鎮守神 であることを知った。……知ってしまった日は、なかなか眠りに就くことができなかったな。あの方がふいに、手の届かないような遠くへ行ってしまったような気がして」
そう語る泊瀬の瞳は、ひどく悲しげな色をしていた。その胸の内を察してか、花夜 がちらりと俺の方を見てから呟 く。
「神と人間 とでは、立場も生きる理 も、あまりにも違いますからね……」
「だがあの方はそれからも、神と人間 との隔 たりなど無いかのように気安く俺に接してくださった。宮殿 の中しか知らなかった俺に世間 の様々なことを教えてくださり、悲しい時には共に泣いてくださった。その上、水を統 べる神であるあの方が俺に親しく接してくださるおかげで、水に属する他の神々までが俺の祈 がいを聞き入れてくださるようになった。いつしか俺は水神に寵愛 された親王 と噂されるようになっていった」
「けれど皮肉なことに、それゆえに泊瀬様は他の氏族から疎 まれるようになってしまったのです。宮殿 をお出にならざるをえなくなったのも、元はと言えばそのことが原因なのですわ。鎮守神 様のご寵愛篤 き泊瀬様が次の代 の国王 になられることは当然の成り行きですのに、そのことを他の氏族の方々はどうしてもお認めにならないのです」
海石はそう言い、物憂 げに溜 め息をついた。泊瀬はそのことには触れず、話を続ける。
「あの方が封じ込められているということに気づいたのは、俺が十一 を過ぎてからだった。初めて豊明節会 に加わることを許された俺は、はしゃいであの方に言ったんだ。『宴 の場でなら現 のあなたと見 えることができますね』と。あの頃の俺は、鎮守神 であれば国の大事な祭祀事 や宴 には当然お出ましになるものと、何の疑いもなく信じていたんだ。だがあの方は寂しげに首を振って仰 った。『いいや、それは叶わぬ。祭祀 や宴の場では、霊 の宿らぬ神坐 を妾 の代 わりに祭祀 るのだ。妾はここを出ることができぬゆえ、な』と。その時俺は初めて、あの夢の場所にあの方が囚われていることを知った。あのような、暗く湿った場所にお一人で……」
泊瀬は己を責めるかのように顔を覆った。
「俺はすぐにあの方に言った。『俺があなたをここから出して差し上げる』と。だがあの方は悲しげに首を振るばかりで俺の言葉を受け入れてくださらなかった。それどころかあの方は『そのようなことを考えてはならない』『妾 のことは忘れ、人間 として穏やかに生きていって欲しい』などと仰 って、夢の中ですら会ってくださらなくなった」
泊瀬の声は悲痛な響きを帯 びていた。それは敬愛する女神に会えなくなったことを嘆いているというより、まるで想い人に会えなくなったことを嘆いているかのような、切なく激しい熱情を感じさせるものだった。
「俺はあの方に再び会いたいと、毎日必死に祈った。自分がそれまでどうやってあの方と会っていたのかなど分からなかったから、祈ることしかできなかった。そのうちに、不思議なことが起こるようになった。夢で会えない代わりに、日中 のふとした時にあの方の声が聴こえるようになったんだ。それも、おひとりで嘆いているような声ばかりが、幻のように耳をかすめていくんだ。あの方はどうやら水を通して宮処 の有様を見守っていらっしゃるようで、水辺 で悪事が行われるたびに、それにより傷ついた民のことを己 がことのように嘆かれ、お泣きになるんだ。だから俺は、あの方の御心 をわずかでも安らげて差し上げたくて、宮処の揉 め事に首を突っ込むようになったんだ。俺にできるのは、もうそれくらいしかないから……」
それきり言葉を詰 まらせた泊瀬に代わるように、今度は海石が八乙女 として知り得たことを語り始める。
「鎮守神様が封印されていることを知っているのは八乙女と国王 だけです。鎮守神様はもう久しく人間 の前にお姿を顕 していらっしゃいませんから、そのことを怪 しがる人間 もいるにはいるのですが、まさか封印されているなど誰も思いもしないのですわ」
「それはそうであろうな。神々の中でも風火水土 の神は別格だ。いかに強き霊力 を持っていたとて、とても人間 の敵 う相手とは思えぬ。一体その封印とは如何 にして成 されたものなのだ?」
海石 は静かに首を振る。
「分かりません。それはどの文書 にも口伝 にも残されていないことですので。けれど、何処 に封印されているかなら存じておりますわ。八乙女は今でも月に一度 、その場所へ参ります。結界に綻 びが生 れていないことを確かめ、鎮魂 の儀 により鎮守神様をお慰 めするのです。もっとも、八乙女の長 たる魂依姫 ですら鎮守神様に見 えたことはございませんので、本当に鎮守神様が御心を慰められておいでなのかどうかは知る由 もないのですが」
その時、それまで黙って話を聞いていた花夜がおそるおそる口を開いた。
「あの……そもそも何故 、水神 様が封印されているのですか?国を守るべき鎮守神を結界の内に封じ込めるなど、正気の沙汰 とも思えませんが」
「古き文書 には『大いなる災 いを防ぐため』だなどと、尤 もらしくもあやふやな訳 が語られております。けれど私にはその真 の訳が容易 く推 し量 れますわ。霧狭司には鎮守神様より授 かりし『祈道 』と、神の御霊力 を秘めた数多 の神宝 がございます。それらがあれば鎮守神様の御力がなくとも霧狭司は充分に国を守っていけるのですわ。むしろ慈悲深く他国 との戦 を厭 われる鎮守神様の存在は、領土を求め戦を欲する方々にとっては邪魔だったのではないでしょうか」
「そんな……」
「神を神とも思えぬ所業 だな。霧狭司の国人 はそこまで思い上がっていると言うのか」
「あくまでも私の当て推量に過ぎません。けれど充分に有り得る話ですわ。霧狭司には己が位 のためならば平気で他人 を踏 みつけにするような国人が山ほどおりますもの」
海石の言葉には妙に実感が籠 もっていた。まるでそうして踏みつけにされた人間のことを実際に目にしてきたかのような……。
「俺はどうしてもあの方を救い出したい。だが射魔 の氏族ですら、あの方が封じられていることを信じてはくれない。そもそも八乙女の結界に対抗しうる霊力 など、誰も持ってはいないんだ。だから……」
泊瀬はそこで言葉を切り、真剣な眼差 しで俺と花夜を見た。
「霧狭司とは何の縁 もないあなた方にこんなことを頼むのは筋違 いだし、ひどく勝手なことと承知している。それでも俺には他に術 が無いんだ。どうか、御力を貸してはいただけないだろうか」
その場に膝 をつきかねない勢いで泊瀬は悃願 してくる。花夜はそれをじっと見つめた後、小さな声で告げた。
「……少し、考えさせてはいただけませんか?」
俺はその返答に少なからず驚いた。花夜であれば二つ返事で頷 くものとばかり思っていたからだ。
「構 わない。そもそもが無理な頼 み事なのだ。考えてくれるだけでも充分 に有難 い」
「そうですわ。どうぞごゆっくりとお考えくださいませ。その間、大刀神 様と巫女様には我が宅 の客人 として精一杯のおもてなしをさせていただきますわ」
花夜はその言葉にも、ただぎこちなく頷 くだけだった。
「泊瀬様は霧狭司の
「とにかく、さすがに俺もおかしいと気づいた。いつも同じ所、同じ方が出てくる夢など、ただの夢ではありえないからな。そのうちに俺は、あの方がこの国の
そう語る泊瀬の瞳は、ひどく悲しげな色をしていた。その胸の内を察してか、
「神と
「だがあの方はそれからも、神と
「けれど皮肉なことに、それゆえに泊瀬様は他の氏族から
海石はそう言い、
「あの方が封じ込められているということに気づいたのは、俺が
泊瀬は己を責めるかのように顔を覆った。
「俺はすぐにあの方に言った。『俺があなたをここから出して差し上げる』と。だがあの方は悲しげに首を振るばかりで俺の言葉を受け入れてくださらなかった。それどころかあの方は『そのようなことを考えてはならない』『
泊瀬の声は悲痛な響きを
「俺はあの方に再び会いたいと、毎日必死に祈った。自分がそれまでどうやってあの方と会っていたのかなど分からなかったから、祈ることしかできなかった。そのうちに、不思議なことが起こるようになった。夢で会えない代わりに、
それきり言葉を
「鎮守神様が封印されていることを知っているのは八乙女と
「それはそうであろうな。神々の中でも
「分かりません。それはどの
その時、それまで黙って話を聞いていた花夜がおそるおそる口を開いた。
「あの……そもそも
「古き
「そんな……」
「神を神とも思えぬ
「あくまでも私の当て推量に過ぎません。けれど充分に有り得る話ですわ。霧狭司には己が
海石の言葉には妙に実感が
「俺はどうしてもあの方を救い出したい。だが
泊瀬はそこで言葉を切り、真剣な
「霧狭司とは何の
その場に
「……少し、考えさせてはいただけませんか?」
俺はその返答に少なからず驚いた。花夜であれば二つ返事で
「
「そうですわ。どうぞごゆっくりとお考えくださいませ。その間、
花夜はその言葉にも、ただぎこちなく